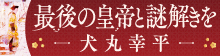第18回『このミス』大賞 2次選考結果 村上貴史
選考員の高評価・低評価が少数の作品に集中
訳あって疲労を抱えて選考会に臨んだのだが、あまり議論が紛糾せずに終わってくれてホッとしている。紛糾しなかったのは、高評価・低評価が例年に比べて少数の作品に集中したことが理由だろう。結果として昨年同様に7作を最終候補として選んだのだが、そこに至る経緯は、前回とは大分異なっていたのである。
というわけで、まずは最終候補について。
野地嘉文『贋者江戸川乱歩』は、戦中戦後の日本ミステリ界の動きが実に巧みに編まれていて愉しい。作中で言及されている実在のミステリ作品の内容(登場人物の造形など)に想像上の陰謀を重ねる手腕も達者。著者の才気を強く感じた。そんななかで作品の欠点といえば、甲賀三郎や横溝正史や木々高太郎を視点人物に設定しているが、それぞれのキャラクターの描き分けがあまり感じられない点だろう(そもそもそういうタイプの小説ではないが)。商品化するに際しての難点は、実在の人物を犯罪者として描いている点である。作品の末尾にエクスキューズは記されているが、正直なところこれで十分かどうかは疑問が残る。本書の魅力と直結する難点だけに、どうクリアできるかが課題。とはいえ、最終選考に残るに相応しい魅力を備えた一作であり、ここで落とすわけにはいかない小説である。
藍沢すな『はぐれた金魚は帰れない』については、心霊的なネタを裁判に巧みに絡めたものだと感心した。そのネタを多様に活かす手腕もお見事。とはいえ、検察側の特殊な証人の扱いがあっさりしすぎているなど、ネタを多く盛り込んだ割に使い切れていない一面があり、ここは改善の余地あり。魅力的な“絵空事”を生み出す才能を評価して最終選考に推す。
歌明田敏『模型の家、紙の城』は、“模型を読み解く”推理が愉しい。よいところに目をつけたものである。主人公が紙の専門家であるという設定も後半で活きていてよい。細かな伏線(フィギュアの品切れとか)もきちんと回収されていて嬉しくなる。同時に、東北まで車で突っ走ったりする破天荒さも魅力。総じて完成度の高い一作である。
泡沫栗子『君が幽霊になった時間』は、パート毎に異なる魅力を備えていた。第1部は、登場人物たちの語り口の面白さで魅了し(ここは他の選考委員は異論を唱えていたが)、第2部はその勢いのままに探偵役キャラと視点人物である男子高校生の絡みを愉しませてくれる。第3部は、謎解きの緻密さで読ませる。分刻みで真相を絞り込んでいく推理の迫力は圧巻。ここが二次通過の勝因である。とはいえ、説明そのものはあまりスムーズではなく、人の移動を示す図を追加するなど、改善を考えてもよかろう。最終的に青春小説として締めくくる点を含め、好感度は高い。
雨地草太郎『闇だまり』は、自分が一次予選で推した作品。自分が感心したポイントが他の選考委員からも支持を得られて嬉しい。
残る最終候補の2作品だが、個人的には積極的には評価しないが、他の選考委員による強い推薦を否定するほどではなかった。
走水剛『わたしの殺した力士』は、前半は相撲知識でグイグイ読ませてくれた。しかしながら、序盤で提示される力士の入れ替わり疑惑という一つのネタで長篇を結末まで引っ張るのは、なかなかに苦しい。中盤以降に一人また一人と登場人物に死を与えるが、目先の賑やかしに過ぎず、終盤では息切れが感じられた。
平島摂子『フィオレンティーノ』は、舞台となる土地も作中の時代も現代日本とは異なる物語。ガリレオ・ガリレイをはじめとする登場人物は豪勢(なおかつ他の選考委員によれば史実の扱いも適切とのこと)だが、ストーリーそのものの魅力は乏しく感じた。
以上7作が最終候補作である。
続いて、自分が一次選考で推したものの、最終候補作とならなかった3作品について。
蝋化夕日『ヒュプノでしかEGOに読ませられない』と荒木孝幸『15seconds gun―フィフティーンセカンズガン―』は、いずれも作者の奇想に惚れて推薦したのだが、その奇想について、他の選考委員の支持が決定的に得られなかった。滝沢一哉『厄介者』は、それらに比べればまだ高く評価されたほうだが、最終候補作7作と比較すると、他のお二方にはさほど魅力的ではなかったようだ。いずれも着想の妙が魅力の作品なのだが、こうした個性だけでなく、文章や人物造形、あるいは謎解きといった“他の作品と競って勝つための標準的な武器”を備えていれば、結果は異なったかもしれない。
次の4作品は、最終候補に推すリストからは漏れたものの、愉しく読めた小説である。
貴志祐方『ユリコは一人だけになった』は、学園劇としてなかなかよく書けている。学園祭のクライマックスなど、映像化向きであるとも感じた。その一方で、初代ユリコの誕生時期が不明という点は、もう少しうまく処理してほしかった。また、ある登場人物に疑いを残すラストもありきたりで残念。終盤をもっと丁寧に処理すれば、評価はもう一段上がっただろう。
岡辰郎『魚鷹墜つ』は、舞台がオスプレイの機内にほぼ限定されていて、コンパクトでよい。そのコンパクトな舞台に、様々な危機が集中している点も高く評価したい。残念なのは、オスプレイが着陸し、物語の本篇が完結した後に、あれやこれやの説明がだらだらと続くこと。正直なところ、これらの説明の大半は、読者としてはあまり関心のない事項である。また、シリーズ化を狙うかのような仕込み(エコーという組織)も不要だろう。まだまだ筋肉質にする余地がある。
澤隆実『EQ 彷徨う核』は、かなり読ませてくれた法螺話。世界を股にかけたこういう話は好きである。だが、いくつかのシーンがあっさりと処理されている一方で、視点人物に無理矢理トラウマを持たせているかのような過剰さがあったりして、設計図の段階でもっとバランスを調整しておくべきではなかったかと感じた。
小塚原旬『レナードの詐欺』も好印象。ただし、ある人物が本来隠しておくべき身分をあっさり明かしたり、重要なアイテムの現物があっさり登場してきたりなど、物語が都合よく進み過ぎていて最終候補には推せなかった。だが、主人公の設定(昆虫好き)が後半でちゃんと活かされている点や、結末で明かされるある因縁の扱いなど、好感を持てる点は多々あった。プロットをきちんと練ったうえでの再挑戦に期待したい。
続いて評価がもう一段低かった作品を4つ。
初宿遊魚『鰓を食らい、毒を矯む』の序盤におけるキャラクター描写はスムーズで、心地よく物語に入り込めた。敵役もしっかりと仇らしくてよい。中心となる隠れキリシタンと河童の謎解きは、論理展開は悪くはないのだが、これぞ正解という決め手感を欠いていた点が残念。主題の処理が不十分では、さすがに推せない。
西宮柊『パンドラの微笑み』のアクション描写はよかった。それに対して、陰謀の描写は説得力不足。また、物語の展開もメリハリに欠けモタモタしている。伏線もほとんどないまま、終盤で突然ある事実が提示されるという構成も再考すべきだろう。
今村ポン太『次の99人』は遺伝子編集が現実になった世界をそれなりにきちんと構築していたり、大量殺戮の際に死体の部位を“合計一人分”持ち去った謎の設定など序盤から中盤に書けては愉しく読めたが、後半での情報追加が多すぎてせわしなく感じた。
天田洋介『テトリス・ペレストロイカ』は、スケールが大きい割に、駆け足が過ぎる。冒険小説としては、意図的に軽妙に書いたのならともかく、描写不足を感じてしまうのだ。骨格そのものは悪くない仕上がりだし、主人公たちの魅力もある。磨けば光る小説だろう。
最後に残りの6作品について。
東雲明『時空裁判(本能寺)』の着想(特殊な設定で過去を探り、法廷バトルに仕上げる)は悪くないが、それだけに依存しているように思えた。法廷ものとしてのストーリーや歴史の謎の語り方でちゃんとした血肉を与えるべきだろう。
京家きづ『親指ほどの』は、叙述の技法を利用した新味はすこしだけあったが、まずは医学ミステリとして、このミス大賞の過去の受賞作と御自身の作品を読み比べてみて戴きたい。
遠野有人『自由の女神』は、電力自由化を契機に小さな会社が技術力で成長を目指すビジネス小説としての魅力は感じられた。後半に某国の陰謀が顔を出してくるのだが、電力関連の緻密さと比較してあまりに雑で興醒めしてしまう。
石澤明『イベントホライズン』は、視点があちこち漂っていて読みにくい。しかも全体としての主役も曖昧。かといって多視点で世界を構築し、その魅力で読ませる小説かというと、描写の濃淡に偏りがある。誤字も散見され、この小説の長所を見出せなかった。
佐竹秋緒『プラチナ・セル』の導入部は悪くない。主人公の造形も悪くない。だが、物語は徐々に勢いを失い、後半で失速している。山場の置き方や読者への情報提供に関して、ペース配分を再整理してみてはいかがか。
あだちえつろう『故漂 鳥取藩元禄竹島一件』からは、ミステリの要素を感じられなかった。あえて不利な賞に応募した理由はなんなのだろう。小説としてはまずまず愉しめただけにもったいない。
さてさて、最終候補作7作がどう評価され、どう競い合うのか。最終選考が待ち遠しい。