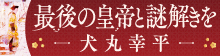第24回『このミス』大賞 次回作に期待
『オーマイガーる』首藤紘太郎
正直、タイトルを見て苦笑いしか浮かばなかったが、読み始めてすぐに姿勢を正した。
冒頭の「ばあちゃんは暗殺者だ」から始まる“ぼく”の幼い語りが、じつはネズミの視点だったことに意表を突かれ、さらに続く女の首吊り死体とその下で息絶えている赤ん坊を眺める刑事の諦念と苛立ちの描写に、文章センスに優れた書き手であるとわかった。古きよき翻訳作品のような会話文からは、文学的な香りを感じる箇所もあり、夫の生き方を受け継ぎ、街の悪を討つ八十二歳の老女の人生から目が離せなくなる。そして読み終え、その澄んだ愛の物語に胸が震えた。
小説教室に通えば身につけられるような筆力とは別格の才能は認める。しかし、ミステリーの物差しを当てると、プロットの弱さは否めない。強烈な謎、ユニークな設定、先を読めせぬ展開、仕掛けとサプライズの連打、そうした他の応募作群の読みどころに競り勝つには、センスだけでは限界がある。ミステリーにこだわらない創作という選択肢もあるかもしれないが、さらに研ぎ澄ましたセンスと練りに練り上げられたプロットで書かれた入魂の首藤作品を読んでみたい。応援してます。ぜひ、再びのチャレンジを!
『仮想の檻』冬海凛
名古屋に事務所を構える三十歳バツイチのデータ復元士・一ノ瀬陽介は、天才ハッカーである中学生の娘・美沙と二人で暮らしている。“サトシ・ナカモト”を騙る依頼人の指示を受けた二人は、古書店とジャズバーと宗教法人から回収したハードディスクを修復し、闇カジノの人身売買を突き止めた。一ノ瀬がカジノに潜入して女性を救った後、美沙は修道院の調査に乗り出すが、犯罪組織の陰謀で殺人容疑者にされてしまう。
データ修復士とハッカーの父娘を主役として、闇組織との戦いを描くサイバーミステリー。データ復旧、ネットログ、仮想通貨などの題材を掘り下げ、専門用語やログを生で記述するスタイルは、雰囲気作りの演出としても有効だろう。基本的にはヒーローコンビの活躍譚だが、娯楽小説としては不親切さが否めず、クライマックスの展開にも疑問が残る。情報と演出が魅力的なだけに、この濃度を維持したうえで、間口を広げたスタイルで再挑戦して欲しい。
『シリウスを討て』才川真澄
一二四七年、地中海に浮かぶキナイア島のグレタ村。ナタリーは養父である神父のフィリッポのもとで、他の子供たちも含めた家族として暮らしていた。ある日、野伏のガリアンが見知らぬ男を背負ってくる。男は死に際に「シリウス……」とつぶやき、息絶える。シリウスとは、子供狩りによって得た肉体を依り代に六百年を生きる死霊術師(ネクロマンサー)。じつはナタリーたちは、シリウスの子供狩りから救出された子供たちだったのだ。シリウスの襲撃に備え、ナタリーたちは山の要塞に籠るが、そこで殺人事件が起こる……。
伝奇×本格推理といった趣向で、物語の構成も整っており、書き慣れた印象を覚えた。惜しいのは、せっかく十三世紀の地中海の島という魅力的な設定なのに、出てくる人物は誰もが日本人的で、物語からこの時代と地域ならではの風習や異文化的な空気がほとんど感じられない点だ。神は細部に宿る。敵の「シリウス」という名をひとつとっても、六百年前から現地の人間たちの間で伝わってきたなら、もっといにしえの呼び名があるのではないか。
面倒な作業だが、こうした考察や作り込みを徹底することで、作品の厚みがぐっと増し、描写もより真に迫ったものになるはずだ。ページを開いた瞬間、令和の日本にいるのを忘れるくらい遥か遠くへと読者を連れて行ってくれる、そんなわくわくする物語を期待してます!
『Adieu…面影に沈む』倉田久代
写真家が訪れた、日本海に浮かぶ小さな島。その旧市街は、かつて大規模な地震で海に沈んでしまった。ここは彼女にとって憧れの地であると同時に、家族とともに事故に巻き込まれた辛い記憶の地でもあった。やがて彼女は、旧市街の沈没に隠された秘密に気づく……。
物語がミステリとして動き出すまでがかなり長い。そして、この長い助走の雰囲気は非常に優れていた。沈んだ旧市街のイメージ、町で出会った人々、残された詩。丁寧な語りによって、独特の世界が構築されていた。
そうした魅力が、物語がミステリーとして動き出すにつれて色あせてしまった。強大な権力の持ち主がある事実を隠蔽しようとした……という陰謀論的な展開は、うまく扱わないと荒唐無稽に見えてしまう。それ自体を魅力の核に据えた作品もあるけれど、少なくともこの作品の前半で形作られた雰囲気とは相容れないように感じた。
ミステリーじゃなくても良かったんじゃないか……と思わせる作品である。
『Hate my Heart』弓月冬彦
母殺しの容疑で逮捕された慎二は、自らの犯行を認めたものの、翌日には供述を一転させる。母を殺したのは自分ではない、自分の中にいるもう一人の別人格だ、と。
一方、慎二の交際相手・絵里が失踪し、家には絵里を誘拐したという手紙が届く。同様の事件が続き、警察は連続誘拐事件として捜査する……。
視点の切り替えを駆使して、複雑に入り組んだ事件を描いた野心あふれる作品。やりたかったことは非常に魅力に富んでいて、応援したい作品であることは間違いない。
ただ、複雑さをコントロールしきれていないところはもったいない。登場人物が多く、人間関係が入り組んでしまったため、例えば楠本碧に関する「驚き」の効果が薄れてしまっている。また、綾辻渚は複数の人間関係の交差点として用意されているように見えるが、かえって人間関係が分かりにくくなってしまった。登場人物を整理して、よりシンプルに見えるようにすることで、ミステリーとしての仕掛けもより有効に作用するのではないかと思う。
『死なないバディ』中村駿季
私立探偵事務所を舞台とした物語である。その事務所に押しかけてきて雇われることになったのが水城という男。彼は、自分は不老不死であると主張する。そして水城は本当に死なないのだ。例えば、骨が折れても数時間で元に戻る。そんな特徴を活かして、彼は次々と事件を解決していく。
設定と展開は魅力的だ。非現実的な、だが水城にとっては能力の範疇の手段で事件を解決し、それに現実の解決を与えるために後付けで探偵事務所の所長が知恵を絞るというスタイルが用いられている。そのスタイルそのものは相沢沙呼の変奏曲的であったりするのだが、不老不死という特殊能力には、物理的な不可能状況を生み出すという特色があるため、これはこれでオリジナルの魅力を醸し出している。
さらに、作品全体としては、不老不死の特長を活かして事件を解決していくだけではなく、最後に不老不死の人物ならではの決着も用意されている。この展開も本作の魅力だ。
とはいえ、ミステリとしての本書を支えるべきである所長の推理、すなわち不可能を可能にするトリックが弱いのが、そのまま本作の弱点となっている。ここで読者を感嘆させてくれれば、別の結果となったであろう。
『殺意と救命のボーダー』江原真理子
総合病院の救命救急センターに着任して一か月の仙石彩花は、全力で仕事に向き合うがゆえに患者の家族とぶつかり合うことが続いていた。そんなある日、病院に脅迫状が届く。ある男性弁膜症患者に対して治療を行ない、術後二十時間以内に所定の場所へ運ぶこと。担当医師は女性。治療費は全額負担で病院が立て替えること。要求を呑まなければ、別の患者に仕込んだ“薬”の回収は行なわれない、というものだった。彩花は院長から、気まぐれで“ワケアリ患者”ばかりを好んで手術するとウワサの凄腕心臓外科医・庵野淑祥とともに対応を命じられる……。
序盤からサスペンスフルな展開で、たちまち引き込まれた。総合病院で働くハードな現場の空気も伝わってくる。ただ、脅迫状の真相には膝を打てなかった。家族を想ってのこととはいえ、総合病院を巻き込んでの狂言は、さすがに無理があるのでは。また、庵野と院長が欠陥人工弁の回収・再手術のために密かに飛び回っているというのも、情報を伏せたままそんなことが進められるだろうかと疑問に思い、物語の後半でも読みながらすんなりと呑み込めないところがあった。こうした引っ掛かり、あるいは話の都合が優先されているように思える箇所を作らないため、よりプロット作りの段階での見直しと修正に力を入れてみるのも改善策のひとつだ。いま医療ミステリーは競争が激しいジャンルだが、医療の現場を真に迫る形で映した「江原真理子」にしか書けない作品を待っています!
『神話へ続く道』矢崎紺
1942年のドイツ、48年のパレスチナ、そして76年のウガンダと三つの異なる土地と時代を舞台に、現在まで続くユダヤとパレスチナの問題に真っ向から向き合った柄の大きな三部構成の物語です。それぞれホロコースト、イスラエル建国、エンテベ空港ハイジャック事件を核に、難しいテーマに真摯に取り組み虚実織り交ぜて複雑なプロットを構築していることは、末尾に上げられた参考資料の多さからも十分に伝わってきます。
にもかかわらず本賞の一時通過作として押せなかったのは、重厚なテーマと大きな物語に、ミステリ部分が釣り合っていないためです。第一章の犯行動機と読者にのみ仕掛けられた意外性、第二章の事件そのものの小ささと真相を巡る詰めの甘さ、第三章のあり得ないレベルの偶然に寄りかかった謎。いずれの事件も穴が多く、謎と論理と解決で満足させるレベルには達していません。ミステリ・パートになると途端にそれまでのシリアスな物語が軽くなってしまうのもマイナスです。読み応えのある物語に相応しい謎と解決を備えたミステリでの捲土重来を期待します。
『揺らめく脚』島村優輔
高級アパレルブランド向けの映像制作を任されたわたしは、偶然知り合った加納由紀子に協力を依頼した。上野駅のコンコースで足をひきずっていた彼女を見かけたのがそもそものきっかけだった。ダンサーおよび振付師でもある由紀子の膝には最新の人工関節が埋め込まれていた。その人工関節の開発者、医療福祉工学の教授の高橋から、彼女自身が踊るように仕向けてほしいと懇願された。彼女はそれを頑なに拒んだが、わたしはどうにか説き伏せ、映像制作にとりかかった。
バレエダンサーと人工関節を題材に、知的で上品な大人の風格漂うドラマティックな展開を堪能した。しかしミステリ要素はいささか乏しい。これだけなら「小説 野性時代 新人賞」「小説現代長編新人賞」「小説すばる新人賞」といったオールジャンル新人賞向けの長編だ。本賞を狙うのであれば、なにか強烈な謎をもってくるか、不穏な先行きを予感させるサスペンスが十分に展開していないと難しい。
『和菓子屋に探偵有り』結坂いと
強迫性障害で仕事を辞めた主人公が、あるきっかけで和菓子屋で働くことになり、そこで起きた事件を癖の強いイケメン若旦那が解いていくという連作。
キャラクターの描写が丁寧で生き生きしており、個々の事件もよく考えられていて好感を持った。特に主人公の強迫性障害をなんとかしたいという焦りやジレンマの描写と、それが事件の展開にかかわる構成もよくできているし、成長物語としても成立している。一次選考通過はほぼ間違いないなと思いながら読み進めた。
だが、全体を貫く謎になっているストーカーの正体があまりに簡単に、そして早々に見当がついてしまうのが致命的。会話の内容やお土産など、ヒントが直接的であからさま過ぎる。何より、他に該当しそうな登場人物がいないので、消去法でもわかってしまう。各話の謎解きにも言えるが、総じて伏線がわかりやすくミスディレクションを使えていない。ミステリとしての精度があがれば一次通過は間違いないだけに惜しい。
また、この手の設定には不可欠の、美味しそうな和菓子の描写や和菓子店の裏側の描写も足りない。食べ物職業系連作ミステリは、読者に「美味しそう、食べたい」と感じさせたり情報の面白さを与えるのも大事な魅力のひとつ。和菓子なら坂木司『和菓子のアン』という強力な先行作があるので、ぜひ自分だけの「和菓子描写」を見つけてほしい。
『夢魔の棺』南野海
夢の中で起きた孤島での連続殺人。そこに集ったのはすべて実在の人物で、夢で殺された人はその翌日、同じ死に方で現実社会でも殺されていく──という超常的な設定のミステリ。
特殊設定ミステリとして、夢を共有させる能力という設定と、途中で夢と現実が反転するという仕掛けは実によくできていた。反転の場面など、それだけで一次通過を確信したほど。ひとつひとつのトリックも(現実には難しいものもあるが)よく練られている。ザ・本格という謎解きにはわくわくした。
ただ、そこから先の展開と真相が、どうにも恣意的になってしまったのが残念。幕間でほのめかされていたとはいえ、明かされていなかった特殊能力や設定がどんどん出てきて、気づけば「富豪の狂った〇〇」「実はみんな〇〇」という真相は、意外というよりも「だったら何でもありじゃないか」という印象を与えかねない。
とは言え、このアイディアと筆力には期待大。夢を共通させる能力と夢の反転という大技はとても魅力的なので、そこを中心にして、「富豪の狂った〇〇」「みんな〇〇」という部分をもう少し現実的なラインにすることはできないか。現状では真相を構成する情報が多すぎて、中心となるサプライズが弱まってしまう。かなり書ける人だと思うので、構成を整理して再チャレンジしてほしい。
『彼のパパは返さない』池井軽
奥村広樹はある日、幼馴染みの友人トモから「ちょっと困ったことになった」と電話を受けた。その電話を、ちょっと仲違いをしていたトモとの仲直りのきっかけにしようと思い、彼の待つ部屋へと広樹はやってきた。その部屋で広樹は、トモと、トモが殺したという女性の遺体を目撃する。そしてトモに頼まれるのだ。遺体の処理を手伝ってほしいと。
物語はその後、意外な方向に転がっていく。なんとか遺体を埋めた広樹とトモは、それぞれ別行動をとるが、翌日広樹は、埋めたはずの女性、詩織と再会するのだ。一体自分は何を経験したのか……。
サスペンスをしっかりと読者に感じさせる筆致だ。状況を単に説明するのではなく、広樹を通じて、確かなものとして体感させるのである。これが出来ているが故に、死体遺棄に巻き込まれた際の戸惑いや緊張感が、実に生々しく伝わってくる。これはこの著者の大きな武器といえよう。
また、主人公の広樹は、妻とともに幼い息子を育てているのだが、妻は仕事で不在がちで、広樹が一人で子供の世話をしなければならない時間が大半だ。そんな広樹の心境もきちんと描かれていて、やんちゃな息子に手を焼く父親というシーンも、それこそ死体遺棄のシーンと同様にしっかりと読ませる。著者の描写力の確かさは、こうしたところからも感じられる。
不足していたのは、ミステリのプロットとしての説得力だ。文章のきめ細かさとは対照的に、真相の造りはかなり強引であり、地に足が付いていない。もっとシンプルな構成を案出し、それを磨き抜いたうえで、この描写力で小説として完成させれば、かなり上質なサスペンスが完成するのではないか。そんな期待を抱かせる作品だった。
『夢の国の消失』角張智紀
開園を一ヵ月後に控えたテーマパークが一夜にして消失したという派手で不可解な幕開けに関心しました。物語の大半を占めるのは、消失前夜にプレオープン招待客を含む七人のテーマパーク関係者の間で起きたパーク内での二件の殺人です。被疑者以外に犯行不可能と思われる事件の真相が、テーマパーク消失の謎と密接に絡んでいるところがミソで、大がかりな舞台マジックそのものの物理トリックもよく練られていると思います。
問題は、この壮大な犯行計画が実現可能とは思えず、真相が明かされても膝を打つに至らない点です。外連味たっぷりな本格ミステリを構築するために都合良く属性を付与された登場人物とあまりにも狭く類型的な人間関係、そしてそもそもこんなことをしなくても他に方法はあるという点はひとまずおいておくとしても、大規模な犯行計画を秘密裏に進めることが可能だと納得できるだけの説得力のある説明がない点は致命的です。独創的なトリックを生み出す力はあると思うので、いかに物語世界内でのリアリティとすりあわせられるかが今後の課題です。
『ユビキリ』竹鶴銀
中心にあるのは、捕らえた女性の万引き犯が頑として容疑を認めないという事態です。どうやら記憶喪失らしいのですが、読んでいる側としてはまず詐話を疑うところで、この態度のおかしさに拘泥していないで先に進まないと、物語は少しも広がらない。刑事の操作は万引き犯の周囲をうろうろするだけでは、女性が何を隠していようと、読者からすれば意外なことは何一つ起こらないのです。これは主人公である警察官の存在感が希薄なことにも結び付いています。この万引き犯の取り調べだけをずっとやっているわけではないでしょう。例えば同時に複数の案件を抱えた刑事が、意外な接点を見つけるとか、警察小説はもっと進化したプロットの作品がすでに多数書かれています。一つの思いつきで満足せず、それを魅力的に見せるための努力を続けてください。
『イァリスは殺人を知らない』石川拓郎
殺し屋の主人公が世界を司るような人工知能と対決することになる。その人工知能に強制されて三つの仕事を主人公が引き受ける、というプロットは神話的構造にもなっていて、奥行きがありました。設定だけ見れば非常におもしろくなりそうなのですが、この作品の残念な点は設定が観念的で、現実に着地するような説明が行われない点です。作者の中では十分に咀嚼できているのかもしれませんが、読者に伝わらなかったら意味がない。ミステリー的には、スリラーとしての構造はきちんとできているのですが、謎の提示とその論理的な解決という点では出たとこまかせな部分があり、納得感がありませんでした。虚構をいかに現実に織り交ぜるかが物語の作者に問われる技量ですが、ミステリーの場合は特に、地上の論理で解釈できる展開が必要になるのです。その意味でミステリーの賞への応募作としては、ややカテゴリーエラーだったのかもしれません。
『キューナナ』ウシジマタクロヲ
有名な経営者のもとを訪れた刑事が、27年前の事件を覚えているかと問いかけるところから始まる、1997年のある一夜を描いた犯罪小説。
カラーギャングを率いる男、その男と親しいギャル、カラーギャングに有名芸人をリンチするように依頼した落ち目の芸人。事態はどんどんエスカレートし、やがて陰惨な事態に……。
登場人物たちがずぶずぶと深みにはまって、幾つもの死体が転がる状況に至ってしまうストーリーの構築は見事。人数をむやみに膨らませることなく、最小限でたった一夜の錯綜した状況を描いてみせる。
ストーリーの組み立てはしっかりしているけれど、それゆえに登場人物たちが巧妙に動かされる「駒」のように感じられてしまうところがもったいない。
妙な表現になってしまうが、この作者なら、冒頭に語られる「灰色の記憶」を、もっと鮮明に描けるのではないかと思った。
『蝉時雨を浴びた茹で蛙』天田洋介
ユーチューバーの誠孝は、心霊スポットで死体を発見した。だが、その場にいた殺人犯によって毒ガスを浴び昏睡し、気がつくと陸の孤島と化した集落跡に放置されていた。フリー記者の侑人と女子大生の綾音に助けられたが、ふたりもこの地に攫われてきたという。誠孝と面識のあった駿少年もそこにいた。やがて彼らは奇妙な生活をつづける。屋敷にインスタント食品の備蓄があり、それで食いつないでいた。集落は絶壁で隔絶され、谷にはばまれているため、そこからの脱出は容易ではない。あるとき峡谷の西側でもめていた人たちと遭遇した。やがて吸血妖怪「空蝉」と信用金庫の一族の関係が徐々にあきらかになる一方、地下シェルターが発見され、広大な町がそこにひろがっていた。
冒頭の展開から流行りのホラーミステリかと思っていると、サバイバル活劇の様相が濃くなり、やがて大がかりな伝奇サスペンスへと転じていく。読んでいてひっかかるのは、強引な展開や乱暴な設定だ。それは壮大なホラ話たる伝奇ものを成り立たせる要素である一方、隔絶された状況なのに食料の備蓄がたっぷりあるなど、ご都合主義な部分も目立つ。細部をつめるか、それらしく見せるか。うまく嘘をついてほしい。
『ある探偵の物語』高円寺くらむ
週刊誌記者の梶山文治に、叔父の宗平の訃報が届いた。医師である宗平はNGOに参加してコンゴに赴き、そこで死んだのだという。自殺とのことだった。そんな叔父の死について掘り下げたいという気持ちを抱いた文治だったが、実家の岡山での葬儀の際に、宗平をかつて担任していたという教師から、一篇の小説を渡される。小学校のころに宗平が書いたという推理小説だった。
本作は、叔父の死を探る文治というストーリーに、過去に宗平が関与した三つの事件が、作中作や懐古譚というかたちで織り込まれている。そのそれぞれは、筆致にしても人物造形にしてもこなれており、心地良く読み進むことができる。
なので、読んでいる最中はあまり意識しなかったのだが、結末まで辿りついて、実はペース配分に難があることに気付く。前半で頁を使い過ぎたのか(あるいは執筆に時間を掛けすぎたのか)、結末に近付くにつれ、どんどん駆け足になっていくのだ。特に、宗平の死の状況については、終盤で思わぬ情報が明かされてさらに真相への興味が募るのだが、その新たな情報を十分に消化しないまま、作品が終わってしまっている。
次回はペース配分をきっちり設計して書いて戴ければと思う。そうすれば、後半を山場としてきちんと盛り上げることも出来るだろうし、結末のインパクトも出せるだろうし、余韻もコントロールできるはず。是非再挑戦を。
『死者の学校』柚崎諸人
他人との会話が苦手な大学生・詩嶋弧堂は、文芸サークルの先輩・坂巻沢永介に「静寂探偵」と呼ばれていた。詩嶋は坂巻沢に紹介された依頼人――女子高生の寺迂路加矢に奇妙な相談を持ち込まれる。子供を亡くした親が運営に依頼し、AIで再現した子供を通わせる“死者の学校”がダークウェブにあり、そこで学生が殺されたというのだ。詩嶋と寺迂路は関係者たちの話を聞き、モデルになった学校を突き止め、哀しくも異様な真相に迫っていく。
チャットでは雄弁になる人見知りの探偵と闊達な少女のコンビは、ベタなりに親しみやすい設定といえる。模造人格の殺害は必ずしも斬新ではないが、死者を再現した学校のアイデアは面白く、運営の真意が明かされる瞬間のインパクトは忘れ難い。仮想空間の作り込みが甘く、重要な部分を「不確定な要素で溢れている」で済ませた点は惜しまれるが、発想力には今後を期待させるものがある。捲土重来を待ちたい。
『我らの時代の終わり』佐伯功一郎
編集者だった祖父がなくなった。祖父の遺言で、借りていた本の返却を頼まれた佐伯功一郎だったが、手帳のリストの最後にある一冊だけが見つからない。古書店を営む父にその本について尋ねると『モモーン山の嵐』は手塚治虫の幻の作品であり、実在が確認されていないことを知らされた。佐伯は父の紹介で火の鳥書店の奥野を訪ねたものの、確かなことはわからなかった。そこで祖父と親しかったという編集者の立石の事務所を紹介される。ところが訪ねた先で死体を発見した。
なんと手塚治虫が赤本時代に発表したと記録にありながら単行本がいっさい見つかっていない作品があってその実話を元にした物語だ。これは手塚マニアでなくとも興味深いものだろう。だが肝心のミステリ部分があまりに弱く安易に思える。「古書の仕事に関わる主人公が、あるとき謎めいた作品について調べていくと、奇怪な事件に遭遇し……」というパターンで書いているのではなかろうか。だから主眼はもっぱらいわくつきの古書にまつわる蘊蓄とその騒動に向いている。主人公はただの駒、死体はまるで道具立て。文章もドラマも人物もしっかり書けているので、あまりにもったいない。語り手自身の運命を揺るがすような事件、それに結び付いた魅力的な謎や人間関係の綾などを丁寧にこしらえ、逆転劇であっと驚かせてほしい。
『速業殺人にうってつけの日』悠木允
作者はミステリーがとても好きなのだな、ということが伝わってきました。よくわからないのは速業殺人というモチーフで、これは密室殺人における、事件が実際よりも早く起きたように見せかけるための技巧です。ドアが開いた瞬間などに飛び込んで相手を殺害するというもので、だから「早」業なのですが、高速でナイフを投げる「速」業とは本来別のものなのでは。細かいことではありますが、物語の根幹にかかわる部分で作者がひとりよがりになっているところがある、と私は感じました。もう少し客観的に自作を眺め直したほうがいいのではないでしょうか。プロットも未整理な部分が目につきました。人物の出し入れなど、まだまだ刈り込めるはずです。
『少年の記憶、そして怪人』暁ただし
久々に、せんげん台(埼玉県越谷市)を訪れた語り手。そして四十年前にそこで過ごした時の出来事を回想する。
昭和53年、宝石店を営む藤寺氏のもとに「魔法博士」なる人物から、予告状が送られてくる。藤寺氏の所蔵する「スノー・クリスタル」なるダイヤモンドを頂戴する、というのだ。藤寺氏は探偵の片山優作に立会人を務めてもらうことにするが、連絡が取れない。
藤寺氏の息子の幸也君(小三)は、クラスメイトの星名君に事情を話す。星名君は片山探偵の友人と知り合いだったため、その喜多川青年を訪ねる。これを発端に、魔法博士と片山探偵、さらには星名君ら少年たちとの対決が始まる……。
本作は、入れ子状の形式で構築されている。現代が舞台の、外枠となるパート。そして過去が舞台の、中身となるパート。後者は、江戸川乱歩の少年探偵団シリーズのような少年少女向け探偵小説の体裁となっている。
文章はうまく、ジュヴナイル・ミステリ風に書かれているためもあるが、非常に読みやすい。
ただ、外枠部分にもっと大きな謎とその解決を用意して欲しかった。あるにはあったけれども、物足りなかったのだ。
江戸川乱歩の少年ものに言及があるのに、敵役の名前が「魔法博士」である理由について説明がないことも気になった(乱歩作品に魔法博士というキャラクターが登場する)し、後半に登場する怪人と乱歩作品との類似についても説明はなかった。
そして小説賞に応募するならば、その傾向などをよく研究して、それに相応しい作品で臨むべきだろう。作品の大半が児童向け小説として書かれている(しかも低年齢向けの「ですます」調になっている)本作は、『このミステリーがすごい!』大賞向けとは思えなかった。
もしまた『このミス』大賞に応募するつもりがあるなら、この賞に相応しい作品で挑戦して頂きたい。