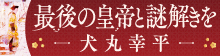第21回『このミス』大賞 次回作に期待
『鶴翼館暗号相続殺人事件』犬上義彦
莫大な遺産を残して、大企業の社長・稲ヶ崎雄一郎が亡くなった。彼の遺志により、北海道のダム湖の奥に隔絶した屋敷に関係者が集まった。娘、妹、亡妻の従弟。執事、秘書、専務、料理人、家政婦、管理人。フリーライター、そして探偵。
弁護士が、遺言状を開封する。そこには、暗号を解き明かして館に隠されたダイヤモンドを見つけた者に遺産を全て与える、と書かれていたのである。
かくして、暗号解読および宝探し競争が始まる。そんな中、不可解な状況でひとりが殺害されてしまう。更に、事件は続く。
はたして。暗号の解答は。ダイヤモンドのありかは。そして、面々の運命は……。
いわゆる「クローズドサークルもの」「館もの」という、ミステリの王道パターンだ。全体に文章はそこそこ読ませるし、小説としてまとまってはいるのだが――「それ以上の何か」がない。
キャラクターは描き分けられているが、もっとしっかり「キャラ立ち」させて欲しい。探偵は、もっとエキセントリックでもいい。小説なのだから、ちょっとばかり滅茶苦茶なぐらいが魅力的に感じられるはずだ。トリックや謎解きも、読んでいて「おおっ!」と思わせてほしい。
タイトルも平凡で、「これはどういうことだろうか! 読んでみたい!」という具合にそそられるものではない。
せっかくミステリーというエンターティメント空間を作り出すのだから、もっと「独自性」を打ち出した上で、読者をしっかり愉しませてください。
『善行の目的』沢波晴
東京行きの飛行機で急病人を助けようとした医学生が着陸後に誘拐され、山奥にある教会のような建物に連れて来られる序盤は強烈に目を惹いた。しかし、誘拐の動機や教会脱出までの流れに、いまひとつ緊迫感と説得力が足りず、盛り上がらない。悪夢の記憶の扱い方、途中で老人に奪われたはずの腕時計が部屋に置かれていた理由にも、呑み込みづらさを覚えてしまった。情報や伏線の提示の仕方を見直し、読者に物語の流れをしっかりと理解してもらう工夫、謎が明かされたときの納得度の向上をより意識し、さらなる創作に励んでいただきたい。
『月天から冀う』悪原霞
宇宙開発企業の代表である母を月で殺したということ以外に一切の記憶を失った少女。彼女が罪悪感を覚え罪を償うために、なぜ、どうして母を殺したのかを解明すべく世界中から十二人の天才を集めるという設定は独創的で面白いです。最後に大きな秘密が明かされ、それまで語られた十一通りの推理を根本からひっくり返す逆転劇が最大の見せ場ですが、もう少し丁寧に伏線を張って手掛かりを仕込んでおけばさらに効果的になったと思います。ミステリ面では合格点ですが、キャラクターが書き割りで、その国の人らしさや年齢、背景が伝わってきません。誰と誰が話をしていても差がないのです。そのため肝心の推理を語るシーンも単なる説明に終わっていて小説としては物足りません。文章力を磨き、キャラクターをいかに作るかを考えて再度挑戦してみてください。
『泥酔探偵』能登崇
これはなあ、惜しいなあと思いました。泥酔探偵がどういうものなのかはあえて書かないのですが、こういう着想で書かれた応募作はけっこう見るのです。私の知っている限りで言えば、もう二十年前ぐらいから別の作者が、別の形で書いてくる。それらが今までなぜ本になっていないのかといえば、設定に甘えて肝腎の謎が平凡だったからです。おもしろい探偵像を思いついた。おお、それはいいことです。でもその探偵が解く謎がどうでもいいものだったら、いくらいい設定でも意味がないじゃないですか。せっかくの泥酔探偵、ちゃんとした事件を解決させてあげたかったなあ。
『硝子の花婿』明瀬琴子
大富豪の娘の夫となる座を争う“宝探し”に参加させられた三七歳の男を主人公にした『硝子の花婿』もよく書けていた。新宿で花婿候補として声を掛けられ、何故彼が選ばれたのかという説明もないまま、長野の大邸宅に移動。そして五〇〇億円の遺産を相続した娘を巡る争いに参加させられる。その争いの様子が物語の中盤から変化していき、また別の構図が顔を出す展開が刺激的だ。変化が生じると同時に、物語の深みが増していくのもよい。つまり本作は、クレシェンド型の小説なのだ。そのまま結末までクレシェンドを続ければよかったように思うのだが、結末は大人しい。主人公が真相を知り(この真相はミステリ的に一ひねりあって悪くない)、一瞬感情を爆発させるのだが、大富豪の娘のこれからに決着をつけずに現場を去るのは、なんとも物足りない。その序盤の出足の鈍さと結末の弱さが、二次進出を阻んだ。
『SUGAR』西ユウ
話を聞くことを生業とする四十路の女が、男に捨てられて自殺しようとした女に”(男が管理する)自宅には汚いお金がある”と告げられ、仲間を集めて金を盗もうと思い立つ。夫の暴虐に晒される女、貧困にあえぐ女、介護に苦しむ少女などで結成されたチームは侵入に成功し、殺人があったと思しき現場に戸惑いながらも、約五億五千万円を手に入れた。しかし組織が黙認するはずもなく、彼女たちに追っ手が差し向けられる。展開がやや遅く、話が終わっていない印象もあるが、主要人物たちの生々しい描写は筆力を感じさせる。プロットに配慮した次作で化けることに期待したい。
『おしえ』菊田将義
歴史的な大事件を背景にした歴史ミステリーということでおおっと期待しながら読んだのですが、それはあくまで引きに使われているだけで、舞台は代替可能なものでした。そうなるとなぜその設定にしたのかが意味不明です。いや、本当に歴史上の大事件で、そこにミステリー的な謎が絡んでいるとなればエンターテインメント的な話題性は抜群だとは思うのですが、借景に借りているだけだったもので。その要素を抜いてしまうと、単に科学捜査が行われない変死事件の謎解きになるのではないでしょうか。いささか肩透かし感がありましたし、この設定ならたとえば現代の話にして、なんらかの事情で外界と隔絶した館の物語として書いても成立すると思います。着想に酔わない。きちんと物語の中で設定を骨肉化しましょう。
『仮象に踊る』小谷茂吉
捏造された動画、いわゆるディープフェイクなど技術の最先端を駆使した犯罪が中心に置かれ、よく考えられているという印象を受けました。これだけのアイデア量を詰め込むのは容易ではなかったでしょう。ただし、求めているのはノンフィクションではなくてフィクション、小説なのです。考え抜かれた犯罪計画であっても、読者の側から見てそれが解かれていくやり方が魅力的でなければあまり意味はありません。どうすれば読者が一緒になって考えてくれるか。手がかりをどのように示せば参加している感じが生まれるか。この作者に欠けている視点はそこだと思います。謎に引き込まれ、ひととき物語の中で遊ぶことができれば、これほどに複雑な構造を持つ物語ではなくても読者は楽しんでくれると思います。ここでちょっと創作の針路修正をしたほうがいいのではないでしょうか。
『コベナント』亜子漣
人気ブランドを運営する企業に、消滅したカルト教団、正体不明のテロリスト……と、多彩な要素を組み合わせて、複雑に入り組んだ構図を作り上げています。出し惜しみせずに詰め込んでいくスタイルには好感が持てるのですが、とにかく足し算で話を組み立てて、要素を詰め込みすぎてしまったところが残念です。ストーリーの大半が構図を提示するためだけに使われてしまって、バンクシー風の正体不明のアーティストや、公安の存在など、消化不足に終わってしまった要素も少なくありません。クライマックスで黒幕がじっくり真相を説明せざるを得なくなったのも、こうしたバランスの悪さによるものではないでしょうか。
でも、減点法評価に強そうな器用で無難な作品より、本作のように強いエネルギーがみなぎっていて、やりすぎて勢い余ってしまう作品に強い魅力を感じます。もっと要素を削ぎ落としても、十分に魅力のある作品に仕上がると思います。
『遠吠え』足立憂基
四角四面な元裁判官の老人と違法営業により女性を食い物にしている風俗店店長。まるで繋がりの見えない二件の殺人現場に残された「この殺人は赦される」というメッセージと、中盤犯人から警察に送られてきた手紙に記された「もうひとりだけ殺させてください」という一文の謎でラストまで引っぱっていくという構成は良いです。ただし過去編と現在編を交互に語る中で、犯人の動機とメッセージの謎が中盤過ぎには察せられてしまうため、ラストで作者が狙ったほどには衝撃が襲ってこない点が残念です。文章力・人物造形力ともに十分あるので次回作に期待します。
『VR少年院『ユートピア』殺人事件』白川尚史
VR(ヴァーチャル・リアリティ)ものは、プロアマ問わず特殊設定ミステリのネタとして人気上昇中だけに似たり寄ったりの話が多く、新人賞応募作ではオリジナリティは必須です。その点、洗脳教育と経済負担軽減からVR化した少年院で連続殺人事件が起きるというアイディアは独創的。個々の殺人トリックは工夫が凝らされているし、ラストで明かされる主人公の秘密も納得度が高い。ただし、あまりにも突飛な連続殺人の動機に説得力を持たせるには布石が不十分です。また探偵役があまりにも有能すぎて作者から与えられた回答を助手役に披露しているように感じられてしまう点もマイナス。本格ミステリのセンスに光るものが感じられるので捲土重来を期待します。
『宝石を纏ったドレッドノート』西田剛
戦前に作られた貴重なアコースティックギターの盗難事件にかかわる謎の物語。ギター工房の人々、事件を追う刑事たちの描写は手堅く、小説としては十分に読ませる出来栄えの作品でした。
ただし、作中人物が盗難事件を「謎」として成立させるべき理由がほとんどないのがこの作品の大きな弱点です。少なくとも「盗難」については、事実を隠して警察の捜査を長引かせるより、さっさと事情を話して捜査を終了してもらったほうが安全ですし、ギターの本当の出自を掘り返されるおそれもなくなります。作中の描写からすると、そういうことを考える時間の余裕もあったはず。
ミステリーとしてはともかく、ギターを作り、ギターを愛する人々の物語として魅力に富んでいて、今回担当した応募作の中で最も心地よく読むことのできた小説でした。今回は「これ、いちおうミステリーの賞だからなあ……」と泣く泣く見送らざるを得ませんでしたが、謎が謎である理由に説得力をもたせた次回作に期待しています。
『夫婦殺人協奏曲~完全犯罪バトル~』盾矢昇
筆に衰えが生じ始めたベテランミステリ作家と、その若い妻で二年前にデビューして勢いのあるミステリ作家という夫婦に諍いが生じ、お互いに三億円の保険金を掛けたうえで、無事殺した方が勝ちという完全犯罪バトルに挑むという一作。コミカルで突拍子もない設定がキュートだ。お互いの手数も多いし、テンポも良いし、勝った負けただけで終わらない展開の妙もある。著者ご本人にしか伝わらない指摘で申し訳ないが、絨毯の処理を手掛かりに大きな反転が生じるといった推理の刺激もある。では何故二次選考に残らなかったかというと、個々のネタの新鮮味や精度がもう一つだった、という点に尽きる。手数やテンポといった前述の美点で救えている面もあるが、ライバルたちとの闘いには勝てなかった。
『ニケの首』酒呑堂ひよこ
五年前に起きた連続少女惨殺事件が再び動き出す『ニケの首』。三人の少女から腕、足、胴が持ち去られるという猟奇的な事件を描く筆力も十分だし、五年後の現在にそのうちの腕が発見されて事件が再び動き出すという展開もよいし、その事件を、担当刑事と一七歳の少年という二つの異なる視点から探っていくという構成もよい。特に一七歳の少年については、立ち位置の設定もユニークだ。彼の姉が同じく五年前に水死体で発見され、自殺と判断されたが、彼としては殺されたという認識だった。つまり四人目の被害者というわけだ。そのうえで、姉の死の衝撃で、少年は姉に関する一切の記憶を失っているという設定も興味深い。後半で両者が合流し真相に迫って行く連係プレイも二段ロケット的な構成で愉しく読めるし、現在進行形のスリルも盛り込まれていて飽きさせない点も見事。刑事も少年も、周辺の人物を含めて癖の強いキャラクターが多いのだが、それぞれに存在感を与える技量も確かだ。犯人が計画を修正する動機も“なるほど”だし、それが現在の事件に繋がるというプロットも上出来。という具合に長所の多い本作なのだが、人と人との接点などに偶然が散見されたのが残念。刑事がたまたま入った店で少年と知り合う流れや、少年が関係者の息子と友人で情報を得られたり、など。こうした欠点を改善すれば、十分勝てる作品に、そして読者を満足させる作品になったはず。
『白と黒の迷宮』佐伯雄大
動物愛護団体の抗議に晒される実験施設で、施設長が実験用マウスに噛み殺された。マウスに攻撃性が認められず、現場にクロロホルムが充満していたことから、県警の真黒恭介は殺人の疑いを抱く。真黒は施設職員の白波真子とともに捜査を進めるが、動物愛護団体の会長が施設に不法侵入し、続いて別の職員が殺される。特殊施設ゆえの設備や環境は目を惹くものの、凶暴マウスの存在と計画の危うさが納得感を減じているのは残念。しかし謎解きの構成やクライマックスの演出は手堅く、あと一歩で先に進める書き手ではありそうだ。