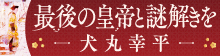第20回『このミス』大賞 次回作に期待
『さよならホームズ』赤埜常夫
日常生活に不満を持つ主人公が探偵能力を持つ友人と推理に興じることで、現実を乗りこえていこうとする。青春小説の要素を持つ連作ミステリーで、最後に主人公が乗り越えられない現実に直面し、成長しなければならなくなる。教養小説的側面にも好感を持ちました。作者がミステリーについて語りたいという熱意が前面に出ているのは微笑ましいのですが、謎の推理よりも蘊蓄の披露が優先されているように見えるのは、同人誌ならいざ知らず、商業出版では難しいです。謎があって探偵の推理があるというだけでは不十分で、手がかりの呈示や伏線配置など基本を忠実に押さえてもらいたいと思いました。
『カリブ海に降る』碧朱莉
国連職員の倉橋唯衣がハイチ共和国で惨殺され、海岸の木に逆さ磔にされた。公安キャリアの大使館職員・司馬仁は、唯衣の婚約者だった一ノ瀬豪右に調査を頼まれ、怪しげな国連職員・夏莉々と行動を共にする。消えた大使館職員・一色七々夏の捜索を進める二人は、国連上層部の白人による児童虐待を目撃した。海外が舞台の投稿作は多いが、本作のような視点を持つものは珍しい。謎めいた女との共闘には独特の緊張感があり、乾いたままの関係性も好印象。明確なテーマを読者に突きつける強さは特筆に値する。長い海外駐在経験を持つ著者だけに、背景の厚みを感じさせる描写力を会得すれば、一気に大化けする可能性もありそうだ。
『星の在り処』荒木公基
アフリカの実在する国家で大規模な虐殺が行われる。首謀者を突き止め動乱を収めるため現地に派遣されるのが主人公です。魅力的な題材ですが、展開されるのが観念的な議論ばかりなのが気にかかります。テロルを未然に防ぐ治安維持システムが全世界に導入されているという設定なので、虐殺とは何か、悪とは何かという議論が中心になるのはわかるのです。ただ、そうした負の要素が地上には今も存在するという現実から目を背けて、観念を語られても読者の胸に迫る物語とはならないのではないでしょうか。着想は買いますが、現実と虚構を接続する手続きが欠けていました。
『コーストガード・コンフィデンシャル』稲葉功
北朝鮮工作員によるテロ計画の情報を受け、海上保安官と公安捜査官が調査を始めた。二人はロシアのスパイを捕らえ、テログループが北朝鮮の反乱分子だと知る。いっぽうテログループはウランを入手し、東京駅に爆弾を仕掛けようとしていた。反目するバディ、ハーフのテロリスト、真の首謀者などのオーソドックスな要素を揃え、骨太のストーリーに徹した作りは評価に値する。その反面、型通りの展開をなぞっている感が強く、プロットや人物像に不満が残った。
『表裏のスペクトラム』遠条景彦
紙一重の差で二次選考に進めなかった。演劇と絡めた学園ミステリで、かなりよく書けていてたのしく読めた。なので、著者がこの作品を書きなおす場合に備えて、プロットの詳細を明かすのは控えておこう(もっとも、これだけのものを書ける人なのだから、おそらく全くの新作を書くことも出来るだろうし、そう期待する)。
そうした良作が紙一重ながらも「次回作に期待」に止まったのは、現時点での応募原稿に弱点があったからだ。まず、全三章のうち、第一章と第三章はテンポ良く流れているが、第二章が淀んでいる。緊迫感を維持しようという意志と工夫は十分ではないものの感じられたので、尋問や証拠探しに費やす記述量や情報提示のタイミングを調整すれば改善できるのではなかろうか。それに加えて、結末の弱さも気になった。何人もの動機が重なることでこの事件は成り立っており、その動機の説明が続くのだが、それらに説得力が不足しているのだ。「実は過去にこういうことがあったからこういう動機を抱きました」という説明が置かれているだけで、響いてこない。各ピースが煮え切らないまま連なってピリオドに到達してしまうのが、なんとも勿体ない造りだった。
とはいえ、ライバル次第では二次選考に進めていた作品である。この書き手の次の作品をまた読んでみたい。そう思わせてくれる才能だった。
『その先にあるのは』黒田雅之
実証実験中の自動運転バスが男を轢き殺し、推進派議員の秘書も盗難車で殺された。関係者たちの思惑が絡まる中、新米女性刑事が殺人犯を暴く。題材のユニークさと犯人像(動機)は目を惹くもので、講義の形で示される蘊蓄も面白いが、大学教授のパートが(解決のヒントに繋がるにせよ)ストーリーから乖離している。主要人物のパーソナリティが見えないのも残念。発想法は悪くないだけに、小説のスキルを磨いて再挑戦して欲しい。
『穢れた鉄槌』渋川紀秀
国税局資料調査課の主人公が、不正な脱税スキームを追いながら組織内の敵にも対峙する物語。テーマの選び方も、主人公の親友などのキャラクターの造形も悪くないのですが、主人公に次々と危機が押し寄せる展開に注力した結果、知能犯なのに何でも暴力に頼る悪役になってしまいました。租税回避スキームの印象が弱くなってしまったのも残念。要素を絞り込むか、バランスを考慮すべきかと思います。
『上書き保存』勢田春介
舞台は西暦2083年の日本。震災や環境破壊により東京が半分以上水没して首都でなくなったり、熱帯化が進んだりしている。国家としても衰退し、金持ちの上級国民と貧しい下層市民に二分化していた。語り手は、LAI(学習型人工知能)を搭載した人型ロボットの「ケント」。ケントのオーナーは、ベアリング製造会社「皆川金属加工」の社長の娘・姫子。社長令嬢と言っても零細な家族経営会社なので、下層市民だ。一家揃って、「ジトゥラ派神教」という新興宗教の信者である。
皆川金属加工はマイクロベアリング技術を確立しようとしていたが、高価なヒードオイルが手に入らずなかなか進まない。また姫子は、恋人に振られてしまう。
やけになった姫子は神教の集団見合いに参加し、結婚することに。ところがその披露宴当日に事件が起こるのだった。
――というSFミステリーだ。全体としての独自のテイストは、なかなか味わい深い。ただ、まだ小説を書きなれていないな、というところが多々ある。なかなか事件が起きない(「出来事」は起きるが「事件」が起きるのは半ばほど)のはミステリーとしてマイナスポイントだ。またSF設定にするなら、もう少し未来予測をすべきであろう。衰退した日本とはいえ、60年後ならもっと色々と変わっている部分があるはずだ。日本語も、もう少しこなれているべき。形容詞などの位置が悪いな、という場合が散見されたので、語順を入れ替えて最もすっきりした文章にすることを目指すとよいだろう。
もっと数をこなして、プロットの立て方もバランスよくなれば、より面白い作品を創れるようになるはずだ。
『極光の鷲』薗田幸朗
力作である。過去に本賞で2度最終候補に残り、いずれも受賞には至らなかったが、2度目の応募作には選考委員から刊行を希望する声も出たほどの書き手の作品だけあって、第一次選考を通過してもおかしくないレベルではある。この作品は、ナチスドイツによる原爆開発を日本人を絡めて描いた冒険小説であり、1940年代のドイツにおける原爆開発という素材は新鮮で、なおかつ科学的な特徴を丁寧に読者にも伝えようとしていて好感が持てた。御自身の長所をしっかり磨いてきた一作なのは確かなのだが、さて、短所についてはどうか。初回の最終候補作は冒険小説であり、定石通りのプロットをなぞってみせたにすぎないといったコメントなど、冒険小説としての新鮮味の欠如が短所として指摘された。翌年には、AIを題材としたSF味のある小説に方向転換し、こちらは前年より好評ではあったが、人間絡みのエピソードの難点や、ご都合主義との指摘で受賞は逃した。今回の応募作は、またしても路線を転換して原点回帰の冒険小説だったわけだが、題材にこそ工夫はあれど、新鮮味に欠けるという短所は残ったままだった。原子力に関する理系ネタや航空機によるバトルなど、長所に関しては見るべきものがあるのだが、3枠を争うとなると、短所が短所のまま残っているのでは、残念ながら厳しい。世の中には「新鮮味などいらないからいつもの味の冒険小説が欲しい」というような読者もいるだろうし、そうした読者には本作は好まれるであろうが、このミス大賞で勝ち上がるには、この磨き方(過去2回の選評をふまえた長所短所の磨き方)では難しかったということだ。力量は感じられるだけに、プロットの新鮮さ、人間絡みのエピソードの強化を徹底的に推進し、再挑戦して戴きたい。
『魔物館の殺人』辻端かおる
“一刀両断ババア”なる怪異によって大きく変質してしまった世界。“一刀両断ババア両断おじさん”の称号を持つハンターのケヴィンのもとに、かつてハンターだったアシェルの訃報が届く。ケヴィンは弟子のメイヴェルを連れ、アシェルの邸宅〈魔物館〉へと向かうが、そこで遺産相続をめぐる殺人事件に巻き込まれてしまう……。
怪異の名称からもわかるように、著者はかなりぶっ飛んだセンスの持ち主なのだが、残念なことに、そうした奇抜なセンスや狙いがさっぱり面白さとして活きてこない。怪異に名称以上の突き抜けた魅力はなく、“一刀両断ババア”の正体も気持ちよく膝を打たせてはくれず、消化不良に終わってしまった。
もし異形の本格ミステリを目指すなら、小手先の奇抜さでよしとせず、もっとミステリ部分を練りに練って、「よくもまあこんなことを考えたものだ」と仰け反るような域まで突き詰めるよう強くお願いしたい。
『テロメアの秘蹟』鳥羽谷美季
化石ハンターの主人公が人質を取られて秘宝を渡すように要求される。その敵と対決するために世界を股にかけた冒険が繰り広げられるという物語です。話の枠組み自体は冒険小説の骨法に則っていてするすると読める。しかし引っ掛かりがないとも言えます。化石発掘という魅力的な題材があり、結末にもそれが関わってくるのに、これは、と読者が仰天するような仕掛けにはなっていない。法螺を吹くにも下準備が必要です。ただ情報を羅列するだけではなく、背景の構築や伏線の貼り方など、話の持っていきようを工夫してください。駒として動かすだけではなく読者が感情移入可能な登場人物も必要だと思います。
『式神使いと死神の住まう島』野原駈
陰陽師と式神のコンビが、妖怪退治に赴いたいわく付きの島で殺人事件の謎を解くことになる。こうしたリアルに縛られない設定だからこそのアイデアを縦横に駆使して、孤島ものに新風を吹き込んでくれるかと期待したが、思いのほかスタンダードな話運びで、特別新味を覚えることなく尻すぼみのまま終わってしまったのがもったいない。推理を組み立てていく細やかな手つきや謎解きの見せ場作りは堂に入っており、終盤で某キャラクターに関するサプライズを用意するなど、最後まで読み手をアッといわせてやろうという意気込みもあって、本格ミステリの書き方を感覚的にはわかっている方なのだと思う。より地に足のついた正統かつ斬新な作品を目指し、ふたたびの挑戦を心よりお待ちしたい。
『空の底に咲く』南水梨絵
交通事故で死亡した令嬢の恋人から、生前、自分が送った手紙を彼女が読んだかどうか知りたいと言われた主人公・星子が、知人の男性とともに手紙の在処を探る。長編を支える謎としては小粒な上、手掛かりが露骨すぎて最初からどこにあるか見当がついてしまう点は大きなマイナス。恋人からの手紙を再読困難な場所に隠す心理も不自然です。昭和初期の雰囲気を出すために事件や事物を連ねていますが、残念ながら書き割りの背景にとどまっています。文章を書く力はあるので、ミステリとしてより練り込んだ作品で再応募されることを期待します。
『罪とX』百舌涼一
子供の頃に団地で女性の遺体を発見したものの誰にも言わずに済ませてしまった過去を引きずる主人公が、罪の意識を解消するために卒論のテーマとして事件を再調査する。巡礼スタイルにより過去の殺人事件を追ううちに、意外な真相が浮かび上がり、関係者の隠された素顔が明かされるというミステリの定番スタイルに則り、読ませる物語に仕上げていますが、作者の都合を優先させるために、登場人物同士の関係を繋げすぎている点はマイナスです。ただ、それ以上に問題なのは、実際に起きたまだ記憶に新しい痛ましい事件を全面的に下敷きにしている点です。登場人物の名前が関係者の実名を少しいじっただけという点を始め、配慮に欠ける点が散見されました。実在の事件に寄りかからない作品で再度挑戦してみてください。
『藪の中の殺人』矢間景太郎
芥川龍之介の薬に毒を仕込んで殺してしまった……という「前世の記憶」を持つ男の物語。たいへん誠実に、かつ堅実に書かれた小説だと思います。
残念なのは、ミステリーとしての驚きの弱さです。芥川龍之介の薬に毒を仕込んだという「記憶」は否定しないものの、死因はその毒ではなかったという結論に着地しますが、そうすると意外さでは差し引きゼロ。早い段階で明らかになる「前世」の人物の正体が、作中の最大の驚きになってしまいます。終盤に驚きを高めるような、構造の工夫が必要だと思います。
『一六年前の君へ』雪瀬ひうろ
売春行為が学校にバレそうになった女子高生と、たまたま彼女を庇うことになった男子クラスメイト。視点を交互に切り替えながら、ふたりの恋模様が描かれていくのだが、まずこのタイトルと章立てを見れば、どんな仕掛けが施されているか、ミステリファンなら即座に見抜いてしまうだろう。いま、登場人物の性別や年齢、時間・時代を誤認させる一手だけで読み手に真っ向勝負を挑むのは無謀というしかない。この仕掛けを踏まえたうえで、さらに二の手三の手を繰り出すくらいの戦略がなければ、二〇二〇年代のミステリとして歓迎されるのは難しいだろう。切ない青春小説として読ませるだけに、なんとも惜しい。
『才のために死んでくれ』和居ナラブ
主人公は、高校生の外河慎弥。彼の叔母・外河京乃は作家だったが、病気で死を目前としていた。京乃は学生時代の映画脚本を彼に渡し、映画サークルでの撮影時に起きた事件を再調査してくれと頼んだ。その脚本は「殺人の小道具だ。犯人は私」であるなどと、謎の言葉も残す。その後すぐに、京乃は亡くなってしまう。
葬儀の際、慎弥はかつて映画サークルに属していた人々に会い、話を聞く。人気俳優の如月柊矢。映画監督の三戸瀬玲。兼業ながら役者として活動する里崎愛果と花野智成。8年前の撮影合宿で、やはりサークルのメンバーだった庄司真希絵が自殺するという事件が起きたのだ。これは自殺ではなく、殺人だったのか。慎弥はなし崩し的に再調査を進める――というのが第一部。
後半は、京乃の未発表原稿「呪いの書物」の内容。四年前に「芸術船」なるアートプロジェクトが行なわれた旅客船上で発生した出来事にまつわるもの。ここでも、京乃は事件に巻き込まれていたのだ。
以上のような、意欲的な二部構成。会話で進むところはテンポがよく、なかなか読ませてくれる。全体に面白いミステリーを書こうという意気込みがひしひしと伝わってくるが、やや書き込みすぎ。もうちょっとスリム化して、展開を早くしないと読者はついてきてくれないだろう。一方で、書くべき細部はもうちょっと書いて欲しい(病院や、葬儀場や、大学のロケーションがどのあたりなのか、など)。減らす部分も、増やす部分も「わかりやすく」を旨とするべし。
句読点の打ち方についても、もう一工夫して欲しい。句読点の数が時々多すぎたり、位置がおかしかったりする。
色々な種類の小説を読み、読ませる小説とはどんなものかを、じっくりと体得して欲しい。ミステリーへの意気込みと読みやすさとの両輪が備われば、ぐんと評価は上がるはずである。