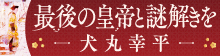第20回『このミス』大賞 1次通過作品 仏もときに幾何学する
純粋数学にパスカル哲学と
京都のお寺の魂の憑依が
きれいに結びつく不思議
『仏もときに幾何学する』東埜昊
主人公慈道は、東京の大学博士課程一年で純粋数学を専攻している。大阪で開かれた代数幾何学の研究会が終わって、同行の後輩、学部三年の明美に連れられて京都の寺巡りへ行く。
すると異常な状態の僧侶につかまる。途方にくれていると老住職が出てきて救ってくれる。僧侶は慈道に、転輪殿、まことの六道の辻をお探しくだされと訴えながら連れ去られる。優秀で慈道の面倒を見ている明美のおかげで、その場から逃れる。
慈道はいじめられて育って友人もいないコミュニケーション障害だから、明美が俗世の世話をするという関係である。ふたりはすぐに専門の数学を話題にする。
このふたりだけが探偵役かと思うと、翌日六地蔵のお寺を訪れたふたりに学部二年の京大生で仏教専攻の刈谷史織が、昨日の事件について聞きにくる。数学と仏教両方の専門知識が合体するユニークなミステリーの幕開けである。刈谷家は大金持ちという設定も少し後になって出てくる。
史織の案内で問題の僧侶の元へ行くと、住職が、昨日の光円という僧侶はこの一週間の記憶がなくて江戸時代の僧侶だと思い込んでいるという。しかも元は京大の数学科中退なのである。ここからむずかしい理論が展開されながら、現実世界では光円の住まいを誰かが探ったような気配があって、ミステリーの形も保つ。
ともかく高等数学や西洋哲学に霊魂がからむのだから、不思議さは三乗になる。それを慈道と明美の他愛ないやりとりがちゃんと救う仕掛けになっている。
少し無理っぽい犯人のような気もするけれど、これくらいのお話があって専門用語とバランスが取れているのだろう。
(土屋文平)