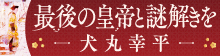第19回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
誘拐ミステリーのサプライズか、遺産相続もののキャラ立ちとハッタリか
今回は、『このミステリーがすごい!』大賞19回目にして初めて最終選考に新メンバーが加入。しかも、そのニューフェイスは、この賞にとって初の(!)女性選考委員となる瀧井朝世さん。これはもう、一波乱も二波乱もあるのでは……という大方の予想を覆し、3人の評価は意外にも過去最高のシンクロ率を記録。大賞の本命は、3人が揃ってAをつけた、呉座紀一『甘美なる作戦』と新川帆立『三つ前の彼』の2作に早々と絞られた。
『甘美なる作戦』はコミカルなタッチのライトなヤクザノワールかと思いきや、本筋は誘拐もの。なるほど、このパターンね。と、けっこう油断して読んでいたので、事件の真相が明かされたときは思わず茫然。いやもう、すっかり騙されました。いろんな手がかりは無造作に放り出されていたというのに、一生の不覚。いや、それにしても、まさかねえ。これはもう、21世紀最高の(または、すくなくとも令和最高の)誘拐ミステリーとして強力にプッシュしたい。
……と意気込んだものの、この小説には誘拐以外にさまざまな要素が過剰に投入されていて、どうも話がごちゃごちゃする印象は否めない。とくに、主人公たちが巻き込まれる殺人事件の真相(および解決の描き方)に難があり、出版には相当な改造が必要になりそうだ。
対する『三つ前の彼』は、強烈にキャラの立った女性弁護士もの。「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という前代未聞の遺言状を残して、日本有数の製薬会社・森川製薬の創業者一族に連なる森川栄治が死去。数百億円と目される財産目当てに、われこそは犯人と名乗り出る候補が乱立。彼らを集めて「犯人選考会」が開催されることとなり、われらが主人公・百合絵は、有力候補のひとりの代理人を引き受ける――と、ツカミはたいへん強力。しかも百合絵は、学生時代に栄治と3カ月だけ付き合った過去があり、元カノリストに記載されたひとりとして、別途、遺産の一部を相続する権利を与えられている(百合絵から見て栄治は「前の前の前の彼」、すなわち「三つ前の彼」にあたる)。百合絵はこの立場を利用して相続騒動の背景を探りつつ、依頼人が犯人に選ばれるように奔走する。
遺産相続ものの例に洩れず、分量の割に登場人物がたいへん多くなってますが、最小限の描写でうまく描き分けられているので、それほど煩雑には見えない。錯綜する背後関係をなんとか整理して、(強引ながらも)ちゃんと決着をつけたところも評価できる。
この2作のうち、前者のサプライズをとるか、後者のキャラ立ちとハッタリをとるか。それぞれに魅力的で甲乙つけがたく、大賞2作との声も上がったが、最終的に、プロットに大きな瑕疵がない『三つ前の彼』が僅差で逃げ切り、『甘美なる作戦』は新設の(というか従来の優秀賞から改名した)文庫グランプリに落ち着いた。
この2作に次ぐ評価だったのが、龜野仁『砂中遺物』。日本の大部分が近隣国(モデルは中国)の統治下にある並行世界を舞台にしたハイスピードな警察アクション。改変歴史SF設定の警察小説と言えば、レン・デイトン『SS‐GB』、マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』、ピーター・トライアス『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』など過去に名作多数。最近の例では、日露戦争にロシアが勝った時間線の東京を描いた佐々木譲『抵抗都市』がすぐ思い浮かぶところだが、本作で描かれるもうひとつの2020年代(推定)日本もそれらに負けないくらい魅力的だ。読みどころは、過剰な武器描写も含めて濃密かつスリリングなアクション・シーン。設定との合わせ技で、個性的なエンターテインメントに仕上がっている。こちらも即戦力ということで、『甘美なる作戦』とともに文庫グランプリに選ばれた。
惜しくも選に洩れた他の最終候補作3作も、それぞれセールスポイントがあり、ちょっと修正すれば商業出版レベルだろう。
高野ゆう『虐待鑑定 ~秘密基地の亡霊~』は、ユニークな設定の鑑定医もの。主人公は、人間の患者を診るのがイヤで法医学者になった人間嫌いの人物だが、なんの因果か、臨床法医として、児童虐待の鑑定を担当する羽目に。ところが、彼に虐待者だと鑑定された親たちが次々に殺され、否応なく事件に巻き込まれてしまう。主人公の設定は面白く、プロットも悪くないが、あまり必然性のない(しかも見え見えの)仕掛けがマイナス点。惜しい。
東一眞『クロウ・ブレイン』は、リーダビリティ抜群のバイオサスペンス。カラスを使ったバイオテロという発想は悪くないし、新聞記者ものとしても面白く書けているが、リアリティのハードルを上げているだけに、真相(および敵役の設定)に無理がありすぎる。筆力はじゅうぶんなので、ここまでハッタリにこだわらなくてよかったかも。
一方、厚労省の役人と捜査一課の刑事がコンビを組んで連続インフルエンザ脳症死の謎に挑む柊悠羅『悪魔の取り分』は、コロナ後の製薬業界ミステリー。まあまあ説得力はあるものの、その分、新鮮味に乏しい。既視感のある材料を使ってソツなくまとめすぎた感じで、こちらはもっと冒険してほしかった。
香山ニ三郎
満場一致で自ずと決定 大本命の受賞作
予選終了段階で、今年は粒ぞろいだという声が聞こえてきた。そういわれると、ヘタな読みは出来ないなと逆に内心ビビったが、最初の龜野仁『砂中遺物』を読んで一安心。
隣国に併合され三分割されたもう一つの日本。和人自治区で活動している非合法な拉致組織が中央政府の高官をさらおうとして失敗、新人メンバーの佐野由佳がとらえられてしまう。彼女は国連警察に移送されることになり、神奈川県公安局の雑賀充希が護送に当たるが、途中で謎の武装グループに襲われる。
ありがちなパラレルワールド活劇と思いきや、雑賀と由佳の逃走劇が切れ味鋭い展開を見せ始めると、後は最後まで一気読み。プロの作品でいえば、長浦京『リボルバー・リリー』を髣髴させる熟練の活劇演出。雑賀のキャラも立っているし(マスク嫌い!)、頭から大賞候補に出会えてよかった、よかった。
呉座紀一『甘美なる作戦』は誘拐活劇仕様のコンゲームもの。真二と悠人は暴力団の見習い。若頭の荒木田にこき使われる日々が続いていた。訪ねた高利貸しの家で殺人現場に遭遇したり、組の事務所に火焔瓶が投げ込まれて捜査を受けたりろくなことはない。やがて荒木田は新興宗教の教祖の孫娘を誘拐する計画を立てるよう二人に命じるが……。
前半はいろんなエピソードが錯綜するが、誘拐劇が始まってから一気に加速する。きちんと構成された群像劇演出から、ユニークな誘拐活劇へ、さらには驚愕のコンゲームへと展開していくストーリーテリングの妙が光る。本作はすでに一度別の新人賞で最終まで残っていて、そのときは残念な結果に終わったが、『このミス』大賞は逃しまへんで、ということで、これまた大賞候補にふさわしいかと。
高野ゆう『虐待鑑定~秘密基地の亡霊~』は児童虐待の鑑定にも当たる臨床法医学者が主人公。彼は鋭い眼力で鬼親の嘘を見破るが、自分自身は、親友が自分たちの秘密基地で首を吊った幼い頃のトラウマから他人を避けるようになっていた。やがて彼が鑑定した虐待の加害者の首吊り死体が運ばれてくる。
臨床法医という仕事がお仕事小説として目新しく、主人公の鑑定相手が次々に首を吊ってという展開もスリリングだが、後半は既存のサイコサスペンスの枠組みに収まってしまう。作者の仕掛けも読めてしまうし、さらなるヒネリ技を乞う。舞台となる函館の風物ももっと活かせたらよかった。
東一眞『クロウ・ブレイン』は大手新聞社の社会部記者が、カラスが人を襲った事件を単独追い始めるが、彼自身、新宿御苑で襲われる羽目に。さらに取材先の「美しすぎる」大学教授の研究室では、カラスがパソコンのキーボードをつついて彼への脅迫文を作成するのを目の当たりにする。
うだつの上がらぬ主人公が汚名挽回を図って奔走するが、いささか空回り気味なのが痛い。カラスの生態を始め科学的な蘊蓄は読みやすくタメにもなるが、A・ヒッチコック監督の名作『鳥』を超える大スケールのパニック劇演出を期待した身としては、ちょっと迫力不足に終わった感あり。
柊悠羅『悪魔の取り分』は厚生労働省医薬食品局安全対策課の佐倉が、新たに開発、販売された抗インフルエンザウィルス薬の危険性について単独調査を始める。やがて佐倉の友人を含む三人の男がその薬の使用後にインフルエンザ脳症で死んでいる事実をつかむ。佐倉は謹慎中の警視庁捜査一課刑事の協力を仰ぎ、三人の死をめぐる謎の解明に挑む。
テーマ的には医学もの、ミステリー的にはバディ捜査もの。ウィズコロナの時代に見合った作品で、よくいえばこなれている、辛めでいえば既視感ありありの仕様で、独自さに欠ける。まあ二〇歳という作者の年齢を考えれば敢闘賞くらい差し上げたいところだが、今後の伸びしろを考えればここでは辛い意見を通しておいたほうがよさそうだ。
今年は『砂中遺物』と『甘美なる作戦』の戦いになるのかなと思ったところで、出てきました、大本命。最後の新川帆立『三つ前の彼』は、大手製薬会社の御曹司の死の謎にまつわる本格ミステリーだが、個人的には独自の女ハードボイルドものとして推したい。
青山百合絵はやり手の弁護士だが金の亡者。安物の指輪を送ろうとした彼氏をふった腹いせに元カレに久しぶりに連絡しようとするが、元カレは謎の遺言を残し亡くなっていた。婚活テーマのバカミス調出だしから謎の遺言をめぐる相続ものへと舵取りが変わると、軽井沢を舞台にした英国調の避暑地ミステリーが繰り広げられていく。何より金の亡者だが一抹の情けもないではないヒロインのキャラが光るが、遺言の真相には結構驚かされたし、人間関係もよく練り込まれていると思った。
ということで、今年は上位三作は皆授賞の価値ありというスタンスで選考会に臨んだのだが、何と他のお二方の採点も同様で、大賞作品も自ずと決定。これまで採点が割れていたのが嘘のよう。
瀧井朝世
発想力、文章力、キャラクター造形力どれも充分 ぶっちぎりで面白い
この第19回から最終選考委員をつとめることになりました。そのため前回までの最終候補作との比較はできませんが、今回どの作品も大変面白く拝読しました。
『砂中遺物』は、パラレルワールドの設定が細やかに構築されていて、その世界観にまず引き込まれました。限りなく現代の日本を思わせる風景のなかに、隣国に併合された後である特徴を紛れ込ませ、現実とは微妙に異なる空間を立ち上げていく描写が巧み。視点の切り替えのテンポ、アクションシーンも上手く、最後まで飽きさせずに読ませる。充分読者に届けられる作品として、文庫グランプリに推しました。ただ、主人公の雑賀が守ろうとする由佳がなぜ拉致グループに参加していたのかといった彼女の経歴や、逃避行のなかで雑賀への信頼感がどのように変化していくのかについて、もう少しエピソードを加筆したほうが人間ドラマ部分の魅力が高まるはず。
『甘美なる作戦』はヤクザの見習いコンビの話、自動車部品店が窮地に追い込まれる親子の話、途中で挿入されるまた異なる人たちのエピソードが後半に絡み合い、意外な方向に事態が収拾されていく様子に驚きと爽快感を味わいました。沢山の人物、要素が盛り込まれますが中だるみもなくエンタメ作品として楽しめる。誘拐事件の身代金の受け取り方法なども面白かった。ただ、当選した宝くじを換金しに行けない理由、殺人事件の犯人が犯行に至るまでの経緯には無理があり、再考の必要があるのでは。また、脇役でも印象的な登場人物については、事件の後どうなったか後日譚を知りたかった。そのあたりをクリアすれば問題ないと判断し、文庫グランプリに推しました。
『虐待鑑定 ~秘密基地の亡霊~』も興味を引く題材を扱っていて引き込まれましたが、ひっかかるところがいくつかありました。イマジナリーフレンドの登場の仕方があまりに都合よすぎて不自然。これは真相に気づく人は気づくのでは。説明が足りないと感じたのは犯人像。これまでの人生や犯行動機などは一応言及されているのですが、駆け足で説明されるためあっけなく、都合よく辻褄を合わせている感がぬぐえず、疑問点もいくつか残りました。犯人像にもっとリアリティをもたせる必要があると感じます。
計画的な犯行の場合、犯人は自分の目的を達成するため、と同時に自分の犯行だと気づかれないようにするため、それなりに周到に智恵をめぐらして準備するものではないでしょうか。だからこそ、それが突き崩される瞬間に読者は快感を得るというもの。ここまで長年罪を重ねてきた人間の行動にそれなりに計画性と説得力がないと、真相が分かった時の驚きと爽快感が半減してしまいます。
『悪魔の取り分』も官僚や警察組織、医薬業界のことを丁寧に掘り下げて筆力を感じさせますが、犯人の目的と行動がひっかかりました。犯行は非常に手が込んでいますが、そのわりには、なにがなんでも目的を達成するために智恵を絞って綿密に立てた計画という印象を受けません。むしろ、これでは目的達成の可能性は低いのでは。さまざまな立場の人間をみな個性的に描き、話を大きく広げいく筆運びが上手なだけに、最後に消化不良感が残りました。また、女性観や女性の扱い方が古くさい箇所がいくつかあり、個人的には気になりました。
『クロウ・ブレイン』については、ウイルスはやはり昨今気になるモチーフですし、興味深く読みました。主人公があちこち出向いて情報を集め、危険な目にあって……と、探偵の役割をちゃんと果てしてくれていてミステリとして安定感がある。ただこの人、行動が短絡的で失敗ばかりしていませんか。もうちょっと、自力で何かを成し遂げるなりどこかに人間的な魅力を感じさせてくれないと、読んでいて苛立ちが募ってしまいます(あんなにSNSで拡散されてしまった問題が回収されない点も、彼の人生これから大丈夫だろうか、と気になります)。
『三つ前の彼』はぶっちぎりで面白かったです。奇妙な遺言状の内容はもちろん、とにかく主人公の人物造形に魅了されました。異様なほど業突く張りな女性ですが、こだわる金額のケタが突き抜けててもはや笑える。でも、心のどこかで世の中お金だけじゃないと感じている節もあるようで、そこも好感を持ちます。次々といろんな女性が登場しますが、主人公が相手に敵意を向けるのでなく、冷静に相手を見て素直に好感を持つ時は持つなど、古いエンタメで描かれがちな「女同士は敵対するもの」というステレオタイプを脱却している点も魅力的でした。また、細かなところまで疑問点を回収してくれているので、モヤモヤが残らず気持ちよく結末にたどり着けました。気になる点もありますがみな修正可能な範囲内。発想力、文章力、キャラクター造形力どれも充分で、今後書き続けていける人だと確信し、大賞に推した次第です。