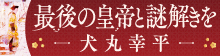第18回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
紙と模型、ダブルで楽しめる即戦力作品が、危なげなく大賞決定
前回、前々回と、最終選考会は、(僕にとって)“開けてビックリ玉手箱”的な、予想外の結果が続いたわけですが、今回はその反対に、おおむね予想通り。二次選考会の評価が大きく覆されることもなく、大賞はあっさり確定した。
一次投票の段階からポイントを集め、危なげなく受賞に漕ぎつけた歌明田敏『模型の家、紙の城』は、紙鑑定士(その実態は、紙の販売代理業を個人で営む紙商)の語り手が、ゴミ屋敷に住む“伝説のモデラー”(プロの模型製作者)とタッグを組んで事件の謎を解くサスペンス。名探偵役が特殊な業界の知識を駆使するタイプのミステリは小説でもドラマでもぜんぜん珍しくないが、紙にまつわる蘊蓄と模型にまつわる蘊蓄がダブルで披露されるのが本編の特徴。紙屋が依頼を受け、模型屋が推理する。こういうコンビは意外と珍しいのではないか。それもそのはず、タイトルひとつとっても、焦点が絞れないという欠点が明らかですが、読んでいるあいだはダブルで面白い。ストーリー展開にご都合主義が目立つものの、語り口とキャラクターは即戦力。不具合をうまく解消して世に出ることを(ついでにシリーズ化されることを)望みたい。
それに次ぐ評価で優秀賞を獲得したのが泡沫栗子『君が幽霊になった時間』。高校の文化祭のお化け屋敷が事件の舞台になるという学園ミステリで、話が動きはじめるのに時間がかかるのが難点だが(あちこちに手がかりをちりばめ、伏線を張りまくってから回収するタイプの本格ミステリなので、そうなってしまうのもある程度しかたない面はある)、ひたすらロジックで詰めていく解決編の切れ味は鮮やか。その直前には、探偵役からの“読者への挑戦”も挿入されて、いやがうえにも期待と気分が盛り上がる。“お化け屋敷の殺人”という、(僕の知るかぎり)ありそうでなかった設定もすばらしい。さしずめ、ライバルは青崎有吾か。といっても、(デビュー作時点で考えても)追いつくにはまだまだ距離がありそうなので、これからがんばってください。
大森がAをつけたものの、惜しくも三番手となり、きわどいところで選に洩れたのが、藍沢すな『はぐれた金魚は帰れない』。冤罪で死刑になった父親の汚名を晴らし、警察と司法と教育機関に復讐するため、衆人環視のなか、犯人が超自然的な力による大量殺人を実行するという導入は抜群。その目的が、警察と裁判所に超自然現象の実在を認めさせることだというのもユニークだし、(常人の目には見えない)宙を泳ぐ巨大な金魚が凶器になるというぶっ飛んだセンスもいい。この怪作に敬意を表して、金魚柄のアロハで選考会に臨んだが、受賞作とするにはさまざまな問題点があるのも事実。そもそもこんな超自然現象の実在が公に認められたら裁判とかやってる場合じゃなく、現代科学が根底からひっくりかえってしまう――と考えるのはSF脳かもしれないが、小説の欠陥がテーマと密接に結びついているだけに、強くは推し切れなかった。
リーダビリティだけとりだすと受賞作にも負けていなかったのが、走水剛の相撲ミステリー『わたしの殺した力士』。顔がそっくりの力士同士の入れ替わりネタだが、実際に一卵性双生児の現役力士がいることを考えると、さすがに無理筋ではないか。その無理を押し通すには、肝心の事件がちょっと地味すぎた。
同じく入れ替わりものを実在の人物でやってのけたのが野地嘉文『贋者江戸川乱歩』。昭和の探偵小説マニアなら大いに楽しめそうだが、どう見てもこの賞のカラーではない。甲賀三郎、横溝正史、木々高太郎など往年の探偵小説作家を語り手に起用しただけでなく、積極的に事件に関わらせたり、存命の実在人物を登場させたりする手法も(二次選考会に続いて)論議の的となった。このまま本にするのはいろいろさしさわりがありそうです。
やはり実在の(歴史上の)人物が出てくるのが、平島摂子『フィオレンティーノ』。こちらは天正の少年遣欧使節を主役にした歴史ミステリーで、筆力はじゅうぶんに評価されたものの、謎とその解決の弱さは否めない。どうせガリレオを出すなら、もっと名探偵らしく活躍させればよかったのに。
雨地草太郎『闇だまり』は、町工場、温泉街、スナック、地回りのヤクザ……と昭和テイストあふれる背景が特徴。文章やストーリーテリングはしっかりしているし、終盤のどんでん返しも鮮やかだが、どういう読者層に訴えるか(金を払って読んでくれる読者がどこにいるか)と考えると心もとない。新人賞の選考では実力が評価されるが、商業出版ということを考えると、プラスアルファのアピール力が必要になってくる。どういう人に買ってもらうのかを意識してほしい。
選評は以上。なお、これまで18回にわたって最終選考委員をつとめてきた吉野仁さんが、今回で退任となる。ミステリー要素に対する鋭いツッコミと分析が聞けなくなるのは残念ですが、長いあいだご苦労さまでした。
香山ニ三郎
今回のイチオシは、未知のキャラクターと薀蓄で読ませるハードボイルドもの
今年の最終候補作のラインナップを見て思ったのは、ベテランの応募者やプロ作家が多いということ。接戦になりそうな予感を抱きつつ、例によって読んだ順から紹介していくと、まず野地嘉文『贋者江戸川乱歩』は戦中戦後の日本ミステリー文壇を背景に、乱歩とそっくりさんとの入れ替わり劇の顛末を描いた伝奇系。ミステリー文壇の権力闘争史は業界人のひとりとして誠に面白く読ませていただいたが、一般受けするかわからないし、モデル小説であるがゆえの権利問題もクリア出来るか疑問。個人的には贔屓するとしても、要相談だろう。
藍沢すな『はぐれた金魚は帰れない』は大阪の小学校が襲撃され三五人の犠牲者が出る。犯人の二〇歳の女は武器を使わず思念物体である金魚を使ったのだった。目に見えぬ犯行は法で罰することが出来るか、というわけで、X-MENばりの超能力者の復讐劇にリーガルサスペンスを織り込んだ問題作。アイデアは面白く、語りも軽快だが、現実に大量殺人が頻発していることを考えると、素直に楽しめず。金魚の問題も事件が事件だけに、実際にはお上は何らかの形で懲罰を図ることになろうし、リアリティに問題はないのか、判断に迷うところ。これまた要相談か。
走水剛『わたしの殺した力士』はベテランの相撲記者が注目の新小結に入れ替わり疑惑を抱くが、夫殺しで服役していた主人公のかつての同僚が出所後この新小結相手に暴力沙汰を起こす。野地作品と同様、入れ替わりものだが、ホントにこんなこと起こりうるのかよと半信半疑。作者はプロ作家で相撲ものもすでに何作か出しているし、これまでとは違うジャンルにチャレンジしてもらいたかったという思いもある。完成度は高いが、授賞の当否についてはやはり要相談だ。
雨地草太郎『闇だまり』は父のDVが原因で親戚の元で育った中卒の工員が主人公。彼女は近隣の温泉町のスナックで働く女友達と同居していたが、そこに行方不明だったDV父が現れ、事件が……。前半はよくあるDVもののパターンで男勝りのヒロインの造形も取り立てて魅力的というわけではない。何故残した、という言葉が喉まで出かかったが、後半の展開に仰天。それまでの善玉、被害者が見事に逆転するのだ。こういうヒネリ方は凄い久しぶりだが、果たしてこれだけでも贔屓する価値はあるのか。要相談。
どこまで続くか要相談作品。このまま自分の推しが出ないまま終わるかと思っていたら、次の平島摂子『フィオレンティーノ』に手応えあり。一六世紀後半、日本の少年遺欧使節団がイタリアに到着。四人の少年たちは歓迎を受けるが、トスカ-ナを治めるメディチ家の権力闘争劇に巻き込まれていく。表題は権力の象徴たる巨大ダイヤモンドのことで、その争奪戦が繰り広げられる。こなれた筆致で読ませる歴史ミステリーだ。少年使節を始め、主要キャラクターの造形もしっかりしている。これといった仕掛けに欠けるし、ガリレオ・ガリレイが今ひとつ役不足なのももったいないが、優秀作候補として充分推せよう。
続く歌明田敏『模型の家、紙の城』にはさらなる手応えが。こちらの主人公は新宿に事務所を構える紙鑑定士。探偵事務所と間違えてやってきた女性の依頼を暇に任せて受けるが、その手がかりは戦車のジオラマ。模型に無知の素人探偵は伝を頼って伝説のモデラーと知り合いになり、彼の助言で見事に依頼を果たす。それがきっかけでさらなる依頼が飛び込むが……。紙鑑定士に模型のモデラーという未知のキャラクターにまず惹かれた。彼らの繰り出す蘊蓄も巧みに事件に活かされ、独自の探偵物語の生成に成功している。ある模型から重大犯罪が浮かび上がっていく後半がやや駆け足になってしまうものの、加筆訂正で何とかなろう、というわけで、今回のイチオシはハードボイルドもの。
最後の泡沫栗子『君が幽霊になった時間』は学園ものだ。架空の高校・羊毛高校で文化祭開幕。主人公閑寺尚の属する二年二組はお化け屋敷を催すが、その最中、彼の片想いの相手、旭川明日葉が絞殺される。傷心の閑寺だったが、これを機会に一目置かれる存在になりたいという地味なクラスメイト甲森璃瑠子にそそのかされ捜査に乗り出す。そのロジカルな推理が目玉で、被害者が死んだ時間を突き詰めていくくだりはスリリングのひと言だ。ただし教員や警官の視点を欠くなどの偏りがあり、閑寺たち生徒の造形にももうひと彫り欲しかった。大賞作には推せないけど、優秀作としてはどうか、要相談ーーって、また元に戻っちゃった。
かくして臨んだ選考会では『はぐれた金魚』と『模型の家、紙の城』、『君が幽霊に』に初めから票が集まり、大賞は順当に決定。筆者の要相談作品は、多くがあっさり落ちてしまった。力になれず、すみません。『フィオレンティーノ』も全員B評価、作者の筆力は認めるものの、物語内容においては決め手を欠くということで強く推す声は出なかった。平島さん、これに懲りず、捲土重来を図ってください。
吉野仁
満場一致の高評価作品が、順当に大賞・優秀賞を受賞
第十八回「このミステリーがすごい!」大賞の選考会は、大きな紛糾もなく、高評価の作品が順当に決定していった。
大賞となった『模型の家、紙の城』は、ジオラマを手がかりにして事件の謎に迫るという斬新なミステリーだ。語り手である紙の鑑定士・渡部が行動派探偵で、プロの模型製作人・土生井が安楽椅子探偵をつとめるという設定もユニーク。模型や紙について繰り出されるマニアックな蘊蓄が面白いだけでなく、それらの知識や情報が、しっかり事件や捜査と絡んでいるため、飽きることなく最後まで読ませる。ただし、目的の場所を発見する過程で、根拠も示さずにあっさりと死体にたどりついてしまう展開などが気になった。もっとも、こうした部分は、受賞作として刊行される際に修正されることだろう。筆力は申し分ない。デビュー後の活躍もたのしみだ。
優秀賞となった『君が幽霊になった時間』は、文化祭の「お化け屋敷」で起こった殺人の謎をめぐる学園もの本格探偵小説で、解決の決め手となるのは、被害者の死んだ時刻を絞り出すこと。欠点を言えば、犯人の印象があまりに薄く、殺人の動機も弱い。だが、前半の思わぬ部分にトリックが仕込まれているなど、解決にいたるプロセスで驚かされる部分がいくつもあり、ミステリの面白さは十分。ページをめくらせるための効果的な演出が前半からしっかりとほどこされているなら文句なしだ。
そのほか、『はぐれた金魚は帰れない』は、宙を泳ぐ十二匹の巨大な金魚による大量殺人という前代未聞の奇怪な事件をめぐるサスペンス。大胆奇抜なアイデアで、ラストも鮮烈だ。ただし、あまりに「ご都合主義」で細部が雑すぎる。主役をつとめる刑事と弁護士がそろって(一般人は見えないのに)「殺人金魚が見える」体質という点は、その最たるものだ。たとえば臨死体験をした人物だけが見える設定ならどうか。刑事は以前、死にかけたことがあり、弁護士は最初から金魚の存在を非現実だと信じなかったが、事故で九死に一生を得てから、見える体質に変り、意見を一転した……、という風に小説内リアリティを高める工夫やエピソードが描き込まれていたならば、大賞レベルだろう。これまで作者の応募作を何作も読んでいるが、ことごとく「ご都合主義」な点が大きなマイナスだった。これをおろそかにせず、つめなければ先はない。
『闇だまり』は、温泉街のある地方都市を舞台にした作品。子供時代に父親のDVに苦しんでいたヒロインが、同居する親友からストーカー被害の相談を受けた。やがて親友をつけまわしていたのは、行方をくらませていた自分の父親で、いまは地元暴力団の組員になっていたと判明した。……というのが導入部。最後にサプライズはあるものの、全体にあまりにも地味で薄く弱い。文章力、人物造形力、サスペンス構成など、もう一段といわず二段三段と濃度を増したうえで、強烈な印象が残る要素をなにかしら加えてほしい。
『贋者江戸川乱歩』は、題名どおり、乱歩に瓜二つの男が登場する。甲賀三郎、横溝正史、木々高太郎といった乱歩と同時代、「新青年」誌で活躍した日本探偵小説創生期の作家たちが語り手となる小説で、ほかにも多くの実在作家が登場する。いちばんの不満は、探偵小説史をもとに虚実をとりまぜて書かれた実録小説が主で、ほんのおまけ程度にそっくりさんの入れ替わりネタが使われているというところ。これでは高い評価を与えられない。
『わたしの殺した力士』も同様である。相撲雑誌の編集部員が主人公で、とある力士がそっくりさんに入れ替わっているのではないかと疑念を抱く。これまた角界のマニアックな情報など相撲に関する蘊蓄は面白く、すでにプロ作家として何作も作品を発表している書き手だけに、こなれた筆致ですいすいと読ませる。だが、ミステリーとしての興奮は乏しい。あくまで相撲ネタで支えられている作品なのだ。
『フィオレンティーノ』は、かの「天正少年遣欧使節」のひとり、中浦ジュリアンを主人公にした異色歴史ものだ。一行はトスカーナ大公フランチェスコ・メディチのもてなしをうける。フィオレンティーノとは国宝のダイヤモンドで、それが偽物と入れ替えられたのではないかと疑いがかかった。こちらは、登場人物が魅力的に描かれているほか、ガリレオ・ガリレイが登場するなど、ドラマの描き方が上手く愉しく読んでいった。歴史小説としての面白さはなかなかのもの。だが、やはりミステリーとしては弱い。せめて謎にまつわるサスペンスを高める構成上の工夫がほしかった。
最後になるが、このたび十八年担当してきた選考委員を退くことになった。今回、入れ替わりトリックがあちこちで使われていたが、こちらもそろそろ入れ替わる時期ではないか。賞は生き物、時代は変わる。新鮮な風を入れよう。ぜひ次の体制に期待してほしい。そして本賞受賞者がいつまでも作品を書き続け、華々しく活躍することを願ってやまない。