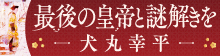第11回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
求めるものは「独創性」や「インパクト」
今回の候補作は(二重投稿で残念ながら失格となった1編を含めて)非常にレベルが高く、どの作品も(多少の手直しを施せば)すぐに出版できそうな水準。Cをつけた作品はひとつもなく、おかげで仕事を忘れて楽しく読むことができたわけですが、だったらどの作品でも躊躇なく大賞に推せるかというと、それはまた別の問題。既成作家や先行作品を連想させるものが多く、新人賞受賞作に期待する独創性やインパクトに優れた作品はあんまり見当たらない。
その中で、圧倒的な牽引力を発揮したのが安生正のサスペンス大作『下弦の刻印』。よくあるパンデミックものかと思って読み進めると、思わず茫然とする真相が明らかになる。ま、まさかそんなことが!? と腰が抜けそうになる大胆な発想は大いに評価したい。
この未曾有の事態に立ち向かう廻田三佐の切り札が、天才的疫学者の富樫博士。『日本沈没』の田所博士に輪をかけたようなこの強烈なマッド・サイエンティストがさらに激しく暴走し、突拍子もない物語をぐいぐいひっぱっていく。
文章、キャラクター、設定、すべてにB級テイストが色濃く漂うものの、B級っぷりもここまで徹底すれば立派。じっさいこれは、高野和明『ジェノサイド』の向こうを張る壮大なスケールのサスペンス……と言えなくもない。
大賞に推すのはこの1本と決めて選考会に臨み、香山、茶木両委員の賛成票を得て、めでたく第11回『このミステリーがすごい!』大賞の大賞受賞作に選ぶことができた。いやまあとんでもない話なので、ぜひこれを読んであっけにとられていただきたい。お楽しみに。
これ以外の5編については、正直、どれが優秀賞に選ばれても不思議のない接戦だった。最終的に明暗を分けたのは、やはり目新しさだろうか。
新藤卓広『或る秘密結社の話』は、大賞受賞作とは対照的に、バラバラのピースを非常にうまく組み上げた寄木細工のような作品。ぱっと見、いかにも伊坂幸太郎フォロワーに見えてしまうところが弱点と言えば弱点だが、話が落ち着く先をなかなか見せない書きっぷりと、パズルのピースのきれいなハマりっぷりは鮮やか。物語の最終的な着地点と、タネ明かしの処理に多少の疑問がないではないが、修正の効く範囲だろう。
深津十一『石の来歴』は、高校生の主人公と石コレクターの富豪との関係を軸に、伝奇ホラー的な要素も交えた幻想ミステリ。次々に登場する奇妙な石はそれぞれ魅力的だが、肝心要の“童石”の謎にもうひとつ説得力がなかったのが残念。とはいえ、独特の味わいを持っているのは事実なので、『或る秘密結社の話』ともども、優秀賞授賞に賛成した。
選に漏れた作品の中で、いちばん面白かったのは柊サナカ『婚活島戦記』。設定を見ればわかるとおり、婚活版『バトル・ロワイアル』。莫大な財産を持つ青年社長の妻の座をめぐり、花嫁候補たちが(命までは賭けずに)離れ小島で壮絶なバトルをくり広げる。バトロワ二番煎じもここまで徹底すれば立派だが、この小説の最大の美点は、ヒロインの造形にある。『エアマスター』の相川摩季が成長したみたいな、ストリートファイター上がりの主人公、二毛作甘柿が(独特すぎるそのネーミングセンスも含めて)すばらしい。彼女を広く紹介するためだけにも、隠し玉枠での刊行を強くリクエストしたい(その場合、カバーはぜひ柴田ヨクサルでお願いします。ムリか)。
それに次いで推したのが、堂島巡『梓弓』。沼田まほかる『九月が永遠につづけば』ののほほんバージョンというか、交通事故で死んだ娘の友だちの行方を追う母親の話。彼女の消息をたどるうちに行き着いたデリヘルでいつの間にか事務のパートをやることになったりするオフビートな展開が楽しい。亡き娘を主人公にした小説を母親が書いていて、みずからの願望や思い込みがそのまま投影された文章が作中に引用される趣向もうまく効いている。ラストには意外なサプライズも用意され、好感の持てる小説だが、残念ながら強力なセールスポイントに乏しく、地味な印象は否めない。
最後に残った藍沢砂糖『ポイズンガール』は、湊かなえ系のイヤミス。女子高の科学部に属する少女たちがたがいに毒を仕掛け合うゲーム「ポイズンガール」にハマってゆく。ゲームが本物の殺し合いに発展する過程に説得力がないのが弱点。正義のヒーローになりたくて警察官を志したのに人を殺して逃亡する羽目になった男の話がサブプロットだが、本筋とうまくからんでいるとは言いがたい。むしろ、ポイズンガールの話だけに絞った方がよかったのでは。筆力はじゅうぶんある人なので、今後に期待したい。