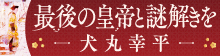第2回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
今回は波乱含みの選考会だった
1次、2次の結果から事前にある程度予想していた通り、今回の最終選考は大森ひとりが“抵抗勢力”に回ることになった。 細かいことを考えずに読めば、『夜の河にすべてを流せ』はたしかに面白い。流行のネタをこれでもかとばかり詰め込み、意外性満点のプロットに落とし込むテクニックは一流だし、売れる素材だとも思う。
しかし、クラッキング、コンピュータ・ウイルス、オンライントレーディング、金融工学、バイオサイエンスなど、各分野の上澄み(あるいはアンダーグラウンドな部分)をすくってきているわりに、ごく初歩的なレベルでの間違いが多く、読んでいるあいだに何度となく脱力させられた。前転もできないのに見よう見まねでウルトラD難度の技に挑戦する芸人みたいなもので、専門的な描写がまるで板についていない。設計は斬新ですばらしいのに施工が手抜きというか、仕上げに充分な時間をかけていない印象。
加えて文章にも冒頭から粗が目立ち、「風に揺れるポプラ」だの「目にも鮮やかな緑の芝生」だの「涼やかな瞳」だの、紋切り型の形容の連発にうんざりしてくる。「面白ければいいじゃないか」と目をつぶるにはマイナス点が大きすぎるというのが結論で、大賞授賞には断固反対――のつもりでいたのだが、いかんせん多勢に無勢。まあ、冷静に考えてみれば、描写のディテールにしろ、文章にしろ、修正が不可能な欠陥ではないわけで、全面的な改稿を前提として『夜の河~』に大賞を贈るという決着に、不本意ながら賛同することにした。「減点法では落とさない」というのがこの賞の基本方針であることを考えれば、それも致し方ないところだろう。
著者の柳原氏に対しては、これからの手直しですべての欠陥をみごとに修復し、受賞作が出版された暁には、読者諸氏が「いったい大森はどこに文句をつけていたのか?」といぶかしむような傑作に仕上げてくださることを強く期待したい。
一方、優秀賞に落ち着いた『ビッグボーナス』は、個人的にいちばん気に入っていた作品。あからさまに怪しいパチスロ攻略情報を数十万円で売りつける立て板に水のセールストークと、何度もだまされてもついカネを出してしまうパチスロ中毒者たちのバカっぷりは抱腹絶倒。よく知らない業界の話だが、小説のあちこちで圧倒的なリアリティを感じさせてくれる。読者賞をぶっちぎりで獲得した事実が示すように、みごとに計算された前半のC調文体も抜群に魅力的で、小悪党小説の傑作誕生かと期待を抱かせた。ところが後半、主人公が破滅に向かって突っ走りはじめると、とたんに馳星周ノワールの劣化コピーに堕してしまう。ピストル片手にドンパチやらなきゃいけない話でもないのに、既成の小説パターンをなぞるかたちに収束させているのが返す返すも残念。どうしてもこれを大賞に――とまでは押し切れず、最後の直線で『夜の河~』を差すには至らなかった。しかし、いまどきこの慎ましやかな長さと、娯楽に徹したVシネマ感覚は貴重。即戦力の人材として、これからの活躍が大いに期待できそうだ。本が出るのをどうかお楽しみに。
選に洩れた三作のうちで大森が好感を抱いたのは『葡萄酒の赤は血のかほり』。『はいからさんが通る』と『南京路に花吹雪』をミックスしたような明治国際謀略活劇で、むしろ「快男児・岩嵜眞一郎」的なタイトルがふさわしいのではないか。惜しむらくは、脇役陣の魅力にひきくらべ、本線のプロットがあまり面白くない。歴史に取材するより、明治のキャラクター小説に徹したほうがよかったのでは。
『愛は銃弾』は、昨年の最終候補に残った『熱砂に死す』とまったく違う方向に挑戦した点を評価したい。引っ込み思案な少年が漫画を描いて年上の美少女にアプローチする過程は、ノスタルジックな少年小説としてそれなりに読ませる。とはいえ、(人工的な本格ミステリならいざ知らず)人間ドラマを軸とした警察ミステリにこの設定はなじまない。クライマックスの盛り上がりも、作者だけが酔いしれているように見えてしまう。
『昭和に滅びし神話』は、やたらとくりかえしが多い文章が印象を悪くしている。正直いって、読み進むのにほねが折れた。手垢のつきまくった題材をテーブルに載せるのなら、料理法にもっと工夫が必要だろう。
選評は以上。大賞受賞作に関して最終選考委員全員の意見がほぼ一致した前回に比べると、今回はやや波乱含みの展開(といっても波風を立てたのは大森だけですが)になったものの、大賞・優秀賞の受賞作は、ある意味で前回以上に『このミス』大賞らしいと言えるかもしれない。
香山ニ三郎
あの手この手で先を読ませぬストーリー展開
今年こそ壮絶なバトルを繰り広げてやる! そう心に決めて選考に望んだものの、いざフタを開けてみたら早々と2作が決まってしまった。その間わずか数分。いや、その後、いろいろ議論が闘わせられはしたのだが、自分の結論とこうもあっさり合致してしまうと、高見盛張りに燃え上がらせた闘争心をどう処理してよいかわからず、往生させられた次第。
それはともかく、選評だ。
落ちた3作からいくと、まず横山仁『昭和に滅びし神話』は1930年代の満洲が舞台。関東軍参謀石原莞爾の手先となって工作活動に従事する中国人暗殺者を軸にした謀略活劇で、主人公もそれなりにキャラクターが立っているし、お話のほうも川島芳子や韓国人酌婦との悲恋をまじえそれなりに手堅く仕上がっている。だが小生がこの賞に望むのは「それなりに」「手堅い」作品ではない。
この手の中国、満洲系活劇はすでに生島治郎や伴野朗を始め、多くの作家が多彩な作風を開拓してきた。第2次大戦があったことすら知らない若者が現われている昨今、ストレートな歴史悲劇に挑むことに意味がないわけではないが、キャラでもテーマでもストーリーでも、一読仰天の創意工夫が感じられなければイチオシには出来ない。粗削りでもいい、「こんな満洲もの、読んだことないだろ」というのを読ませて欲しかった。
満洲ものがもう一作。浜田浩臣『葡萄酒の赤は血のかほり』の時代背景は横山作品からさらに時代を数十年遡った1905年。日露戦争真っただ中の満洲の戦場で諜報員が殺され、それをきっかけに浮かび上がる国際謀略に財閥出の新聞記者とその恋人が挑む。擬古典的な語りや暗号解読等パズラー趣向が盛り込まれている辺り、創意工夫という点では好印象なのだが、こちらはこちらで、横山作品とは異なるデジャヴューが。マンガ的といおうか、どんな危機に直面しても主役は無事、謎も難なく解かれて大団円という通俗的なご都合主義に染まっており、それはそれで心地よくないことはないのだが、面白さが上っ滑りして軽量級に止まってしまったのは残念。
なおこの作品については、他の新人賞にも応募されていたとの指摘があった。二重応募ではないにせよ、掛け持ちの応募は著しく印象が悪くなる。今後は避けられたい。
もう一作、島村ジョージ『愛は銃弾』はあるホームレスの死をきっかけに中年刑事の少年時代の初恋悲劇が回想されていく。1970年代前半の風俗を取り込んだその悲劇からノワール風犯罪活劇へと一転する展開は悪くないが、犯人当てという点では見え見えで、思い入れたっぷりの筆致もいささかナルシスティックに走りがちな感あり。いいかえれば、読者を娯(たの)しませるというより、自分が娯しんでしまっているような。
前回最終候補に残った『熱砂に死す』の小生の評は「演出も人物造型もいささか類型的で古臭い」だったが、今回それが改善されたとはいい難い。今後は自分の身近な世界ではなく、外の世界に題材を求め、持ち前の筆力を活かしていっていただきたいと思う。
さて、受賞作だ。
ハセノバクシンオー『ビッグボーナス』は筆名といい「明石家さんまが好きなシチュエーション--」という出だしといい、「なんじゃこりゃ」感が高かったが、読み進めていくうちに独自の軽ノワールタッチに乗せられた。ただ400字で400枚強の軽量、物語にも今ひとつ膨らみがないし、前半と後半のタッチも変わってしまう。パチスロの描写も門外漢にはわかりにくい等、粗を挙げ出したらキリがないかも。にも関わらず高評価を得たのは、パチスロの裏世界を活写したコンゲーム演出にも、SM趣向の恋愛演出にも、この人ならではのタッチが溢れていたからだ。個人的にはマイナス面も多々あり、あまり強くは推せなかったが、今後大いに期待出来そうだし、他の委員の推す声に異議を唱えるつもりも毛頭なかった。受賞者は独自の乗りを活かしてバクシンしてください。
大賞の柳原慧『夜の河にすべてを流せ』は誘拐ものだが、「誰も殺さない、誰も損をしない、せしめる金は五億円」という著者自身のキャッチフレーズ通り、奇抜なアイデアが凝らされたノンストップ犯罪活劇に仕上がっていた。筋の面白さは読んでのお楽しみとして、小生がここで強調しておきたいのは、脇役のキャラ造型。敵味方いずれも個性豊かな人物が登場するが、特に子供と爺さんの健気なセリフに涙ちょちょぎれました。
株取引やインターネット関連の取り扱いに難ありとか、紋切り型の表現が目につく等、問題点も指摘されたが、あの手この手で先を読ませぬストーリーテリングの妙にかけては第1回の大賞金賞受賞作、浅倉卓弥『四日間の奇蹟』よりも上、ということで、前回とはまたタイプの異なる大賞作品が出せたことは誠に喜ばしい。
太鼓判のこの面白さ、ひとりでも多くの読者に味わっていただきたい。
茶木則雄
傑出した原石
昨年の選評にも書いたが、この賞の最も大きな特徴は、才能第一主義にある。たとえ欠点はあっても、大いなる原石の輝きを秘めたものであれば充分、受賞の対象になり得る、という点だ。むろん、原石でありさえすれば何でもいいという訳ではない。ちょっとした原石なら、どの新人賞でも1次通過レベルにごろごろ転がっている。『このミステリーがすごい!』大賞が求めるのは、少なくとも書き直しを前提で受賞作と認めるのは、傑出した原石である。これまで見たこともないような形体の新奇な金剛石であり、磨けば眩いばかりの煌めきを放つと思われる大粒のダイヤだ。
柳原慧氏の『夜の河にすべてを流せ』は、まさにそうした、傑出した原石であった。
一読のかぎりにおいては、その斬新な発想と陰影に富んだ登場人物の巧みなキャラクタライゼイション、何よりも先の展開をまったく読ませない卓抜したストーリーテリングの妙もあって、欠点はさほど目立たない。豪腕とも言える圧倒的リーダビリティで一気呵成に読まされてしまうからだ。多少引っかかりを覚える箇所があったとしても、そこで立ち止まる余裕が、正直こちらになかった。物語がどう展開していくのか、気になって気になって、ページを繰る手を止められなかったのである。しかし再読すると、最終選考会で指摘されたいくつかの欠点を、嫌でも感じざるを得ない。まず気になったのは、紋切り型の表現が思った以上に少なくない点だ。将来の活躍を期待させる総体的な筆力は確かにある。キャラクターを際立たせる人物造形などはその最たるものだろう。が、ときに描写が、安易な道に流れていることは否めない。しかしこれは、書き手の意識の問題だろう。常套句を極力、排除するよう胸に刻めば、プロで充分やっていける文章力だと思う。また女性刑事の全体像にいまひとつ厚みが足らない点も、気になると言えば気になった。エンターテインメントの常道からすれば、犯人を追い詰める捜査側の主役である彼女に、もっと多くの筆をさくべきだろう。だが、常道を外れているからこそ先が予測できない、という部分もある。このあたりのバランスは微妙で、正直いまでも判断に迷うところだ。主役不在の群像劇という誘拐ミステリーではかつてない斬新性を是とするか否とするか、最終的な判断は読者に委ねたい。
もっとも、これらふたつは些細な疵に過ぎない。この作品の最大の欠点は、類いまれな器の素晴らしさに比べて、あくまでも比較の問題ではあるが、料理そのものの深みや玄妙さに欠けているところだ。器――すなわち着想やプロットは、抜群にいい。はっきり言って、国宝級である。一級品の素材を見抜く目も、間違いなくある。しかし肝心の料理はと言えば、明らかに器負けしている。当然、一番出汁でとられたと思ったものが、よく吟味すると間に合わせの化学調味料だったりするのであった。しかし、これは手抜きと言うよりも、取材不足に起因する下拵えの不備によるものだと思う。
下拵えに時間をかけ、推敲を重ねれば、この作品は誘拐ミステリーの歴史に新たな金字塔を打ち立てる画期的な傑作になる。議論はあったものの、われわれ選考委員は最終的に全員一致で、そう判断を下した。本賞の創設意義からしても、然るべき判断だったと、いまも信じている。
優秀賞に決まったハセノバクシンオー氏の『ビッグボーナス』は、小説そのものは小粒だが、これもまた、大いなる原石の輝きを十全に感じさせる作品だった。何よりも素晴らしいのは、パチスロ業界の圧倒的ディテールと裏ギャンブル社会の匂うがごときリアリティである。作者がアンダーグラウンドの世界に精通しているであろうことは、一読歴然と映る。取材や想像だけでは決して補いきれない迫力が、真剣で斬り合った者だけが持つ迫真の息遣いが、作中に横溢しているからだ。それを軽妙なユーモアに包み、軽いタッチのノワールに仕立て上げたところが、この作家の将来性を保証していると感じた。いささか説明不足な点や前後半のタッチの乖離、予定調和の定型に落とし込む安易な展開など、書き直すうえでの課題も少なくない。だが、阿佐田哲也や浅田次郎に連なる地下水脈からまたひとり、極めて有望な才能が噴出したことは、間違いないところだ。
横山仁氏『昭和に滅びし神話』と浜田浩臣氏『葡萄酒の赤は血のかほり』は、残念ながら作品に煌めきを感じられなかった。手垢のついた素材に挑むなら、その調理法にはなおさら斬新な工夫が必要だろう。島村ジョージ氏『愛は銃弾』には、まだしも原石の微かな輝きが感じられる。エンターテインメントの第一義は、読者を愉しませることにあるのであって、自分が愉しむために書くのでは所詮、同人誌レベルを脱却できない。そのことを胸に刻んで、これからもいっそう精進していただきたい。
ともあれ、第2回目もこうして、優れた才能を世に送り出すことができた。選考委員として慶賀に耐えない。願わくば来年もまた、この喜びを味わいたいものである。
吉野仁
応募者に望む! つねに新作で挑戦してほしい
『このミス』大賞最大の特徴は、なにか。それは選考委員がすべて書評家ということである。
みな長年にわたり膨大な量の小説を読み込んでいる。新人賞の予備選考を数多く担当してきた。文章力やドラマづくりのうまさ、もしくは想像力ないし創造力の豊かさなど、プロとして認められる基本的なレベルを把握している。
そのうえで、とくに新人に求めるのは個性的で斬新な才能だ。これまで発表された作品の下手な焼き直しにすぎないものほど最終選考では低い評価となる。もちろん、この世に完璧なオリジナルはない。だれもみな親から生まれる。問われるのはあくまで安易な猿真似、不味い二番煎じである。
今回、柳原慧『夜の河にすべてを流せ』が大賞作として選ばれたのは、まさに新奇な特性が発揮されているからだ。誘拐ミステリーとしてのアイデアや動機、人物など、これまでにない発想がいくつも生かされている。なにより予測できない状況の流れを追ったストーリーがいい。誘拐ものにありがちなパターンを単純になぞっておらず、先が読めない。この点を高く評価した。
残念なのは、多彩な人物をうまく書き分けているなか、ヒロインらしき女性刑事にいまひとつ華がないところ。さらに欲をいえば、軽妙に展開していく分、個々の場面がものたりない。他の選考委員から設定の甘い部分が指摘されたが、全体にもうすこし深みと臨場感がほしかった。
一方の優秀賞、ハセノバクシンオー『ビッグボーナス』は、パチスロ機の攻略法を売る怪しげな情報会社社員が主人公という異色犯罪小説である。クセの強い連中による、知られざる世界の興味深い内幕をみせる。クレーム客とのやりとりをめぐる場面のなんとリアルなこと。やり手社員の口八丁手八丁ぶりとギャンブル中毒者の生態がそこにある。必ずしも題材の珍しさだけにとどまっていない。ユーモラスでテンポがよく痛快。こういう小説を書ける作家はいまの日本に少ない。
ところがこの作品、一読しただけでは何を言いたいのか分かりづらい文章が冒頭から目立つ。ひとりよがりな描写も多い。体言止めの悪しき多用ばかりか、後半いきなりシリアスで破滅的な活劇に転ずるなど、馳星周もどきに堕ちてしまう。それこそ安易な猿真似だ。ミステリー小説としての完成度は、はっきり言ってぎりぎりのレベルかもしれない。
だが、多くの欠点がありながら、長所だけをとりだすと、もはや人気作家となるのは確実とおもえる才気に満ちている。いまから次作が愉しみだ。それだけの魅力を放っている。ある意味で、もっとも本賞らしい作家を世に送りだす結果となったのかもしれない。
今回受賞を逃した残りの三作のうち、まず横山仁『昭和に滅びし神話』は満州を舞台にした歴史活劇。主人公らしき中国人が単なる狂言まわしでしかなく、むしろ実在した人物の歴史をなぞっただけという印象しか残らなかった。登場人物に共感を覚えたり、その行方が気になってはらはらどきどきしたりする要素がどこにもないのだ。個性的で実在感のある人物の創造やクライマックスに向けて盛りあがっていく話作りをこころがけてほしい。
島村ジョージ『愛は銃弾』は、ていねいな筆致ながら、あまりに紋切り型の調子と内容だった。洋館「白薔薇館」、年上の美少女「大河内沙羅」、偶然による「運命的な出会い」がたび重なるなど、まるで大昔の少女漫画を読んでいるような古くささと気恥ずかしさを覚えてしまった。大仰な語り口のわりに、サスペンスや意外性に欠ける。登場人物らの過激で悲惨な過去もみなありがちな話ばかりだ。何度も述べるように、この賞が求めているのは、これまでさんざん書かれたもののコピーではない。その点を克服しないかぎり、受賞は難しいだろう。
浜田浩臣『葡萄酒の赤は血のかほり』は、『昭和に滅びし神話』と同じく満州を舞台にはじまる歴史物語だ。スパイあり、暗号あり、仮面舞踏会の殺人ありと盛りだくさんの趣向ながら、どれも詰めが甘い。類型的な人物の登場とご都合主義の展開ばかり。地の文が古めかしく凝った文章なのに現代風にくだけた会話の箇所があるなど、ちぐはぐな部分ばかりが目にとまった。
しかも、あとで判明したのだが、この作品、かなり以前にある新人賞へ応募されたものと内容的には同一らしい。大幅に書き直したにせよ、すでに今年も別なジュニア小説の賞に応募し落選しているようだ。いま新人賞が乱立している。小説のかたちがある程度できあがってさえいれば、予備選考までの通過は案外やさしい。問題はその先である。落選したあと何年も同じ作品にこだわりちょっとした手直しや題名を変えて違う賞に応募するよりは、できればつねに新作で挑戦してほしい。これはすべての応募者に望むところだ。