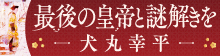第1回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
仕事を忘れさせてくれる原稿に出会えた
大森がこの一年で目を通した小説新人賞の応募原稿はたぶん400本を越えるはずだが、仕事を忘れて読みふけるような作品はせいぜい片手で足りるほどしかない。したがって、今回、仕事を忘れさせてくれる原稿2本に出会えた時点でこの賞の成功は確信できたし、その両者がそろって大賞に選ばれたのは当然の帰結。じっさい、選考会はあっという間に結論にたどりつき、あとは主に手続き上の問題を議論していただけだった。
とはいえ、選考委員4人の趣味・嗜好はてんでばらばらなので、作品の質に関する評価は一致しても、好き嫌いの差は当然ある。
大森が個人的に深く惚れ込んだのは、東山魚良『タード・オン・ザ・ラン』。タランティーノのスタイルとガイ・リッチーの下世話さにコーエン兄弟の諧謔をブレンドしたような――と形容するのは誉めすぎかもしれないが、とにかく一気に読ませるノリノリの脱獄小説。戸梶圭太や小川勝己の作品にはじめて触れたときの興奮が甦り、ページを繰る手が止まらない。
現代の日本で脱獄小説を成立させるために無理やりな大ウソ(刑務所から逃げたら目玉が飛び出すアイ・ポッパー)を導入する方法論は『バトル・ロワイヤル』流。そのシステムをぬけぬけとことこまかに説明し、強引に納得させてしまう手つきがすばらしい。破天荒な設定が超個性的なキャラクターたちとうまくマッチして、なんとも独創的な小説に仕上がっている。思わずamazonでローリング・ストーンズの『Exile on Main Street』(メイン・ストリートのならず者)を注文し、タイトルの元ネタになっている「Turd on the Run」を聞きながらあらためて読み返したくらいだ。
前半にくらべて後半の展開が弱いという指摘はなるほどもっともだが、必ずしも致命的な欠陥ではないと思う。脱獄に成功したあとはどこかでひと息つきたいのが人情だろうとつねづね思っていたから、この小説の後半のだらけた感じにはけっこう共感できたし、現代犯罪小説のお約束的な要素やご都合主義の導入も、まあ許容できる範囲。とはいえ、「後半を書き直せば年間ベストワン級の傑作になるのに、このままではもったいない」という意見も納得できたので、「改稿を前提とした銀賞授与」という決着に賛同した。モデルチェンジして刊行された暁には、ぜひ三池崇史監督で映画化してほしい。
一方、浅倉卓弥『四日間の奇蹟』は、それと正反対の端正で上品な感動作。『タード・オン・ザ・ラン』がストーンズならこっちはベートーヴェンがモチーフで、「月光」の響きにふさわしい格調を誇る。文章、キャラクター、会話、プロット、ストーリーテリングなど、どの要素をとっても技術的には完璧に近く、この小説をこれだけうまく書ける作家は、プロでもそうはいないだろう。
唯一の難点は、作品のアイデアとモチーフが複数の(それもきわめて有名な)先行作を容易に連想させること。読者によっては致命的な欠陥だと見なす人がいてもおかしくない。出版後に当然予想されるその批判をこの賞が(つまり選考委員が)引き受けられるのか。新人賞受賞作に期待される「新しさ」や「意外性」に乏しい本作が、それでも大賞に値するだけの魅力を備えているのか。選考会が瞬時に導き出した答えはどちらもYES。
アイデアのオリジナリティはきわめて重要だが、それだけに拘泥して小説の値打ちを見失うのは本末転倒だろう。『四日間の奇蹟』は、すでにクラシックの風格を備えている。減点方式で選ぶ新人賞からは登場しにくい本作に大賞を授賞できただけでも、この賞の存在意義があったんじゃないかと思う。
優秀賞の『沈むさかな』は、選考委員の中で大森の評価がいちばん厳しかった作品。主人公が中華料理屋でバイトする場面やダイビングのディテールは抜群によく書けていて、青春小説の側面はすばらしいが、その一方、偶然に頼りすぎたプロットや、リアリティに乏しい真相、現実味のない会話など、欠点も少なくない。この作品にかぎらず、エンターテインメントなんだから事件を派手にしようと考えて(どこかで見たような)大風呂敷を広げるのはむしろ逆効果だと思う。とはいえ、二人称で長編ミステリを書くという難事をやりとげた筆力と非凡な個性は評価できる。
その他の候補作についても簡単に。『そのケータイは、XXで』は、秀逸な発想を無神経な文章が殺している。肝心のケータイ関連の描写や使い方にも二、三首を傾げる箇所があった。いまどきのケータイのリアリティがきちんと表現されていれば傑作になったかもしれない。『熱砂に死す』は反時代的に古風なスタイルが貫かれた小説。抑制の効いたタッチで進む前半は好感が持てるが、中盤からのラブストーリー要素があまりにも類型的で興を殺ぐ。『俄探偵の憂鬱な日々』は、第一話、第三話のインチキ商売のアイデアがいい。軽いタッチで楽しく読めるコンゲーム小説だが、長編新人賞を狙うには不利な作風だろう。連作としてもいまひとつバランスがよくない。
香山ニ三郎
最終候補の6作は色とりどりで、読み応えも充分
えーっ!(嬉しい悲鳴)こんなん、読んだことないよォ、というのを読ませてくれ──そんな破天荒なエンターテインメントこそ『このミス』大賞には相応しい。とはいってきたものの、正直初回から傑作目白押しというわけにはいかないだろうと思っておりました。が、いざフタを開けてみたら、最終候補の6作は色とりどりで、読み応えも充分。これもやはり選考委員の顔触れの賜物と自画自賛したいのは山々ですが、応募者皆様がリキの入った作品を出してくれたおかげです。
ここから半分は落とさなければならないとは殺生ですが、差し当たって次の3作を外すことに致しました。『熱砂に死す』は出版編集者の青年がサハラ砂漠で失踪した異母兄の足跡を追うお話。主人公を軸にした人間関係劇の演出が巧みで、青春小説、家庭小説、恋愛小説の諸要素を活かした一気通読のミステリーロマンに仕上がっています。が、巧い反面、演出も人物造型もいささか類型的で古臭い。とりわけ女性像が通俗に過ぎ、随所でツッコミを入れたくなりました。どうせなら兄弟ではなく姉妹の話にして、後半はアフリカを舞台に冒険活劇調に転じて欲しかった!?
『そのケータイは、XXで』はふたりの娘が山間の温泉でトンデモない騒動に巻き込まれるホラー調のサスペンス。因習的な村のありさまや暗躍する殺人者の謎(公衆便所での死闘!)等、いかにもパロディめいた設定はそれなりに楽しめるものの、粗っぽい語りやご都合主義的な展開等、修正点は多々あります。個人的には溢れんばかりのバカミスパワーを高く買っているのであまり煩(うるさ)いことはいいたくないけど、今後は話の練りかたにいっそう力を入れて下さい。
『俄探偵の憂鬱な日々』は大阪のインチキ探偵コンビが一攫千金を狙って様々な儲け話をでっち上げるコンゲームもの。熟れた語りでコンパクトに仕上がっている点はさすがプロの技量を感じさせますが、プロの皆さんには一般応募者以上に型破りな話作りを期待したい。そこそこ読ませる作品ではなく、自分の殻を破る野心作でチャレンジ願います。
残る3作はどれも外すには惜し過ぎる──と思っていたら、幸いにも選考委員一同、考えは同じだったようです。
優秀作の『沈むさかな』は「きみは……」という二人称による瑞々しい語りにのっけから惹かれました。ただ主人公が父の死にまつわる謎を追っていく前半は、暗いといおうか陰の薄いキャラ造型のせいもあってか、いささか鈍重で華に欠ける気がしたのは否めません。むろんそれは濃密な描写と裏表でもあり、そこまで重く感じたのは小生ひとりだけのようでしたが。いっぽう後半は、陸に海に、一転して華々しい展開を見せます。前半が重かった小生としてはダイナミックな活劇演出等、好ましく感じましたが、そちらはそちらで仕掛けかたに賛否両論あったりして。いやはや、作品の評価って、ホントひと筋縄ではいきません。ともあれ、筆者が並々ならぬ技量の持ち主であるという点では異論なく、納得の優秀作といっていいでしょう。
受賞作については、1本に絞るなら『四日間の奇蹟』のほうというスタンスで臨みましたが、これまた2作同時受賞というベターな結論に達してよかったよかった。『タード・オン・ザ・ラン』は近未来の福岡を舞台にした脱獄活劇で、多国籍のタフガイたちのくそったれぶりはすこぶる上等、犯罪被害者の絡ませかたもカッコよく、前半を折り返した段階では今回はこれで決まりかと思いました。だが後半、話は期待したほどうねりも膨らみもせず、収束してしまう。意外なキャラを用意してそれなりに読ませはするものの、選考会でもこの失速ぶりがやはり問題になりました。そこを修正していただくという条件付きの受賞が“銀賞”という形になったわけですが、刊行に当たって本篇がどう変身するのかということもさることながら、何より国際級の力量を備えたこの作者の才能が今後どう開花していくのか、大いに楽しみです。
いっぽう『四日間の奇蹟』はひと言でいえば、癒しと再生のファンタジー。作者は挫折した音楽家と少女ピアニストの宿命的な出会い劇を織り込みつつ、彼らの演奏旅行のありさまを丹念に綴っていきます。ふたりの交情を軸にした濃(こま)やかな人間ドラマ演出の妙。「癒し」という言葉を見て引いてしまう向きもありましょうが、食わず嫌いはいけないよ。小生も奇蹟が起きる前に、すでにこの物語に取り込まれてしまったといって過言ではありません。ただ他にも問題がないわけではなく、ミステリー系を読み慣れた人なら、程なく似たような先行作品があることにお気づきになるはず。他の新人賞ならそれが致命的な欠点になりかねませんが、小生、それを認めたうえでなお、本篇の豊穣な物語力に脱帽せざるを得なかった。参りました。本篇にひとりでも多くのファンが付くことを願ってやみません。
茶木則雄
3作に共通するのは卓抜した文章力と導入部の巧さ
白熱した選考会であった。サイトでも紹介されている通り、確かに選考委員の間では、激論――と呼んで差し支えない議論が展開された。掴み合いの喧嘩こそなかったものの、最終選考会が紛糾したのは事実である。
しかし議論が縺(もつ)れたのは、選考委員おのおのの間で大賞に推す作品が異なったためではない。むしろ、大賞候補は呆気ないほど簡単に、最初の討議の段階で早々と絞られた。浅倉卓弥氏の『四日間の奇蹟』と東山魚良氏の『タード・オン・ザ・ラン』、ティ エン氏の『沈むさかな』の3作である。
率直なところこの3作は、選りすぐられた最終候補作のなかでも頭ひとつ抜け出ていた。作風はそれぞれ異なるが、共通するのは卓抜した文章力と導入部の巧さである。
『沈むさかな』の冒頭――主人公が魚を捌く場面の情景は、今でも頭に焼き付いている。鮮烈なのは、そのイメージ喚起力だ。主人公の孤独な内面と鬱屈した日常を、冒頭のこのシーンひとつで見事に映し出す筆力は、只事ではない。また『タード・オン・ザ・ラン』の、主役たちが登場する本編の導入部は、この作家の持つ傑出した才能の一端を、まざまざと見せつけてくれた。ジェフリー・ディーヴァーを思わせる《語り=騙り》のテクニックは、新人のレベルを遥かに凌駕している。同様に『四日間の奇蹟』の冒頭も、実に印象的であった。一読、何が行われているか把握しづらいのは、このシーンが「説明」をいっさい排した「描写」のみで構成されているためだ。だが、主人公と少女の関係および二人の置かれた特異な状況を把握した後で読み返すと、その巧さに舌を巻くことになる。まるで旋律が聴こえてくるかのようなピアノの演奏シーンを含め、この作家の完成された文章力は、新人賞レベルでは特筆に値すると言っても過言ではない。
問題は、この3作が、読者の目に触れれば当然指摘されるであろう弱点――もしくは欠点を、それぞれ抱えていたことだ。
大多数の読者から最も容易に指摘される弱点を抱えているのは、『四日間の奇蹟』だろう。この小説の核となる唯一の仕掛けは、ミステリーファンならほとんど誰もが知っている有名作品のネタと同じものだ。この点に関しては、是非をめぐって非常に突っ込んだ議論が行われた。が、ネタそのものは前々からすでにあったものだし、物語自体は作者の完全なオリジナルに仕上がっている。むしろ、あえて同じネタに挑戦した作者の意欲こそを買うべきだろう。何よりも、問題の先行作品をも凌ぐ感銘――実際、クライマックスからラストまでの数十ページ、私は心揺さぶられ、泣き通しだった――を与えてくれる作品の素晴らしさを、高く評価したい。そうした意見が続出するに至り、大賞はこれで決定という雰囲気が支配的になった。
ところが、残り2作の処遇をめぐって議論は俄かに縺れはじめる。というのも、傑出した “原石”をいかに掬いだすか――それがそもそもの、本賞創設の目的のひとつだったからだ。減点法で無難な作品を選ぶのではなく、たとえ破綻があっても、瑕のひとつやふたつあったとしても、真に優れた、もしくは大いなる可能性を秘めた“才能”を選び出そう。これが事前の諒解事項だった。1次選考に携わった委員はもちろん、2次選考から参加した委員にも、また最終選考を委託された委員にも、その趣旨は徹底されていた。
『沈むさかな』の場合、弱点はふたつあった。いずれも、メイン・トリックとミスディレクションに絡む微妙な問題である。書き直しのうえ刊行されることが決まっている以上、具体的な記述は避けるが、手を加えた方がさらに良くなることは明白だった。これは選考委員全員の一致した見解である。ただ、二人称の語りとメイン・トリックを有機的に絡めた精緻な構成と、青春小説としての瑞々しい魅力は、それだけでも充分、何らかの賞に値するものと言えた。
さらに揉めたのは『タード・オン・ザ・ラン』の処遇をめぐってだ。この小説の場合、それは弱点と呼べるような生易しいものではない。明らかな欠点――それも非常に大きな欠点を、作中に抱えていた。一言で言うと後半が破綻しているのである。しかしこの小説は、その欠点を補って余りあるほどの輝かしい魅力に溢れていた。具体的には、タランティーノやバンカーを彷彿させるアウトローたちの突出した魅力と、国産作品とは思えないクールな語り口のセンスである。後半を書き直せば、とんでもない傑作になる可能性を、この作品は秘めていた。創設時の目的からすれば、これも充分、賞に値する作品と言えた。
しかしだからと言って、まったく書き直す必要がない作品と書き直しを前提にした作品を同列に処遇するのでは、明らかに問題がある。
選考会は議論に議論を重ねた結果、ようやく全員が納得する落とし所を見つけた。すなわち、大賞に急遽、金賞と銀賞を設け、優秀賞を出したうえで、賞金総額1400万を4対2対1で分けるという案である。
確かに前例のない方式、ではある。しかしそれも、《このミス》らしいと言えば、らしい。
最後に、受賞者の方々に心より祝福のエールを贈る。個人的には、金賞を受賞した『四日間の奇蹟』は、ここ十年の新人賞ベスト1である。銀賞『タード・オン・ザ・ラン』の前半は、それだけでミステリー史に残る年間ベスト1級の傑作だと思う。優秀賞『沈むさかな』は、手を入れれば、大賞受賞作であってもおかしくないほどの傑作になり得るはずだ。記念すべき第1回からこれほど凄い才能に出会えたことを、心から感謝したい。
吉野仁
次の作品もぜひ読んでみたいと思うような書き手
吉本興業のお笑いタレント、ホンコンがよく酒の席で若手の芸人らに説教するそうだ。おまえら、ギャグの三原則をいってみい、と。「つかみ、本ネタ、オチや!」。酔うごとに、耳にタコができるほど繰り返すという。この三つの要素、ミステリーでも同じだ。つかみ、本ネタ、オチとはすなわち、魅力的な謎、(犯罪をめぐる)物語のスリルとサスペンス、意外な結末のことである。出だしで読み手を作品世界に引き込み、ページをめくるたびにはらはらどきどきさせ、クライマックスでは大きな驚きや快感や感動を与える。さらに、文章やキャラクターがしっかりと書かれており個性的であるならば申し分ないだろう。
記念すべき第1回『このミス』大賞を選ぶにあたって、理想をいえば、これらの要素がすべて揃っているに越したことはない。だが、プロ作家でさえ難しいハードルをデビュー前の新人が飛び越えるのは至難の技である。まして作品のどこに魅力や驚きを感じるかは、読み手によって大きく異なる。絶対的な判断基準はどこにもない。百人いて百人が傑作と認めるミステリーがこれまでどれだけあったのか。また、すでにベテラン作家として第一線で活躍している書き手でも、みな処女作から高い評価を得てきたわけではないだろう。
ならば、あら探しをしたり、減点方式で採点したりするよりは、できれば長所を評価したい。小説として、あるレベルに達しているなら、『このミステリーはすごい!』といえる決定的な一面を持つものを筆頭に挙げたいのだ。次の作品もぜひ読んでみたいと思うような書き手に受賞してほしいのである。
そんななか、今回の最終選考作品のなかで、もっとも優れていたのが『四日間の奇蹟』だった。
けっして派手な題材の物語ではない。扱われているエピソードもさして目新しいものではないだろう。なにより誰もが指摘するだろうが、核となるネタの部分に有名な先行作品と同じ趣向が使われている。おそらくそれについて、鬼の首を盗ったように指摘し、小バカにするチンケなミステリーおたくも少なくないだろう。まして、最初に派手な謎が提示されたり、話が二転三転したり、怒濤のクライマックスへ突入したりはしない。あくまで淡々とした語り口で話が運ばれていく。にもかかわらず、『四日間の奇蹟』は、それらマイナスの部分を凌駕するほどの読みごたえを感じた。アイデアを巧く生かしている。感動へと導いてくれたのである。
大風呂敷を広げたはいいが、終盤になるとバタバタと辻褄合わせに終ってしまう作品は多い。その点、本作はじっくりと読ませつつ、最後までテンションが落ちないどころか、ラストに来るほどじわりじわりと盛りあがる小説だった。それまでの描写の細かい積み重ねがボディブロウのように効きだし、読んでいるこちらが最後でノックダウンしてしまった。
欠点だけをとってこの作品を落してしまうのは罪な話である。あらゆる人にとり完璧ではないかもしれないが、この感動は捨てがたい。その思いは、他の選考委員も同じだった。そこで、本作が大賞に選ばれたのだ。
一方、『タード・オン・ザ・ラン』は、また別の意味で大きな問題があった。後半部分があまりに弱いのだ。しかしながら、おおげさにいえば、前半部だけでも大賞に値する面白さだった。監獄脱走ものという、海外では珍しくない題材と内容ながら、国産ではいままでに読んだことのない圧倒的な凄味と魅力をそなえていたのだ。だが、このままで本にすると欠点のほうが目立つだろう。その理由で世に出ないのはあまりに惜しい。そこで、書き直しすることを条件に、あえて銀賞という扱いにした次第。いまは、その判断が正しかったことを願うのみである。
また『沈むさかな』もまた、せっかくの優れたアイデアを生かしきっていないとの欠点が指摘された。その部分をうまく処理しさえすれば、大賞になっていてもおかしくない出来栄えなのである。こちらも一部を書き直すことで優秀作に決定した。
そのほかの候補作に関しては、基本的に受賞レベルに達していないと判断した。あまりにご都合主義がすぎたり、設定や文章に甘さが目立ったり、アイデアが凡庸だったりしたのだ。大賞賞金1200万円どころか優秀賞200万円を得るにも至らない。
たとえば、ふつう作家が得る印税収入は、本の定価の10パーセントが相場である。すなわち1200万円の賞金とは、極端にいえば作品そのものに対して1億2000万円の価値を認めたことになる。
1億円をこえる面白さの、つかみ、本ネタ、オチ、そして文体とキャラ。それだけのエネルギーを費やし情熱をこめ、これまでにない内容と完成度をもった小説を書いてほしい。新たな応募者は、ぜひともこれから一年間かけて挑戦していただきたい。