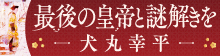第23回『このミス』大賞 2次選考選評 村上貴史
魅力的なエンターテインメントとして磨かれたものを求む
今回の二一作品、いずれも愉しく読ませて戴いた。しかしながら、選考という視点で比較すると、まずまず顕著な差があった。最終選考に進むことになった七作品、それに準ずる作品(支持者はいたが上記七作品に競り負けた作品)、それ以外、である。その順にコメントしていこう。
最終選考に残った七作品のうち、『私の価値を愛でるのは? 十億円のアナリスト』と『九分後では早すぎる』は、自分が一次で選んだ作品。いずれも他の選考委員からの支持を得て最終選考に残った。
後者と同系統なのが、『謎の香りはパン屋から』である。いずれも“日常の謎”系ではあるが、物語が進むにつれ重さや苦さが変化していく『九分後では早すぎる』と比べ、こちらはよりピュアだ。謎そのものは決して強くはないが、この作品世界に相応しい重さの謎で、バランスが良い。二作それぞれに特徴があることから、両作品を最終選考に残すことにした。
『一次元の挿し木』は、二〇〇年前の人骨と四年前の失踪者のDNAが一致するという謎をはじめ、長所が沢山ある小説だった。遺伝人類学を専攻する主人公の専門家らしさもきちんと書けているし、一方で“ちゃぽん”という擬音の活かし方も巧みだ。展開が生じさせるスリルも、描写で感じさせるスリルも、いずれも備わっている。なお、真相そのものに弱さはあるのだが、それをこの形で魅力的なエンターテインメントに仕上げる腕力は評価できる。また、関係者が少々喋りすぎるきらいはあるが、圧倒的な長所を否定するには至らない。最終選考に強く推した一作だ。
『わたしを殺した優しい色』は、前世の記憶を持つという大学生の桃子が登場し、その記憶を活かして過去の殺人事件の真相を探ろうとする作品。町田の歓楽街の案内役という主人公と桃子のコンビネーションが素敵で終盤までテンポ良く読ませてくれたうえに、予想しない角度でのサプライズが用意されていて満足の一作。
残る二作は、若干評価は落ちる。『どうせそろそろ死ぬんだし』は、余命宣告を受けた終末期患者たちが山奥の別荘に集まり、そこで殺人を疑い得る不審な死が生じるという“何故”の魅力で読み手を捉え、そこに別種の仕掛けをトッピングして愉しませてくれた。合わせ技一本というかたちで評価した。
『魔女の鉄槌』は、十六世紀の魔女裁判のある世界のミステリだ。展開が巧みで頁をめくらせてくれるし、所々で披露される小理屈も心地良い。重要人物に関する“実は○○だった”でも愉しませて貰った。一方で、「古文書を翻訳した」といいつつ「現代知識を前提した描写が随所に見られる」という“額縁”の曖昧さと、その額縁内の物語の視点の在り方には、疑問が感じられる。パーツの魅力の強さで、最終選考に残すことに同意した。
続いて、惜しくも最終選考進出を逃した作品である。私としては、是非再挑戦してほしい方々だ。
『十二人のイカれた人々』は、人里離れたカラオケボックスに殺意を抱えた人々が偶然集まってきて騒動が起きるという物語。限定的な舞台での連鎖反応が非常に愉しい一作だった。この作品、一夜の物語ならではの勢いはよいのだが、登場人物たちがけっこう愚かな者ばかりだから成り立つ勢いでもあって、手放しでは支持しにくい。あちらの出来事とこちらの出来事をうまいこと関連付ける才能はあるように思えるので、本作の勢いを削がぬかたちで、より丁寧な人物造形(賢さ増量も含む)と、丁寧な描写を心掛けて戴きたい。
バンドマンだけでは食べていけないドラマーの青年が主人公の『ナノフィアの楽園』は、その主人公と仲間たちの魅力がとにかく際立っていた。彼らは、知り合った少年の父親の自死の謎を探ることになるのだが、そのなかでの各自の価値観の描写が極めてナチュラルであり、しかも、各人の個性が活かされるかたちで事件の解決に繋がっていく。残念ながら事件の構造そのものに新鮮味がなかったために最終選考は逃したので、そこに気を配った新作を期待したい。
自分が一次選考で推した『鼠』は、テロリスト側が次々繰り出す多様な仕掛けなど、長所である推進力は評価されたが、一方で、警察内部での争いなどが類型的との指摘も受けた。プロットレベルでの強化が必要ということになる。このジャンルでの受賞を目指すのであれば、本賞でデビューした安生正の作品を、書き手の視点で研究してみるのがよかろう。
『シビュラの囁き』は誘拐ミステリとしてスリリングに愉しめたのだが、中盤以降、真相を読者に対して隠し切れていなかった。また、その真相が「誘拐」という形をとる必然性にも弱さがある。意外性を求めたのだろうが、強引に真相を構築しても無理が生じるだけだ。さらに、多重人格、という設定の使い方にも唐突さを感じた。前半の筆力を最後まで活かせるようなプロットを考えてみてはどうか。
『境界探偵とゴミ屋敷の殺人』は、境界探偵という仕事に着目した点を評価したい。ただし、事件が発生するまでに時間が掛かりすぎる点や、探偵役の設定に唐突感がある点など、せっかくの着眼を活かせていない。誰が推理を披露するかという点を含めて、別の事件で境界探偵が活躍する小説を読んでみたい。
残るは、それ以外の作品だ。
近未来SFアクション『電気犬の見る人間の夢』は、活劇描写やスプラッター描写などから熱が伝わってきて好感が持てた。一応警察小説という枠組みも作られてはいる。とはいえ、ミステリの賞で最終選考に残るには、顕著なサプライズが“アンドロイドの妊娠出産”だけでは厳しい。ミステリとしての特筆すべき魅力を探してみて戴きたい。また、SFとしての既視感が他の選考委員からも指摘されていたので、その点も対策が必要だろう。近未来にこだわらないという手もある。
『1962 流浪の殺人』は、北朝鮮の密偵が日本にやってきて、あるプロパガンダ小説に秘められた謎を探るという小説。そのプロパガンダ小説が唐突に完成したように読める点や、あるいは、そもそもの北朝鮮側の動きに不自然さが否めない点など、問題点が散見される。各場面での登場人物描写などは悪くないだけに、謎の作り方や解かせ方の工夫が必要になる。
『夜の歌、ピクシーの歌』は、聴くと死ぬ歌、という題材は、ありふれてはいるが、やはり魅力だ。しかしながらその真相にもう一つ説得力がなかった。順調に読み進むことができていただけに、残念である。どこまで真相から逆算して書いたかは不明だが、その観点での設計も必要だろう。
『RION』は、サイコキネシスという飛び道具をエンターテインメントとして活かすというより、それに依存するかたちになっているのが残念。昨年の最終選考進出という成果と、今年の結果について分析してみると、おそらく御自身の長所短所が見えてくるのではなかろうか。
グリーン・ウォッシュという題材を格闘家の探偵と組み合わせた『sustainable woman』は、題材の社会性や県知事殺害という事件の大きさと、警察捜査と、市井の格闘家探偵とのバランスが不自然だった。題材への着眼点や探偵役の設定の妙は評価できるので、それをどうミステリとして説得力を持つ物語に仕上げるかがカギとなる。
北海道を舞台とする警察小説『悪神』は、全体としてゴツゴツした読み応えで悪くない。「鯨」という謎めいた男の存在感もよい。ただし、事件の真相に新鮮味がなく、結果的に突出したものがないまま、二次選考で終わりとなった。最終選考進出には、事件か人物か驚愕か、何らかのプラスαが必要不可欠だ。
『わたくしは探偵を殺します』は、倫理観の欠如した主人公が探偵を殺そうとする経過を描いているが、主人公の行動に説得力が乏しく、また、犯行計画も緻密さが欠ける。このアイディアを犯罪小説というエンターテインメントに仕上げるためには、基礎工事からやり直すのが、結局は近道だろう。
『探偵と五人の息子たち』は、私立探偵と居候の物語なのだが、物語の動きが遅いのが問題点。私立探偵の特徴(隠し子が四人いる)も活かしきれておらず、全体としてもどかしい。親子関係を巡る複数の秘密が仕込まれた構図になっているが、整理してメリハリを付けたほうが読みやすく仕上がったのではないかと思う。
『ラマダンの陽炎』は、来日したイスラム教徒が金のために闇の仕事として死体処理を行っているという犯罪小説だ。作中で描かれる各種の犯行が余りに短絡的だったり、物語のたたみ方が性急だったりと、エンターテインメントとしては磨き方が足りない。他の書き手の方々と大賞という座を争う場であることを強く意識して、御自身の作品を見つめ直して戴ければと思う。