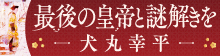第22回『このミス』大賞 2次選考選評 村上貴史
年に一度の応募機会を活かしてほしい
まずは最終選考に進んだ作品について。『溺れる星くず』と『箱庭の小さき賢人たち』は、一次選考で自分が選んだ作品。二次選考で競った他の作品と比べても、十分に優れていると判断して選考に臨んだが、他の選考委員からの支持も得て、無事、最終選考に進むこととなった。『ミイラの仮面と欠けのある心臓』は、古代エジプトという舞台設定を十二分にミステリとして活かしていて好感が持てる。要素の一つである密室のトリックだけを取り出してみると既視感はあるのだが、それはあくまでも要素の一つ。全体としてはさらに大きな“何故”の謎があり、それが圧倒的に見事な出来なのでさほど気にならず、最終選考に積極的に残すべき一作と判断した。『あなたの事件、高く売ります。』は、四人組の強盗団による信用金庫立てこもり事件からの目まぐるしい展開に魅了された。事件の骨格を冷静に眺めてみるとかなり強引なのだが(特に結末部分)、彼女たちのキャラクターによって、それがスムーズに読める小説に仕上がっている。長所を評価して最終に推す。『空港を遊泳する怪人の話』は、主人公が事件に巻き込まれる導入部が巧み。しかも、そこから先の展開も巧みでグイグイ読ませる。中盤で要素を盛り込みすぎて失速しそうになるが、なんとか終盤で勢いを取り戻した。全体としては新鮮味を強く感じさせてくれて推したくなる一作だ。『龍と熊の捜査線』は科学捜査の魅力が詰まった作品。技術の読者への紹介も手際よいのだが、それだけに、現代のネットセキュリティの基礎となっている技術を暗算で突破できるという設定(それに登場人物たちが違和感を覚えない)にはいささか疑問あり。それが重要な要素の一つであるため、この一作は消極的推薦。
最終選考には残れなかったものの、選考会で評価が高かったのが『バンカー・バンカー』と『空白の椅子』。前者は、地下の秘密施設での連続殺人を十分なサスペンスで綴っていて愉しく読ませてくれたが、極めて大掛かりな仕掛けを複数の部外者を巻き込んで遂行する動機の説得力に弱さがあった。後者は(前者と同じく)閉鎖環境が舞台だが、こちらはディスカッションを通じて過去の事件が浮かび上がってくるという刺激的な構図の一作。デジタル・フォレンジックという美味な題材を用意しつつも本格的にそれと向き合わなかった点が惜しまれる。また、Aという事件の真相/その犯人を巡る事件の真相/それにまつわるもう一つの真相、という三段重ねの謎解きが、かえってそれぞれの衝撃を薄める結果となっていて残念。CPUの使い方にも疑問が残る。とはいえ、この両作品は最終選考進出にギリギリまで迫っていたので、書き手の方々には再挑戦を期待したい。
続いて、好感を抱いた作品について記しておこう。『マリンフラワーの密室』は謎が深まっていく造りで、心地良く読める。トリックも大小の細工を組み合わせていてまずます丁寧なのだが、物理トリックとしてもう少し説得力が欲しかった。また、ジュヴナイル小説のような読み味で、それにも好感を抱いたのだが、その点については他の選考委員から賛同を得られなかった。『失われし者のために』はホラー小説にミステリ的な趣向を盛り込んだ作品。筆力と人物造形、前向きな着地は評価するところだが、ミステリとホラーの融合という観点で新鮮味が欠けていた(ミステリとホラーの重ね方について著者がきちんと考えているらしいことは伝わってくるが、それでも、だ)。『不退転の花』は、一次で自分が推した作品。主人公の女性に対する周囲の反応が画一的である点などが指摘され、他の選考委員からの積極的な支持を得られずに、ここで闘いを終えることとなった。
以降の作品は、もうワンランク低い評価だった。『秘境駅に消える』は雰囲気よく読ませる鉄道ファンミステリなのだが、説明口調が時折顔を出し、せっかくの雰囲気を壊してしまっている。ある種の密室状況をめぐるトリックは、現場を知らない読み手としてはなかなかに愉しめたので、説明文で伝えている情報を物語のなかに溶かし込めるようになれば、もう一段進化できるはず。『脳取-ノットリ-』は、序盤の裁判の場面から引き込まれ、結末まで力強く読ませてくれる小説だったが、いかんせん荒い。登場人物の名前がブレていたり、別の登場人物と名前が入れ違っていたり、明らかな誤字が繰り返し使われていたりするのだ。本筋については読ませる力を感じただけに、丁寧な仕上げを身につけて戴ければと思う。メインストーリーとサイドストーリー(刑事コンビのドラマなど)とのバランスも見直した方がよかろう。『嘘つきな探偵に真実を』は、様々なかたちで読者を攪乱するミステリだ。そのなかで第三話が突出して謎の説明がスッキリしており、故に騙される感覚を心地良く味わうことができた。この攪乱と明瞭さのバランスを、他のエピソードや作品全体でも実現できれば、細かな伏線の巧みさからして最終選考を争えたのではないか。
最終選考進出が遠かった作品を続けよう。『ウィザーズエンド』は、異世界を舞台とする謎解きなのだが、その設定だけではもはや新鮮味に欠ける。犯人の設定が魅力といえば魅力なのだが、その隠し方にもう一工夫欲しかった。『ブリッジ』は、筆力はまずまず感じられたし、中心人物の造形はしっかりしていてよいのだが、事件そのもののデザインが強引だった。なお、後半におけるWhoやHowといった小見出しを用いた記述は、うまくすればこの著者の持ち味になるかもしれない。『悪魔のDスナイパー』は、現在進行形の出来事、すなわちウクライナへの侵攻を題材としている。そうした題材は、この賞の応募〆切や選考から出版に至る日程を考えると、執筆時点で最新の情報であっても、刊行時には一年ほど古びた情報になってしまう。書き上げて即刊行というスタイルが不可能な新人賞という枠組みには不向きな題材を選んだと考えざるを得ない。また、鮮度が欠けていても、小説として圧倒的に力強ければ賞にも至るだろうが、この作品は、日々現地から伝わってくる生々しい映像を凌駕するだけの何か(ストーリーやプロット、あるいは主人公の魅力など)が不足していて、推そうと思わせてくれない。しかも、「実在するウクライナの少年をモデルにした」と述べつつ、どの部分がそれに該当するのかは記していない。つまり、創作者としての著者の才能の判断にも困るのだ。セリフや擬音もコミックから切り抜いてきたようで、最終選考進出という結論は出せなかった。『容疑者「幽霊」』は、題名にもある幽霊という題材の活かし方に工夫が足りない。この真相を読者に納得させるには、そこまでに丁寧な仕掛けが必要だ。『見える人たち』もまた幽霊という題材を扱っている。展開を改善して中だるみを回避する必要があるし、セリフも小説としてのそれにすべく改善要。『悪魔のロジック神のセオリー』と『殿塚に呪いをかけないか』は、クイクイ読ませるという点では一定の水準に達しているが、最終選考に推薦した作品が備えていたような新鮮な魅力に欠けていた。『運命の子』もまた新鮮さに欠けるし、物語の動きも遅く、相対的に辛い点を付けざるを得ない。
『死に至る6バイト』は、昨年別の新人賞の選考時に読んだ作品。当時とタイトルを変える工夫は行われているが、登場人物の学校内での評価があっさり上下しすぎる点や、登場人物の(意外な)親子関係が都合よすぎる点などの問題点が全く改善されていなかった点には失望。学園サスペンスとしての魅力はあり、スピード感にも満ちているだけに、残念だ。『ニケの首』は、昨年、「次回作に期待」となった作品。同じ作品での再応募を否定するものではないし、過去には第15回の『がん消滅の罠 完全寛解の謎』(刊行時のタイトル)のように大賞受賞に繋がった作品もあるのだが、『ニケの首』についていえば、「次回作に期待」での評価からさほど変化が感じられない。特に、欠点として指摘された展開の都合良さは、今回の応募原稿でも残存していた。力量のある書き手だと感じるだけに、年に一度の応募機会をどう活かすかを考えてみてはいかがだろうか。