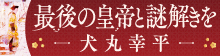第23回『このミス』大賞 次回作に期待
『266球という出来事』内野ライト
物語の構成と流れが巧みで話の展開にどんどん惹きつけられていく。登場人物が多いにもかかわらずひとりひとりの性格が明確に描写され、読者を混乱させない筆力も見事。【中】の視点人物となる清美沢監督の感情の揺れも、監督未経験者や野球を知らなくても充分に共感できるほどの普遍性があって、とても読ませる。ただ残念ながら、これをミステリ小説にカテゴライズするのは無理がある。一編のエンターテインメントとしてはとてもレベルが高いが、賞の性質上、展開の意外性だけではなく、ミステリとして謎と真相の意外性がほしかった。
『ジェームズ・ディーンは二度死ぬ』山下章太
ベトナム戦争、安置所の遺体すり替え事件の捜査、暗殺指令、さらに死から甦るファンタジックな要素まで加え、バランスよりも盛り込みを選び、大風呂敷で新人賞に臨んだ姿勢は歓迎したい。
ただし一人称が使いこなせておらず、状況の説明と描写の域から脱していないため、臨場感のない浅く平板な印象に終始してしまったのは残念。タイトルに絡めたせっかくの趣向も控えめなものになってしまい、ページ枚に〈僕〉が五回も六回も念を押すように繰り返されるのもしつこく感じた。
もし一人称小説に固執するなら、その視点人物が見るもの、聞くもの、嗅ぐもの、触れるもの、感じるものが、人生観、嗜好、生い立ち、価値観、感受性などを通じて描写されなければ試みる意味がない。一人称とは、じつはとても難度の高い手法なのだ。
この点を改善するには、より内外の作品を読み込み、量を書いて習得するしかない。いつか難しさをぶち破り、独自の語りを備えた雄大な小説をものしていただきたい。
『涅色に染まる人力車』鬼頭蘭丸
浅草で人力車の俥夫をしている主人公のもとに、死んだはずの考古学者だった父親から手紙が届く。内容は暗号文のようなもので、これはもしや徳川埋蔵金を追い掛けていた父からのメッセージでは? というなかなか面白い出だしから、さらに全身白の洋服で固めた年齢不詳の人物から「七月の間、奇数日に十時間の案内をして欲しい」という奇妙な依頼を受けるなど、読み手の引き込み方の上手さにまず目を見張った。
加えて、著者が経験者だからこその血の通った俥夫小説の面白さが素晴らしく、これはいい作品に当たったぞとうれしくなった。
だが、その期待は後半で残念ながら崩れてしまう。首相選を控えた大物政治家が選挙への影響を考え、殺人を偽装するというのもいささか荒唐無稽だが、そのためにわざわざ人力車を仕掛けに使うのは書き手側の都合といわざるを得ない。父親の暗号文のほうの結末が悪くないだけに、なんとも惜しい。
筆力のある方だ。読み手が「確かにこの方法しかない!」と膝を打つような仕掛けと謎解きで、ぜひふたたび挑戦していただきたい。
『カミサマの目』山平高志
せっかくの視覚共有能力なのに使い道がカンニングというスケールの小ささが妙に面白いのと、主人公が並外れて勉強ができないので書き写す練習から始めるディテールがいちいち楽しい。これはキャラ造形やセリフの巧さゆえだ。準備段階の面白さ、試験当日のトラブルをどう対処するかなどなど、ライトなSF青春コメディとしてとてもよくできている。読んでいる最中、とても楽しかった。ただ、これがミステリかと考えると少々弱い。全体的にコンゲーム的面白さがあるのと、予想をずらしていく展開や最後の「カミサマ」の真相とその伏線などにミステリテイストはあるが、物語の最大の魅力がミステリ以外のところにあるのは否めない。
『二条鏡花が死んだ日』真田霙
政府と密接な関係にある秘密組織を舞台とするスリラー。組織の役割は、暗殺を含む特殊任務だ。主人公の五十嵐修は組織の第一部隊に所属。彼のバディだった秋月楓の第ゼロ部隊昇格に伴い、新たなバディとして、新人の佐山美里を迎えることになったが、二人の関係は、秋月の元婚約者で、五十嵐の同期の友人でもある人物が殺されたことを契機に悪化していった……。
特殊な組織の中での殺人事件を、その組織ならではの人間関係のなかできっちりと描いていて好感が持てる。五十嵐と佐山の関係悪化といった人間関係の変化もなめらかに語られている。暗殺組織のメンバーが備えるべき非情さの描写にも過不足はないし、そのなかで、任務との葛藤を炙り出さすエピソードは秀逸だった。
物語も結末に至るまでにいくつかの仕掛けがあって愉しませてくれたし、二次選考に推す候補の一つとして読み進んでいたのだが、ある登場人物に関する設定(実はこんな過去が……というもの)には強引さを感じてしまった。また、フィリピンのマフィアとの関係も唐突な感が否めない(他の海外組織との関係に筆が費やされていないため)。これらの問題点により、他の一次選考通過作との相対評価で負けるという結果になった。
僅差である。次回は、自分の作品に強引さや歪さがないかを確認の上、応募されることを期待する。そうした作品を読めることが愉しみだ。
『派遣秘書・ルーラと迷探偵・西園地ノボルの事件簿』松下トモ
T大卒の元官僚ながら経営難で行き詰まっているダメ探偵と、奇抜な装いで「推し活」命な超敏腕派遣秘書。そんな迷コンビが活躍するライトテイストなミステリー。
キャラ造形とテンポに優れ、犬の捜索から殺人事件、そして駅裏の再開発をめぐる闇へとストーリーを広げていく話運びも上手い。
しかしクライマックスに至り、倉庫に隠した覚せい剤を売買して選挙資金を捻出、現役大臣から指示を受けたやくざの組長が殺し屋を動かすなど、物語の練り込みを放棄したような真相には大きく肩を落とさざるを得ない。政治家、やくざ、秘密結社、宗教団体、犯罪組織、殺し屋は、安易な使い方をすると読者が鼻白んでしまうことを肝に銘じておくべきだ。
軽やかで愉しい魅力をそのままに、よりミステリーとしての驚きや意外性の演出に力を注いでいただきたい。
『殺人金庫』竹鶴銀
昭和12年に天才金庫師の造った、開錠困難な三つの金庫からなる伝説の「三猿」。中には金塊が入っているとか、人を殺す金庫だとか、噂されていた。そのひとつ「桃猿」を開けるよう犯罪者に強要された鍵屋の力丸(リッキー)は、開ける際に命を落とす。リッキーの弟子で「金庫の声が聴こえる」力を持つ芦田錠(ジョー)は、師匠の娘・佐知を引き取って鍵屋を始める。だが数年後、ジョーは殺人事件に巻き込まれてしまう。やがてその事件には「三猿」が関係していることが判明する……。
伝説の金庫とか、金庫内密室殺人とか、扱われる要素はなかなか面白い。だが作品の前半部分では、話がどちらに向かうのかが分かりにくい。そのために、読ませ続ける力が少し弱い。
また主人公の「金庫の声が聴こえる」という特殊能力が、作品全体の世界観から浮いてしまっているように思われた。いわゆる「チート能力」的なものであり、異世界ファンタジーならばそれもいいが、ミステリーにおいてはそぐわないのではなかろうか。何か、そのような能力を持った「理由」が、超常的なもので構わないから語られていれば、もう少し読者を納得させられるのだが。
金庫についてはよく調べているようで、歴史や構造についての薀蓄も語られる。これは悪くない。
一方、主人公が自動車で移動するたびに、移動ルートがやたら詳しく説明される。これは作者の好みなのかもしれないが、話の本筋にかかわるのでなければそこまで細かくなくていいと思う。作品全体において「説明のバランス」を意識すれば、完成度はより上がるはずである。
『すべては映画のために』阿波野秀汰
ある映画のスタッフや出演者たちが情報共有に使用するアプリの事故で、誰かのスマートフォンにあったと思われる動画が一部の関係者に流出する。そこには、事故で亡くなったとされていた俳優が、撮影者の手によって崖から突き落とされる様子が映っていた。しかも、そこにはこの映画の主演女優の姿もあった。映画の主演女優が所属する芸能事務所の社長はスキャンダルを恐れ、まずは内部調査を行うという。かくして、映画撮影のさなか、動画の流出元と疑われる7人が集められた……。
自然な語りと会話で読ませる、特異な状況での犯人捜し。アプリの事故はややご都合主義に思えるものの、芸能事務所の社長の思惑や、関係者が集められる過程はうまく描いている。
気になったのは、物語の核となる動画の撮影状況だ。スマートフォンで撮影して誰か識別できるくらいの距離に女優がいるような状況で、他人に知られたくないことをあれこれ話した上に殺人を行うのだろうか、という点が気になった。また、造形師の入れ替わりや、別れた彼女からの電話といった意味ありげな要素が、物語の進行にほとんど作用していないところも残念だった。映画監督の強い思いを現したもののようだが、これらの要素があってもなくてもストーリーには影響がない。そのため、目立つだけの「ノイズ」になってしまっている。人物描写もしっかりしていたが、主要登場人物のキャラクターをより掘り下げた方が、さらに驚きの大きい作品に仕上がったはずだ。小説を組み立てて語る力は十分にあるので、新たな作品に期待したい。
『双卵の女王』憂咲いろは
クローン技術が発達した近未来、あるクローンが、自身の元となった女性の首をしめて殺すという「親殺し事件」が起きた。さらに捜査部一係の係長、英さんが磔にされ殺されるという事件が起こる。そこで長門は警視総監から呼び出され、自身のクローンでありながら性別は異なる女性の陸奥を妹として共同生活をはじめることになった。一方で事件の真相をもとめ捜査を続けていく。
饒舌な語りと脱線の多い会話、めまぐるしい話の勢いによりぐいぐいと読ませる筆力は十分にある。問題は細部のつめだ。その高度なクローン技術がどのように発達し、どのように日本でおこなわれているのか、彼らの人権そのほかはどうなっているか、といった細部があいまいで、都合よく書かれているように感じられた。主人公のキャラは立っているが、それ以外の人物はいささか頭に残りづらく、単なるコマとして描かれているように見える。それを活かすための描きわけやドラマの作り方など、もうすこし考えて欲しい。
『死んだ魚だけが流れに流されてゆく』新木光希
旧植民地の新興国の中には、帝国主義支配時代の宿痾を解消しきれず長い内乱が続いているところが多くありません。その一つが舞台で、実際に起きた痛ましい事件を題材として真摯に向き合った良作でした。誰かが密告したために主人公の一家はジェノサイドに見舞われる。ミステリーとしては肝腎な、その犯人捜し要素が薄いのが残念でした。ここで論理的な謎解きが行われていたら間違いなく二次まで通過です。また、途中で主人公が追い込まれる事態がありますが、ここはもっとスリリングに書いてもらいたかったところです。
『女スパイは服を脱がない』佐々木誠竜
正体不明の女が”整備士たちが爆弾を仕掛けた”と空港で母親を待つ少女に告げ、その直後にプライベートジェットが爆発する――本作はそんな場面で幕を開ける。その後、雑誌記者が女性スパイ組織”百合機関”に欺かれるエピソードを経て、首領である防衛大臣・千歳真白、機関のメンバーである一条椿、新人スパイ・結城茜といった面々の虚々実々のやり取りが描かれていく。
色仕掛けを使わない百合機関の設定は(やや類型的だが)いかにも訴求力を感じさせる。復讐という目的を用意したうえで、変装や入れ替わりを伴う騙し合いを展開する作りも好ましい。しかし閣僚の謀殺や首相就任、国家改革レベルの主張といった事物の扱いが軽く、全篇が絵空事めいた印象を残してしまう。題材やスケールを見極めて再挑戦して欲しい。
『チェルシー・ガールにうってつけ』室荒打馬
1960年代末にカリフォルニア州のワイン・ショップで発生した女子大生殺しの真相を、半世紀を経て東京の病院で明らかにする二部構成の犯罪小説です。60年代半ばの海外渡航自由化により現地派遣となった日本人一家の娘を主人公とした点がプラス・ポイントです。これにより海外を舞台に日本人が殺人事件に巻き込まれる物語にリアリティを与えると同時に、当時アジア人、とりわけ日本人がアメリカ社会でどう見られていたか、逆にベトナム戦争とヒッピー・ムーブメントに揺れるアメリカが他国の目にどう映っていたのかを描き、現在まで続くアメリカ社会の諸問題をテーマとし、迷宮入りした背景に説得力を持たせる試みは大いに評価できます。
一方、60年代の社会を描くのに、登場人物の口から当時の社会現象や風俗、流行を頻繁に列挙させる手法は、やや説明くさい上にストーリーの流れを停滞させてしまうためマイナス・ポイントです。現代パートで過去の未解決事件の謎を解くという二部構成に、なるほどと膝を打つぐらいの説得力があればミステリとしてより高く評価できたと思います。書きたい物語と伝えたい事があることが十分に感じられるので捲土重来を期待します。
『ガウディの罠』小河
中堅ソフトウェアメーカーの依頼を受けて最先端AIを搭載した画期的な統合基幹業務システム「ガウディ」を開発中の天才プログラマーが、納品期限の日に突如詐欺罪で逮捕されてしまう。病に倒れた上司に代わって急遽弁護する羽目に陥った若き女性弁護士に対して容疑を全否定する被疑者。冤罪を確信した彼女は、契約不履行による莫大な違約金支払いを回避すべく奔走する。
二重三重に仕組まれた複雑かつ巧妙な犯罪計画と意外な真相は、ミステリとしてとても魅力的です。文章力・キャラクター造形力ともに水準以上で、読み終わる直前まで一次通過と思っていましたが、最後の最後に明かされる真相で大きく評価が下がってしまいました。複雑な犯罪計画を成立させるための核となる状況を犯人が設定することは限りなく困難であるにも関わらず、十分な説明がなされていないのは致命的です。この一点さえ説得力を持って書かれていればと残念に思います。軽妙な犯罪小説を書く力があると思いますので次回作に期待します。
『裁判所の亡霊』渋川紀秀
良心を失ってしまった裁判官が殺害されるという事件が描かれます。その設定から、裁判官にとっての良心とは、という問いに関心が集中するのは当然だとは思いますが、あまりにもそのために人間関係などを作り込みすぎており、不自然になってしまっているのが気になります。作者の都合のいいように物語をデザインする癖がついてしまっていないでしょうか。迫力のある文章を書かれる方なので他所なら間違いなく一次通過していたと思いますが、この作為感は本賞の選考では命取りとなります。やむなく今回は見送りました。
『ローズキラーの挽歌』高栖匡躬
殺人事件発生の緊急連絡で起こされた刑事が、上着のポケットに見知らぬ女性の運転免許が入っていることに気づく。不審に思いながら現場に着いた彼が目にした被害者は、運転免許の女性だった……という序盤の展開で心をつかんでくれた作品。
自分は二重人格ではないかと脅える刑事が捜査を続ける、という状況は魅力に富んでいる。捜査の過程も丁寧に描いている。ただ、主人公が捜査と並行して精神科医の診察を受ける部分が気になった。捜査の様子を手堅く描いている一方で、精神科医のパートは粒度が粗くなっているように感じられる。医師の正体に関わるエピソードも現実離れしていて、堅実な捜査の部分と並べるとリアリティのレベルが合っていないように感じた。また、ラストに描かれる同僚の女性刑事との結婚も、そこまでの物語では彼女と接点があまりないので、ずいぶん唐突に感じられる。また、「もし主人公が二重人格でないとしたら」と考えると、犯人の正体がすぐに見当がついてしまうのも弱点。ミステリーとして魅力のある状況を描く力はあるので、新たな作品に期待したい。
『モナコでの盗み』海江田信夜
伝説のサファイア“天使の涙”を盗むためにモナコ公国に潜入した怪盗が、いずれも腹に一物ある大富豪や記者、警察官らと虚々実々の駆け引きをしつつ宝を奪取すべく奔走するゲーム色の強い犯罪小説です。
くだんの宝石を巡って百年前に起きた不可解な消失と殺人の謎解きと現在の犯行計画を同時に書く手際は一次通過の水準に達しています。ただし、人物造形があまりにも類型的な点と、登場人物全員が老若男女にかかわらず高校生のような言葉遣いで話すため人間として薄っぺらく感じられる上に区別がつかない点、無駄な会話が散見される点は大きなマイナス・ポイントです。意外性のあるミステリを構築するセンスは、十分に感じられるので次回作に期待します。
『怪人裁判』双村ミト
人間に支配された怪人がスラムに隔離されている日本。息子が人間の子供を傷つけた責任を取るために、怪人モルグは決闘裁判に臨むことになった。怪獣対策特務班(通称”戦隊”)の五人と戦い、生き残れば無罪になるという制度だ。モルグは戦隊の一人を殺して無罪を勝ち取るが、その隊員が毒を盛られていたことが判明し、謀殺の疑いで起訴されてしまう。事務所を畳もうとしていた弁護士・真締は報酬に釣られてモルグの弁護を引き受け、怪人たちの苦しい生活を知り、人間の傲慢さを痛感していく。
トカゲの顔を持つ怪人、五色の戦隊といった特撮風のアイテムを使い、特殊な裁判の顛末を描く異世界ミステリーである。理不尽な決闘裁判に既視感はあるが、状況説明から真締が使命感を抱くまでの導入は滑らかで、奇抜なシチュエーションと合理的な動機を両立させたプロットは評価に値する。その反面、明快さを重視したにせよ、特撮ベースの借景があまりにもベタに過ぎ、終盤の計画が御都合主義的であることは否めない。発想と前半の筋運びが良いだけに、オリジナルの設定を作り込んだ力作を望みたい。
『業務上過失』古林和典
拘束中の青年が取調室から逃亡する事件が起こった。彼は精神薄弱を患っており、その逃亡も自覚して行ったわけではないようだった。ところが、この日、近くの川で遊泳中の小学生二人が流されるという事故が発生していた。偶然にも現場に居合わせたその青年は、ひとりを助けたのち流されたもう一人を追って濁流に飛びこんでいった。事件が報道されるや、国民は青年の安否を心配し、注視するようになった。ところが行方不明のまま三ヶ月が経過したのち、「青年を誘拐した」という書簡が警察に届く。それは前代未聞の脅迫状だった……。
すでに起きた過去のできごとを最初からすべて明らかにせず、まずおおまかに匂わせてながらだんだんとその詳しい情報を読者へ与えていく展開はそれだけでサスペンスを生み、面白い。だが中盤でその流れが分かってくると、結局は語りの順番をひっくり返したことで生まれた逆算型プロットであり、青年の事件は、犯人の真意のために用意された、都合のいい設定に思えてしまった。なにより現在、発達障害とされる人物、もしくは警察や国家に対する挑戦的行為とその対応の描き方など、エンターテインメント小説として成立させるにはかなり注意を払う必要があるだろう。その点も含め、テーマやプロットが先走っているのではないか。もともと事件とは無関係の第三者の目を通して描くなど、それを活かして読ませる手法はあるはずだ。
『蕃神』我妻大輔
古代の有名な出来事を殺人事件に見立てて、実在の人物が謎を解くという形式の物語です。その着想に感心し一時は予選通過も考えたのですが、読み直してみるとミステリーとしてはワンアイデアで押し通してしまっているのが弱い。いくら古代で科学捜査がないと言っても真相へつながる手がかりの配置など補強材は必要ですし、真犯人もこれしかないという一本道になってしまっています。また、諷刺要素を盛り込んだ趣向もおもしろくはあるのですが少し欲張りすぎで、それならミステリー部分を頑張ってもらいたいと思いました。
『ライジング』長瀬遼
昭和二十一年の東京を舞台に、戦災孤児たちが活躍する少年少女冒険活劇である。三人の男の子たちを中心とする活劇は、新橋の地下に侵入するなど、十分な筆力でテンポよく読ませてくれる。素直に愉しめる小説に仕上がっているのだ。
だが、新人賞の応募作として読むと、弱みがある。結末に至るまでの仕掛けに新鮮味がないのだ。意外な人物の登場や、ある人物の裏切りなどが配置されてはいるものの、過去に読んだことのあるパターンなのである。“ミステリー”を冠する賞だけに、新鮮な驚きに欠けると弱みとなってしまう。
過去の応募作では、一次選考通過時に「展開そのものに仕掛けがあり、なるべく予備知識なしに読んでほしいタイプの小説」との高評価を得た書き手でもあるだけに、その特徴を今回も活かしてほしかった。