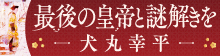第22回『このミス』大賞 1次通過作品 箱庭の小さき賢人たち
学内限定のポイントは、学食でも使えるし単位すら買うことが出来る――
そんな商科大学で、学生たちが経済バトルを繰り広げる!
『箱庭の小さき賢人たち』海底明
ビジネスセンスを備えた人材を育成しようと設立された商科大学を舞台とする一篇。その大学には、学内でのみ通用するポイントがあった。そのポイントは、学食でも使えれば、家賃に充当することもできる。それどころか、授業の単位さえ購入することさえ可能だった(同様に、取得した単位を売却してポイントを得ることも可能だ)。そうした大学において、サークルとは、共通の趣味のために存在するのではなく、事業を行うために存在していた。そう、特定の事業目的で設立され、その事業に必要な人材を集め(部員だ)、事業を行い、そしてポイントを稼ぐのである。サービス業を営む者もいれば、アプリを開発する者もいる。実態はガールズバーという家庭教師サークルもある。主人公である降町歩は、その大学の二年生。彼は、家庭の事情で、この先の四ヶ月で三百万ポイントから四百万ポイント程度稼がねばならないことになった。それが達成できなければ、大学を辞めるしかない。降町は、先輩のアドバイスを得ながら、ポイント稼ぎに知恵を絞る……。
ミステリとして、なかなかカテゴリを特定しにくい小説である。強いていえばコンゲームか。知恵を絞って作戦を立て、遂行し、予想外の事態にも臨機応変に対応し、そして結果を得ていく。そこに新鮮なスリルがあるのだ。その物語のなかに著者は、伏線とその回収も織り込んでおり、しっかりと愉しませてくれる。さらに、対立する勢力間の攻防という要素も仕込まれている。もちろん、経済小説的な魅力もある。事業計画そのものの独創性(例えばタイムマシンに関するビジネスなんてものさえ存在している)であったり、監査を乗り切るための工夫であったり、愉しませてくれるポイントが多々ちりばめられているのだ。人物造形や文章も一定以上のクオリティで、安心して読み進むことができる。
読後感は、“きれい”のひとことに集約される。人間関係の決着もきれいだし、難題の処理もきれいだ。
典型的なミステリでは決してないが、ミステリセンスがしっかりと伝わってくる小説であり、二次に推す。
(村上貴史)