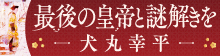第21回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
三つ巴の熾烈な戦いを勝ち抜いたのは……
第21回『このミステリーがすごい!』大賞の最終選考に残ったのは、昨年に続いて8作品。長編の新人賞で最終に8本も残るのは珍しい。書評家が選考委員をつとめる賞ならではかも。
その最終選考では選考委員3人の推す作品がバラバラで、大賞候補3作が三すくみの状態に陥り、選考が膠着。ひさしぶりに長期戦となりかけたが、つかみ合いの大喧嘩に突入する前になんとか決着した。
大森が大賞に推したのは、美原さつき『イックンジュッキの森』。主人公は霊長類学を専攻する大学院生・父堂季華。彼女が所属する研究室に、米国の大手建設企業から環境アセスメントの依頼が舞い込む。コンゴで計画している開発事業が現地に生息するボノボに影響を与えないかどうか調査してほしいという。季華は指導教官や先輩たちとともに調査隊に加わって現地へ赴く。だがそこには、”ライオンイーター”と呼ばれる狂暴な未知の生物が跳梁していた……。
かくして、高野和明『ジェノサイド』のアフリカ・パートを思わせる冒険小説の幕が上がる。惨殺されたヒョウの死体。ジャングルに潜む凶暴な何かの気配。はたしてライオンイーター(イックンジュッキ)の正体とは?
野心的なテーマに挑む大型エンターテインメントで、ストーリーテリングも上々。ヒロインの奇矯な性格(およびその原因となった事件)の設定には大いに問題があるものの、そこは改稿すればいいだけの話。致命的な欠陥にはならない――と思っていたのだが、いまどきのエンターテインメントとしてこの女性観はどうなのか、そもそも世間の空気を感じとれていないのでは……という強い反対意見が出て、最後は根負け。『イックンジュッキの森』は文庫グランプリという結果に落ち着いた。
もう1作の文庫グランプリ受賞作、くわがきあゆ『レモンと手』は、手堅くまとまったダーク・サスペンス。大きなマイナス点はないものの、良くも悪くも優等生的で、際立った特徴が見当たらない。虐げられる側から虐げる側への逆転劇は面白いが、そこまでの展開に(どんでん返しも含めて)既視感がありすぎる。著者は昨年べつの公募新人賞を受賞し、すでに2冊の著書を商業出版している人。それだけに、『レモンと手』もじゅうぶん出版レベルには達しているが、だからといって『このミステリーがすごい!』大賞に選びたい作品かというと、個人的には首を傾げざるをえない。
というわけで、三つ巴の熾烈な戦いを勝ち抜いたのは、小西マサテル『物語は紫煙の彼方に』。こちらは鮎川哲也賞の最終候補に残った作品を大幅に改稿したもの。レビー小体型認知症を患う老人が安楽椅子探偵をつとめる〝日常の謎〟系の本格ミステリー連作で、いかにも創元っぽい。冒頭、瀬戸川猛資『夜明けの睡魔』にまつわる謎が浮上し、往年のワセダミステリクラブについて語られるあたりは中高年ミステリ読者の郷愁を誘うものの、『このミス』大賞読者の多くに共有されるかどうかははなはだ疑問。連作を締めくくるラストはきれいに決まっているし、全体の語り口も悪くないが、残念ながらトリックがあまりぱっとしない(し、現実的に無理があるものも含まれる)ので、ミステリー的な驚きに欠ける。鮎川賞落選作を大幅に改稿してこれだとすると、果たしてのびしろに期待できるのか。だいいち、どう見ても鮎川賞向けにチューンナップされた作品で、およそ『このミス』大賞らしくない。
……と思ったが、まあね、そこに意外性があると言えなくもない。『レモンと手』か『物語は紫煙の彼方に』かで悩んだ挙げ句、『物語は紫煙の彼方に』の大賞受賞に賛同した。3作とも、小説としては大賞のハードルをクリアしているので、あとは趣味の問題というか、どの要素を重視して選ぶかの差にすぎない。いずれ書店の店頭に並んだ暁には、めでたく大賞を受賞した『物語は紫煙の彼方に』と、文庫グランプリに輝いた2作をぜひ読み比べていただきたい。
他の5作は早々に大賞レースから脱落したが、最終選考会でいちばん話が盛り上がったのはおぎぬまX『爆ぜる怪人』だった。東京都町田市のご当地ヒーロー「マチダーマン」を擁する特撮プロダクションの話で、ヒーローショーの内幕がたいへん面白く描かれている。昭和の映画界の体質をそのまま残したパワハラ当たり前のブラック企業の日常がディテール豊かに活写され、大賞受賞作はこれで決まり! と、途中までは思っていた。しかし、殺人事件が起こり、その謎と解明に物語の軸足が映ると、小説は急速に魅力を失っていく。事件の真相は、それまでのコミカルなトーンとは裏腹にたいへん陰惨なもので、途中から出てくる探偵役のキャラにもあまり魅力がない。児童誘拐殺害事件とからめてミステリー的な核をつくりたい気持ちはわかるが、小説の内容とあまりにもミスマッチ。せっかくの(ひどすぎて笑える)マチダーマン・ワールドが台なしにされてしまった感じで、なんとももったいない。とはいえ、「マチダーマン」には大いに可能性があると思うので、改稿を経て出版されることを祈りたい。
竹鶴銀『龍の卵(ドラゴン・エッグ)』は台湾をめぐるマンガ的なB級国際謀略小説として楽しく読んだが、昨今の台湾情勢がシリアスすぎて、こんなお気楽なエンターテインメントを素直に楽しむのはむずかしいという声があり、なるほどと納得した。作中では、現実にはありえないウルトラCで台湾独立が達成されるが、そういうファンタジーがエンタメ小説として成立しにくい状況になっている。
中村駿季『天の鏡』は、他人のトラブルに首を突っ込んでひたすら謝罪する主人公を軸にしたオフビートなコメディ。顧客を満足させるため、時間をかけて専用に準備した設定を使って顧客の前で即興劇を演じ、高額の報酬を受けとるというビジネスはなかなかユニークだが、後半は主人公の「謝罪の王様」設定がほとんど生かされない。主人公の過去が舞台上で明らかになる半ば文学的なラストの仕掛けも、『このミス』大賞的にはちょっとむずかしいかも。
三日市零『ゴールデンアップル』は、「合法復讐屋」を営む元弁護士エリスのキャラがちょっと面白い。復讐の手順もよく考えられているが、だんだん復讐から遠ざかり、小説の焦点がぼやけていく。
鹿乃縫人『夜明けと吐き気』は、若々しい本格ミステリー。世界観やキャラクターには見どころもあるが、肝心の密室トリックに(第一段階も第二段階も)説得力がなさすぎた。現実に実行不可能なトリックを作中で使ってもいいが、およそありえないようなトリックを探偵役が提示したときにはそれなりのツッコミが必要だろう。突拍子もない冴えたトリックと、それを成立させる手続きをじっくり考えてから再挑戦してほしい。
香山ニ三郎
マニア心をそそられる趣向と古典作品へのオマージュ
最終候補作は今年も八本。読んだ順から取り上げていくと、まず竹鶴銀『龍の卵(ドラゴン・エッグ)』は台湾有事をテーマにした国際謀略スリラー。東日本大震災で死んだはずの友人の姿を追って総統選真っ只中の台湾に渡った日本人カメラマンが候補者爆殺事件に遭遇、彼はそこで出会った謎の女に拉致される。その主人公の運命を軸に、ウイグル内乱、中国北部戦区のクーデター等、多角的視点から中国の今そこにある動乱を活写していくが、読みやすい文章といい、大スケールの話を手際よくまとめ上げた手腕といい、すでにプロ級というべきか。惜しむらくは主要人物の魅力不足、事と次第では現実が小説を超える事態となる可能性もあり、簡単には評価しにくい一面もあって、採点はB。
小西マサテル『物語は紫煙の彼方に』はミステリーマニアの女教師とレビー小体型認知症の祖父の絆を軸にした日常の謎系連作集。ヒロインが購入した本に挟み込まれた栞の謎をめぐる第一話からマニア心をそそられる趣向が凝らされており、古典作品へのオマージュも好印象。認知症の祖父は安楽椅子探偵というか、ディーヴァーのリンカーン・ライムのヴァリエーションのようだ。脇役の善人キャラといい、鮎川哲也賞作品を髣髴させるとも思わせられたが、実際同賞の最終候補作を加筆訂正したものだと知ってびっくり。本賞はそういうのもありなので無問題として、採点はA。
次のおぎぬまX『爆ぜる怪人』は東京・町田のご当地ヒーローの運営会社で働く青年が主人公。そこで、かつて彼がデザインしてお蔵入りになったヒーローが誘拐犯を退治するという事件発生。彼は仕事の傍らその謎を追い始める。ミステリーとしては過去の誘拐殺人も絡んでくるところがポイントだが、読みどころはやはりご当地ヒーローの会社の個性豊かな人間模様か。あたかもテレ東の深夜ドラマのごとし。ちょっとマニアックに傾き過ぎて採点はCだが、隠し玉候補には最適かも。鹿乃縫人『夜明けと吐き気』は連続猟奇殺人を追う警視庁刑事の話かと思いきや、そこにカルトな団体に勧誘された多重人格探偵の調査行と猟奇殺人、カルト団体双方に関わる不運な男の動向が絡んで話が進んでいく。先を読ませない展開というと聞こえはいいが、頭でっかちな語りが先行して読者が置き去りにされている感あり。もっとも、筆者は書き手のプロフィールを抜きで作品を読んだので、この作者が一六歳だというのを後々知って驚愕。一六歳でこれだけ書ければ天才級、今回はCだけど、もう少し肩の力を抜いて、今後も本賞にリトライしていただきたい。
美原さつき『イックンジュッキの森』は、アフリカの鉱物採掘道路建設に必要な環境調査を依頼された日本の大学の科学者チームがコンゴの奥地に赴き、そこで未知の霊長類に出くわす。こりゃもうマイクル・クライトン直系の秘境冒険小説ということで、一気に読まされた。コンゴの描写もヴィヴィッドで採点はもちろんAだが、一つネックがあり、それはチームの女性隊員・父堂季華が男友達の暴力で右目を失い、それを契機に男狂い(!?)になったという設定。いくら彼らが足を踏み入れるのが暴力を厭うボノボの生息地とはいえ、これはやはり走り過ぎではないか。案の定、選考会では瀧井さんから痛烈な反対意見が出され、そこは手を加える形で何とか文庫グランプリということで落ち着いた。
中村駿季『天の鏡』は自分に関わりのないトラブルに首を突っ込んでは謝るという青年が元SМ女王に拾われ彼女の仕事を手伝い始める一方、ひょんなことからヤクザと関わり出世の道を歩みだす。一風変わったテイストのサイコミステリーだが、良くも悪くもいかにも浮世離れした演出は今一つ手ごたえを感じられず、採点はC。三日市零『ゴールデンアップル』はオネエの元弁護士が調査会社の裏メニューで営む合法復讐屋の仕事を描いた連作集。主人公が変幻自在の活躍を見せる全四話は後の作品ほど手が込んでいるが、小学生の秘書といい、ちょっとテレビドラマ的な演出や造形がいかにも軽い印象で、こちらも採点はCだ。
残るくわがきあゆ『レモンと手』は大学職員のヒロインが妹を殺されたあげく、その妹に保険金殺人犯疑惑もかけられ、彼女の潔白を信じる男子学生とともに晴らそうとする。これまたよくあるテレビドラマ的な話のようだが、さらに長年音信不通だった母も殺され、どうやら一〇年前に父親が殺された事件が絡んでいるらしいことがわかってくるにつれ、俄然面白くなってくる。一見単純に見えた事件は実は入り組んでおり、前半丹念に織り込まれた伏線が後半次々に炸裂するのである。
最終選考会では『物語は紫煙の彼方に』と『イックンジュッキの森』、『レモンと手』の三つ巴の争いとなったが、『レモンと手』は大森さんからよくあるクライムサスペンスだと反対意見が出、ミステリー趣向に突っ込みどころがないわけではないが、とくに強い反対意見の出なかった『物語は紫煙の彼方に』に大賞が贈られることに(『レモンと手』は文庫グランプリ!)。ちなみに受賞作のヒロインの祖父は筆者と同じワセミスOBということであるが、だからといって、身びいきはしておりませんので。
瀧井朝世
魅力的な物語を書き続けていける方だと確信した
今年も最終選考に残ったのが八作品と多め。上位作品はすんなりと決まりましたが、どれを大賞に選ぶかで意見が分かれたものの、納得のいく結果となりました(私は)。
激論の末大賞に決まったのは連作ミステリ短篇集『物語は紫煙の彼方に』。これはキャラクターが非常に魅力的。特に、主人公の女性に関わる、青年二人それぞれの不器用さがなんとも可愛く、彼らの会話がとっても楽しい! ミステリー部分に関してはやや弱く、他の方も指摘しているように居酒屋の密室の真相などは不自然。安楽椅子探偵役の祖父が、彼しか知らない情報をもとに推理する話についてもミステリーとしてアンフェアに感じましたが、これは許容範囲内か。それらを考慮してもなお、全体を通しての空気感、安定感が秀逸でした。最終話の盛り上げ方もよかった。魅力的な物語を書き続けていける方だと確信しました。タイトルはちょっと古臭いので改題を希望します。
『レモンと手』は群を抜いて文章が上手かった。ちゃんとストーリーにマッチした文体が選ばれていて素晴らしい――と思ったらすでにデビューされている方なのですね。後半の、やりすぎじゃないかというくらいの二転三転四転五転の展開にねじ伏せられました。それが行き当たりばったりのどんでん返しではなく、前半から周到に準備してあるところが私の中では高ポイント。登場人物それぞれの、ちょっと歪んだキャラクターも面白かった。途中までは「『このミス』大賞に選ぶならもうちょっとエンタメ的痛快さがほしいな」と思っていたのですが、最後の最後がめっちゃ痛快! 文庫グランプリおめでとうございます。
『イックンジュッキの森』はアフリカの奥地が舞台の異色作。ミステリーというより冒険エンタメとして読みました。ただ、多くの読者にとって未知の場所なのですから、もう少し情景描写などを書き込んで臨場感を持たせてほしい。また、主人公の女性のキャラクターについては改変の必要があると思います。本筋とまったく関係ないのに(←ここ重要)、物語の彩りのために性被害とそのトラウマを軽々しく、ユーモラスな要素として取り入れることに疑問を持ちます。そんな要素がなくても充分引き込ませる話なのに……。私はその点の改変を条件に入選を了承しました。
『爆ぜる怪人』はご当地ヒーローとその運営会社という題材がユニーク。話運びも上手く、登場人物の大半のキャラクターもよく描かれている。ただ、謎解きの過程や真相に無理があると思いました。ラストも別にこのままでもいいのですが、欲をいえば、もうちょっとだけ、説得力&納得感&スッキリ感のあるものにしてほしかった。これは改稿可能なはず。気軽に楽しく読めるので「隠し玉」によいのでは。
『龍の卵(ドラゴン・エッグ)』も非常に読み応えのある作品でした。文章も上手く、複雑な状況の説明も過不足なく読みやすい。手に汗握って読みましたが、だからこそ、途中から、ここまでの壮大な試みを実行する人にしては詰めが甘いのではないか、と感じる箇所も。また、国家間の戦争(殺し合い)を避けて平和的解決を達成するところに心動かされたので、終盤で明かされる過去の殺人と、最後のふたつの復讐のための殺人は蛇足だと感じました。
『天の鏡』は、「謝罪癖」という主人公の最大の特徴が、出来事の発端になるだけでその後はあまり活かされていないのが惜しかった。彼が関わる、クライアントの不満やストレスを芝居で解消する仕事については、「これでストレス解消するのか?」「大金払ってまで頼みたいか?」という疑問が拭えず。最終的に主人公も衆人環視のなか無理やり苦い過去を芝居で再現させられることになりますが、これ、逆にさらなるトラウマにならないのでしょうか。人間の謝罪に対する心情、トラウマを乗り越える心理過程について、納得できる要素があると一段と面白くなったかも。
『ゴールデンアップル』は合法的な復讐屋という設定は興味をそそりましたが、読み進めるほどに新鮮味が失せていった印象です。最初のエピソードで主人公の用意周到さに感心したのに、他の話ではそうした特性が発揮されることもあまりなく、主人公としての魅力と個性が希薄なのが残念。また、あまりうるさいことは言いたくないですしそれが大幅なマイナス点になったわけではないですが、いくら本人が言い出したからといっても、小学生の少女(主人公の助手ではありますが)が、小児わいせつの証拠をつかむために潜入調査する展開は読んでいて愉快ではないです。
『夜明けと吐き気』は練りに練ったサスペンス。構成力はありますが、細部に疑問点が多かった。どの登場人物のパートも思弁的、観念的で、やや肩ひじ張りすぎな印象を持ちますし、それだけでなく、それぞれの思考や主張、言葉選びが強引で大仰、青臭く感じる箇所が多いな、というのが正直な感想です。読了後に著者の年齢を知り、十六歳でここまで書けるなんてと驚きましたが、もしもっと大人の年齢だったら最終選考に残っただろうかという疑問も持ちました。伸びしろがあると信じて、今後の作品に期待します。