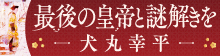第12回『このミス』大賞 2次選考結果 茶木則雄氏コメント
喜ばしい傾向
今回の一次通過作品21本は、バラエティに富み、総じて読み応えがあった。ミステリー的興趣に欠けるスペキュレイティブ・フィクション(SF・ホラー・ファンタジー系列)やキャラに頼る薄味の“日常の謎”タイプ、必然性なく海外を舞台にした自己陶酔型の翻訳調小説、あるいは上辺だけを真似た伊坂チルドレンや春樹エピゴーネンが、大幅に減ったためだろう。個人的には、喜ばしい傾向だと思う。
替わって目に付いたのが、いわゆる“右傾エンタメ”だ。断っておくが私自身、この呼称に与するものではない。左端に立つから右寄りに見えるだけで、「日本人の誇りを失うな」というメッセージは、どこの国に置き換えてもごくごくまっとうな、ど真ん中の主張だと思っている。本来は“中道エンタメ”と呼びたいくらいだ。最終に残った『勇者たちの挽歌』と『僕が9歳で革命家になった理由』の根底を支えるのは、「生まれた国を愛する」という当たり前のテーマである。なお、二次突破作品の評価については例年どおり、最終選評で触れるつもりだ。
もうひとつ目を惹いたのは、在日や韓国といったデリケートな問題に対するタブーへの挑戦だ。『沈黙の死闘』に見られる在特会(「在日特権を許さない市民の会」の略称)への言及や、二次を突破した『真相を暴くための面倒な手続き』の日韓併合に関するニュートラルな文言は、一昔前の応募作では目にすることはなかった。二作とも、親韓とか嫌韓ではなく、プロットと有機的に結びつくひとつの題材として、臆することなく採り上げている。これも歴史の真実を見つめ直そうとする時代の空気と、無関係ではないのだろう。
『沈黙の死闘』は、病院に立てこもった麻薬密売グループが在日を名乗り、反日的要求を政府に突きつけることで、左翼マスコミや人権派弁護士を扇動して朝鮮半島の反日世論を喚起し、英雄として韓国への亡命を企てる、という筋立てだ。昨今の韓国の、苛烈さを増すばかりの凄まじい反日行動の前には、有り得る事態として首肯する読者は少なくないだろう。惜しむらくは、リンカーン・ライムばりの全身麻痺に陥る主人公刑事のキャラクターだ。造形が浅く、鋳型に嵌め込まれた量産タイプの劣化版・堂場瞬一臭がする。アイデアはいいのだけれど、脚本で言うところの「コロガリ」が良過ぎる展開で、物語に深みとコクがないのが、最大の弱点か。
アイデアと言えば今回、これも喜ばしい傾向であるが優れた作品が少なくなかった。筆頭は『ロストナンバー』だ。たった一枚の紙幣を廻り、日本に非常事態宣言が発せられる――この着想は抜群に面白い。が、リアルな物語として構築していくためのプロットが、如何せん脆弱だ。三億円の謝礼がかかった、ある紙幣番号の一万円札を求めて市民が全国のATMに殺到し、非常事態の端緒となる。しかし冷静に考えれば銀行は、パニックを回避するためすぐさま手持ちの紙幣を確認するはずだ。警察関連の描写にリアリティが欠けているのも、落選の大きな要因だろう。警察組織を登場させる以上、関連描写のリアリティは筆力同様に、作品の死命を制するバロメータになる。ここがいい加減だとまず、最終には残れない、と申し上げておく。
同様のことは『俺たちはヒーローじゃない』にも当て嵌まる。刑事と容疑者が手錠で繋がれたまま、事件の真相を追いかける――というアイデアは、ラストも含めてアメリカ映画の翻案っぽいが、それなりに面白い。だが、刑事が捜査本部に応援も求めず、容疑者を留置することもせず、そのまま珍道中を繰り広げるという設定には、いくら何でも無理がある。このシチュエーションに現実感を持たせるためプロット作りに腐心するのが、本来の小説作法だろう。それと、この作者には以前にも指摘したつもりだが、警察関連の描写が相変わらずいい加減。関連資料なり上質の警察小説を、もっと読み込んでください。
警察関連のディテールで萎えた作品がもうひとつある。『流星雨』だ。勾留と拘留を混同するのは有りがちだけど、留置と勾留、起訴と送検の違いくらいは弁えて欲しい。あと、記者クラブに所属しないフリーの記者が警察会見に参加することはできないし、警視監がやくざのフロント企業に再就職することは有り得ない(警察官僚の天下りリストを一度ネットで見てください)。それなりに調べた跡は窺えるのだけど、上辺の知識だけで書いては、警察小説ブームで目の肥えた読者は騙せないと思う。
近未来警察小説の『飛州DMZ』と『maman~殺戮の天使~』はある意味対照的な作品だった。前者のガジェットは現実世界の延長線上にあり、納得できるものも少なくない。大阪都構想が実現した大阪都を舞台に、警察関連描写にもさほど違和感はなかった。ただ、地の文はそれなりなのに、台詞がいまいち(推敲の際、音読をお奨めする)。事件の全体像にも目新しさはなく、近未来にこだわる必然性を感じられなかった。一方、後者は、ガジェットに工夫を感じられず、警察描写もいい加減だが、近未来である必然性はなきにしもあらず、だ。が、いずれにせよ近未来物は、よほど斬新な作品でもないかぎり最終に残れない。それが二次選考会の一致した意見だ。
同様に時代小説もまた、ハードルは高い。『無明長夜』は筆力もあり、極めて端正な作品だが、オリジナリティを感じられなかった。エピソードはそれなりなのだが、凡庸な物語展開でリーダビリティに欠ける。ページを繰る手に力がこもらないのだ。非常に丁寧な筆遣いの、「写経」を読まされた気分である。「物語」と「ドラマ」について、もう一度、突き詰めて勉強してみてはどうか。昭和の名劇作家・笠原和夫の「シナリオ骨法十箇条」(新潮社『映画はやくざなり』収録)をお奨めする。
『萌えないゴミはただのゴミだ。』と『血の氷像』は、共にゴミにこだわった作品だが、テイストは正反対。タイトルどおり前者はライトなタッチ、後者は重苦しい筆致だ。が、両者とも、二次を突破できるレベルになかった。物語を創るとはどういうことか、過不足ないエピソードとは何か――を、いま一度じっくり考察していただきたい。
『水底の解』と『水彩プラネタリウム』は、申し訳ないが私にはさっぱりだった。特に後者は前回の応募作よりガクンと落ちるだけに、失望感が強い。『タスマニアデビルの憂鬱』はそれなりに読ませる作品だが、ミステリーの書き方が分かっていない。視点の人物が知り得た真相を読者に隠し、その人物の視点で謎を引っ張るのはどうか。どうせ視点を変えるのだから、重要な情報を入手した直後に変えるのが、フェアな書き方だと思うが。
タイトルの衝撃度で言えば今回一番の『金玉さん』だが、これはさすがにカテゴリー・エラーだろう。いくら広義といえどもミステリーの範疇に収めることは難しい。艶笑譚として面白くは読めたけれど。
最後になったが、A評価をつけながら最終に残せなかった『ティーン・エイジ・エイリアン・サマー』にエールを贈りたい。若さ迸る鮮烈な語り口は、特筆に価する。導入部はいささか冗長だが、平成の少年少女版『OUT』といった趣で、ジャック・ケッチャムを彷彿とさせる凄絶さが忘れ難い。他の選考委員の賛同は得られなかったが、いずれ世に出るべき才能だと、強く感じた。是非とも、捲土重来を期して欲しい。
さて、今年の最終候補は七作。揉めに揉め、『このミス』大賞選考会の最長審議時間記録が更新されるのか、されないのか――。
蓋を開けるまで、まったく予断を許さない。いずれにせよ、今回の二次選考会同様、最後は全員納得の、喜ばしい結果を残したいものだ。