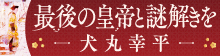第12回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
甲乙つけがたいユニークな警察小説2作がW受賞
第12回『このミステリーがすごい!』大賞の最終候補にコマを進めたのは全7編。二次選考は大モメにモメたそうですが、勝ち残った7編を読んでみると、その理由も推測がつく。実際、そのうち4、5編は、どれが大賞をとってもおかしくないレベル。裏を返せば、「今回はこれで決まり!」という突出した作品がない。選ぶ方としては、こういうときがいちばん困るわけですが、大森が最終的に絞り込んだ2編は、梶永正史『真相を暴くための面倒な手続き』と八木未『ボクが9歳で革命家になった理由』。
前者は、すぐにでも映像化されそうな(エンターテインメントとしての)もてなしのよさがポイント。東京・渋谷の西武百貨店B館に入っている銀行で立てこもり事案が発生。犯人からの指名で、畑違いの捜査二課に属する女性警部補(“電卓女”と渾名される)郷間彩香が現場指揮官に起用される――という発端からして、舞台設定もキャラクター設定もすばらしい。お約束の展開も、それなりにきれいに決まっている。欠点は、立てこもり犯の最終目的が明かされたときのガッカリ感。なんかこう、もうちょっとやりようはないもんですかねえ。
後者は、「誘拐事件発生。身代金は991兆円!」という直球のインパクトがすべて。社会派といえばこれほどストレートな社会派もないだろう。メインアイデアだけでお客が呼べる点は、高く評価できる。問題は、この一発ネタを支えるべき犯人側の主張が、あまりにもあたりまえすぎること。日本中が知恵を絞っている問題に独創的な解決を求めるのはないものねだりだとしても、誘拐ものと組み合わせるのであれば、なにかもうひとつ新しいひねりがほしかった。
以上、ともに一長一短あって、甲乙つけがたい。片方が大賞でもう片方が優秀賞、どっちがどっちになるかは出たとこ勝負。なんならジャンケンかサイコロで決めればいいじゃないの――という無責任な目算のもと選考会に臨んだところ、前者を推すカヤマー委員と後者を推すチャッキー委員がともに一歩も譲らず、ユニークな警察小説2作が大賞を分け合うことに。欠点がうまく修正されれば、どっちも話題を集めそう。勝負の決着は、書店の店頭で手にとるお客さんにつけていただきたい。
第8回以来、ひさびさに大賞が2作になったので、じゃあ優秀賞はなくてもいいよね――ということで、第3回以来10年ぶりに優秀賞は「該当作なし」となりました。まあ、この賞のつねとして、選に漏れても「隠し玉」の可能性が残っているので、「あれが読みたかったのに!」という人は気長にお待ちください。
さて、残る5編について、簡単にコメントする。
村上暢『ホテル・カリフォルニア』は、砂漠に建つ超豪華ホテルを舞台に展開する、物理トリック(『斜め屋敷の犯罪』風)満載の本格ミステリ。数多ある欠点は、探偵役が若き日の御手洗潔(アメリカでジャズ・ミュージシャンをしてるころ)で、著者が島田荘司だったららすべて解決される――というか、島田ファンは大喜びして読むんじゃないかと思いますが、この賞から出る新人のデビュー作としてはちょっと厳しいか。
志門凛ト『幸せの戦略』は、“半沢直樹以後”を先取りしたかのような企業コンサルティング・サスペンス。前半の企業小説パートが非常に面白く、コンビを組む女性上司のキャラもユニーク。ただし後半、登場人物たちの過去の因縁を探る昭和ミステリ的な方向に流れるのが惜しい。企業ドラマに徹した方がよかったのでは。
越谷友華『生き霊』は、いかにも乱歩賞っぽい警察ミステリ。小児殺害事件の現場から発見された精液のDNAが、16年前に起きた同様の事件の犯人と一致。だが犯人は今も刑務所の中にいる。いったい何が起きているか?
――って、生き霊とか持ち出すまでもなく、ふつうに考えると、服役中の犯人の精液が外部に持ち出されたか、一卵性双生児の犯行か、二つに一つでしょ。最初に考慮すべきその可能性が捜査陣に検討されない時点でどうなのかと。あと、文章は全面的に改稿が必要。ほとんど1行ごとに日本語のおかしい箇所があります。
小池康弘『勇者たちの挽歌』、女子マラソンのメダリストがマクガフィンを背負って追われる身に――という設定はすばらしい。ほとんど戦争ものかというくらいに武器が多用されるアクションシーンも最高の迫力。和製グリーニー登場か……と思うくらいだが、事件の真相とマクガフィンの中身がダメすぎる。いいところと悪いところがこれだけはっきりしている小説もめずらしい。活劇だけなら文句なしに大賞なのに……。惜しい!
影山匙『正邪の獄』は、幼なじみ4人組が再会したら、2人は刑事に、2人は泥棒になっていた――というありえない偶然から始まるサスペンス。コミカルで軽快な(たとえば伊坂幸太郎的な)タッチで書かれていれば、その後の意外すぎる展開も含めて気持ちよく読み進めただろうが、これまた文章がまずく、一文ごとに粗が目立つ。語られる内容と語り口のミスマッチが小説世界全体を壊している。
とまあ、今年もバラエティ豊かな作品がそろって、楽しく読むことができた。大賞か落選かを分ける差は紙一重。ただし、簡単に直せる部分で損をしている応募作も多いので、投函する前にぜひともじっくり(客観的に)見直してください。
香山ニ三郎
才能豊かな書き手が揃っていた
今年も七作が残った。やれやれまた混戦なのかと思いきや、どれも面白く読ませていただいたし、授賞候補も自分なりにすんなりと出せた。
例によって読んだ順から紹介していくと、まず影山匙『正邪の獄』は中高生時代に親友だった四人の男がファミレスに集って自分たちの仕事ーー泥棒と刑事であることを互いに明かすプロローグでは脱力したものの、刑事の片割れの恋人が殺され捜査が始まる本篇では前半から思いも寄らない展開を見せる。その後もヒネリ技を駆使して、予想のつかない対決劇に運んでいく力には非凡なものを感じさせられた。伊坂チルドレンだし、語りにもまだまだ荒さはあるものの、二三歳という若さを考えても有力候補のひとりと考えたい。
小池康弘『勇者たちの挽歌』は軍事謀略をベースにしたサバイバル活劇。アブない容器を秘密裏に運んでいた政府専用機が北海道上空で撃墜され、同機に乗っていて生き残った女子マラソンの元金メダリストがそれを引き継ぐ。墜落現場近くで訓練中だった自衛隊のエリート部隊員が彼女を守ろうとするが……というわけで、男女の逃避行活劇を期待したけどそちらの演出は盛り上がらず、軍事活劇のほうに偏ってしまった。勿体ない。次作は情報を盛り込むいっぽうで、主人公の造形に沿った物語演出に期待したい。
梶永正史『真相を暴くための面倒な手続き』はタイトルを見てこりゃダメだと思ったが、東京・渋谷の銀行で起きた人質籠城事件の現場指揮に何故か警視庁捜査二課の跳ねっ返り女刑事が当たることになる序盤から軽快に読ませ、後半にも思いも寄らない展開が待っていた。笑いのセンスもあるし、商品性高し。これまた有力候補だろう。
村上暢『ホテル・カリフォルニア』はアメリカを旅する日本人ミュージシャンが途中で知り合ったジミーという男ともどもモハーベ砂漠の中に建つホテルで過ごすことに。夜な夜な繰り広げられるパーティで歌う女たちが次々に殺されるという本格もの、“館もの”であるが、館の特異性はもとより探偵や被害者たちの個性も今ひとつ弱く、音楽趣向や謎解きの妙はあるものの、既存の館ものから抜け出る面白さには乏しかった。
志門凛ト『幸せの戦略』は外資系の経営コンサルタントがアメリカ帰りの美人マネージャーとともに宮城県の中堅電子部品メーカーの企業価値評価に当たり、依頼主であるアメリカの投資ファンドの強い要望もあって順調に再建計画が運ぶかに見えたが……。初めての小説執筆とは思えないこなれた筆致、筋運びではあるが、後半企業サスペンスから親子の血の秘密が絡んだ家族劇に収束、ありがちな話に落ち着いてしまった。主役のキャラは立っている。独自の企業もののアイデアを練ってぜひ再チャレンジしてください。
八木未『ボクが9歳で革命家になった理由』は国政のありかたを憂う北海道・十勝在住の少年の手記から幕を開ける。女性保育士や学生が彼のシンパとなるが、やがて元閣僚の孫で現衆議院議員の甥に当たる小学五年生の男子が誘拐され、犯人の「革命係」から財政赤字と同額の九九一兆円が要求される事件が。奇抜な誘拐サスペンスで、章ごとに事件関係者ひとりひとりの視点から描かれていく語りかたもワザあり。財政危機に対する謝罪や再建を求める犯人側の要求はちょいと青臭いというか理想論的で、破天荒な面白さには欠けるものの、話は充分読ませる。これも授賞対象に加えていいかも。
最後の越谷友華『生き霊』はホラーものだと思ったら警察もの。埼玉県草加市で男児が惨殺され、現場の遺留物から一六年前の猟奇殺人犯のDNAが検出される。だが男は今も刑務所に服役中だった。不可能犯罪の謎自体は魅力的なのだが、過去の事件が掘り起こされていく過程で服役囚と瓜二つの男を登場させるなどちょっと興醒めな部分もあり。また全体的に文章が荒っぽく、他の作品と比べても見劣りがした。骨太な捜査ミステリーではあるけどちょっと冗長でもあるし、次作は構成、推敲に充分気を付けて。
かくして個人的には『正邪の獄』か『真相を暴くための面倒な手続き』のどちらか(出来たら二作授賞)、『ボクが9歳で革命家になった理由』は優秀作ーーというスタンスで選考会に臨んだが、票が割れた。『正邪の獄』は○と×がハッキリ分かれ、×派の強めの反対もあって授賞には至らなかった。残念! でも影山さんが才能豊かな書き手であるのはまぎれもない事実。幸い隠し玉として出して貰えそうなので、マイナス部分をきっちり直して世に問うてほしい。受賞した二作と同様、ご注目いただきたい。
茶木則雄
第一級の“憂国”誘拐ミステリーと警視庁“電卓女”の圧倒的存在感
今年の最終候補は(一次通過作品も含めて)、アイディアに優れた作品が少なくなかった。なかでもとりわけ目を惹いたのは、大賞を受賞した二作だ。
『ボクが9歳で革命家になった理由』はこれまでにない趣向を凝らした、新機軸の誘拐ミステリーである。何と言っても、千兆円近いミステリー史上最高額の身代金が、読み手の度肝を抜く。国家を相手に身代金を要求する作品はこれまでにもあった。が、犯人の狙いが二段仕立てにも三段仕立てにもなっている点は斬新。本作の最大の特長だろう。
大物政治家の孫を誘拐した犯人は、マスコミを通じて政府に二つの要求を突きつけ、どちらかを実行するよう迫る。すなわち、日本の財政赤字に匹敵する巨額の身代金を払うか、抜本的な国家財政の具体的再建案を速やかに提示するか、の二択だ。そもそも日本が三流国に成り下がったのは、理不尽な他国からの要求に屈する、国家の気概の欠如にある、とする犯人側の言い分に、首肯する読者は少なくないだろう。犯行の目的は、「次世代に対する財政的幼児虐待」からの解放であり、「他国への隷属的追従」からの脱却である。そこにあるのは右寄りの思想でも左寄りの思想でもない。自分の生まれた国を愛する、真っ当な日本人の心の叫びだ。センセーショナルな事件を通じて国民一人ひとりが、将来の日本の在り方を真剣に考えて欲しい――それが犯人の真の狙いだ。そのために、死を賭して捨石になる。一歩間違えば、臭くて読めない設定だろう。が、作者は、熱を内に秘めたクールな犯人像を巧みに創造し(犯行に至る、隠された真情が秀逸)、読者の自然な感情移入を可能にしている。
かつてこれほど、共感すべき誘拐犯がいただろうか。読後の率直な感想だ。財政赤字へのアプローチが一面的過ぎるきらいはあるが、斬新なアイディア、緻密に構成されたプロット、説得力ある物語展開、警察捜査の確かなディテール――受賞作に相応しい、第一級の“憂国”誘拐ミステリーである。
同時受賞となった『真相を暴くための面倒な手続き』は、警察捜査の常識をことごとく打ち破る、逆転の発想に驚嘆した。白昼の渋谷で発生した銀行立てこもり事件。通常、経済事犯を扱う捜査二課の女性刑事が、立てこもり現場の陣頭に立つことなど有り得ない。それも“電卓女”を自称する三十路の一警部補が、警視庁捜査一課特殊犯係のSIT精鋭を指揮することなど、絶対に有り得ない。しかも進行中の現場に、警察庁のキャリアが単独で介入するなど、百二十パーセント有り得ない。さらにこのイケメン警視長が、特殊部隊SATの狙撃手を“一名だけ”引き連れてくるなど、警察捜査の常道と指揮系統を考えれば、二百パーセント有り得ない。もう、破天荒も破天荒、無茶苦茶な設定である。
ところが作者は、この破天荒な設定に、警察関連の豊かなディテールと様々なエクスキューズを加えることによって、あっても不思議ではないリアリティと説得力を構築しているのだ。脱帽である。事件の背景となる秘密組織の存在に違和感を覚えたが、警察ミステリーの常識を覆す発想の数々は、称賛に値する。何より、女性刑事の軽妙なキャラクターが魅力的だ。この“電卓女”の圧倒的存在感に、拍手喝采を贈りたい。
いま一歩及ばなかったのは、『正邪の獄』と『生き霊』。ことに前者は、序盤で思わず、腰を抜かすほど驚いた。倒叙物かと思わせてアリバイ崩し、そして……という二転三転の展開に目を見張った。まさに意外性の連打! 物語の源泉にいささか不満は残るが、創りこまれたプロットといい、予断を許さぬ展開の妙といい、捨て置くには惜しい才能だ。一方の後者は、刑務所という鉄壁のアリバイに挑戦した不可能犯罪ミステリー。誰もが想像するネタを除外すべく、一応の布石は打たれているのだが、その布石が万全ではない憾みが残った。とはいえ、冒頭からラストまで一気呵成に読ませるリーダビリティは、抜群である。二作とも隠し玉の有力候補か。
申し訳ないが『ホテル・カリフォルニア』の良さは、私には分からなかった。舞台となるホテルの全体像が曖昧で、トリックにも展開にも新鮮さを感じられない。偶然やご都合主義が散見され、勢いだけで書いたのでは、と思えてしまう。
個人的に惜しまれるのは、『幸せの戦略』と『勇者たちの挽歌』だ。前者は、企業コンサルティングをひとつのミステリーとして構築するアイディアが素晴らしい。筆力もあり、商業出版して問題ないレベルだ。が、それだけに、後半の凡庸な予定調和が惜しまれる。もっとヒネリを利かせて画期的なコンサル・ミステリーに仕立てあげれば、文句なしの大賞レベルだった。後者の特長は、兵器と戦闘シーンの圧倒的ディテールだ。これだけの知識を持つ書き手は、プロにもそう多くないだろう。ただ惜しむらくは、文章力も含めた“小説”部分。上手く育てば、大藪春彦の衣鉢を継ぐ存在になるやも、だ。再挑戦を心待ちにする。両名とも是非、捲土重来を期して欲しい。
吉野仁
オリジナリティの発揮と細部の完成度を高めるべし
今回は、二作大賞受賞という結果になった。まずは、惜しくも落選した五作品について触れていきたい。
まず、最終に残った七作中、わたしが相対的にもっとも高く評価したのは、越谷友華『生き霊』だった。以下、あらすじ。埼玉の草加市で男児の変死体が見つかった。その事件は十六年前に起きた事件と類似していたばかりか、現場に残されていた精液から、その事件の犯人・坂本と同じDNAが検出される、だが、坂本は現在刑務所に服役中。アリバイは完璧だった……。残念なのは、肝心のトリック、真相に驚きがないこと。選考会では乱歩賞っぽいという意見が出た。手堅い話だが斬新なミステリとは言いがたいのだ。それでも全体のドラマや刑務所での様子などはうまく描かれている。バランスがいい。次はより独創的なアイデアで挑戦してほしい。
志門凛ト『幸せの戦略』。コンサルティングの最前線を扱った企業ミステリとでもいうべき導入部にまず驚かされた。オリジナリティということでは文句ない。個性が光っている。しかしながら、どうにもプロットが練られていない。意外性をもたらすための伏線や「この先、何かあるな」と思わせるほのめかし(フラッシュフォワード)など、スリルを高めるための構成づくりに乏しいのだ。たとえば前半、息子がとつぜん訪ねてくるのは突飛すぎる。ビジネス中心の展開から、いきなり家族問題へシフトするため、ちぐはぐに感じられた。冒頭あたりで主人公が「今度のプロジェクトはなにかあるな」ともらしたり、家族についての話題をほのめかすシーンを挿入したりするのがサスペンスの定石だろう。そのほか、隠していた情報を少しずつ小出しにするなど、読者を退屈させず話に引きこむための語りの工夫も必要だ。
題名のとおり、イーグルスの名曲をテーマにした、村上暢『ホテル・カリフォルニア』は、館もの本格ミステリだ。しかし、その設定にこだわったせいか、ひどく強引な仕上がりとなってしまった。イーグルスという実在のバンドを題材にしながら、物語に登場するホテルもその道具立ても現実にありえないファンタジーなものばかり。書き方があいまいでつかみどころがない。チューニングが不完全でリズムも音量もバラバラという感じ。名プロデューサー&エンジニアが欲しいところだ。だが全体に平明で読みやすく語り口もいい。細部までこだわった作品を仕上げれば、すぐに作者はプロデビューするだろう。
影山匙『正邪の獄』は、選ぶ人によっては予選一次通過も危うい内容ではないだろうか。幼なじみの四人が集まり、うち二人が刑事、あとの二人が泥棒というおよそ現実にはありえない設定なのだ。おまけに文章が拙く、ご都合主義の展開がすぎる。申し訳ない、わたしはまったく評価できなかった。大胆なストーリーを読ませるためには、現実世界をディフォルメして描き、嘘をホントらしく見せる洒脱な語り口がほしいもの。
そして、小池康弘『勇者達の挽歌』は、軍事アクションもの。元オリンピック女子マラソン金メダル選手がテロ事件に巻き込まれる。彼女は、不時着した飛行機から「容器」を抱えて脱出し、安全な場所まで必死の逃亡を果たそうとする。おそらく軍事オタクが読めば満足するのかもしれないが、そうでない読者にとり、兵器に関する記述や描写が過剰すぎる。全体に文章が固い。731部隊が絡み、スーパー老人が都合よく現れるなど、全体に乱暴すぎる点もマイナスとなった。ヒロインの視点のみでサバイバルゲームに徹して描いていれば、もっと高く評価したのだが。
大賞を受賞したうちの一作、八木未『ボクが9歳で革命家になった理由』は、身代金の要求が国家相手というスケールの大きな誘拐ミステリ。だが、全体に幼稚でご都合主義がすぎる感じがつきまとい、わたしにはいまいちピンとこなかった。あっさりと事が運びすぎるし、人生に長けた思慮深い大人がどこにもいない。もっとも本作の主題が現代日本の「世直し」にあるなら、ゆるく浅薄でいきあたりばったりな感じの革命話もふさわしいか。そう思って強く反対はしなかった。
もう一作の大賞、梶永正史『真相を暴くための面倒な手続き』は、渋谷の銀行で起きた立てこもり事件を扱った警察小説だ。タイトルだけで判断するなら落選確実のものながら、ヒロインの警部補キャラと意表をつく展開がよく、くいくいと読ませる。いささかコミカルがすぎるノーテンキな場面があったり、真相となる「悪」や「組織」の取り扱いがやや陳腐だったりするものの、伏線や仕掛けを含め、全体にわたって娯楽性が発揮されている。これならば大賞受賞に文句はない。
これからの応募者は、ぜひ文章、プロット、細部など、徹底的にこだわって書きあげたのち、もういちど見なおし完成度を高めてほしい。