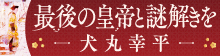第11回『このミス』大賞 2次選考結果 茶木則雄氏コメント
己を信じ、ひたすら精進すべし!
第11回の『このミス』大賞には、過去最多の応募作が集まった。その数、473篇。昨年に比べて79本の増加である。第1回の応募総数が163本だから、この10年余りで約3倍に伸びた勘定になる。一次通過作品の本数もこれに応じて増える傾向にあり、最も少ない第3回の8作(応募総数202本)から昨年、今年の最多23本(※編集部注/二重投稿失格により22作。以下同)と、これも約3倍に伸びている。この5年間で計算すると、一次突破率の平均は5.36%という数字だ。今年度の第58回江戸川乱歩賞が一次通過作98本、二次通過作22本(応募総数367本)だから、本賞の一次は乱歩賞の二次よりさらに狭き門ということになろう。
一次の難関を突破した応募者の方々は、自信を持っていただきたい。己を信じていただきたい。と同時に、最終選考に漏れた応募者は、大いに自省していただきたい。何が足りないのか、どこがまずかったのか――。
落選作で最も点数的に惜しかったのは、『オレ様先生』だ。残留思念リーディングというSF的ギミックを使うなら――つまりひとつの《大嘘》を前提にするなら、それに対する科学的アプローチや警察捜査のリアリティに、一段と腐心すべきだろう。実際この種の連続誘拐事件が発生した場合、警察がどう動くのか。まずは関連資料を精読してほしい。警察捜査全般に現実感が乏しいため、本来あるべき緊迫感が著しく削がれている。また女子高生と教師の恋愛模様も、あまりに甘すぎて食傷した(特に後半)。サスペンスを基調とするなら、ヒーロー、ヒロインはフェイ・ケラーマン『水の戒律』(創元推理文庫)あたりの「節度ある関係」を念頭に置くべきだろう。ミステリーにおいて恋愛的要素はあくまで副菜であり、決してメイン料理ではない、ということを肝に銘じてほしい。
最大の欠点は、残留思念が事件解決の決定打になりすぎる点だ(少女の過去の謎も含めて)。特殊能力が「のび太」における「ドラえもんのポケット」であっては、作品に謎解きの妙味もサスペンスも生じないことを、声を大にして指摘しておく。筆力があり、敲いてみたい素材だからこそ、つい辛口になった。ついでに言えば、誘拐事案等の特殊犯罪捜査については毛利文彦『警視庁捜査一課特殊班』(角川文庫)が、一般の警察捜査については『殺人捜査のウラ側がズバリ!わかる本』(謎解きゼミナール編、KAWADE夢文庫)あたりが、最もわかりやすい入門書だと思う。他の応募者も参考にしていただきたい。
次に惜しまれたのは『2Days with 死体 in 冷蔵庫』だ。一気に読ませる面白さは、並々ならぬものがある。コンパクトにまとまりすぎた観はあるが、倒述型ミステリーとしてこの斬新な設定は十分、賞賛に値する。ただ、特異なシチュエーションを構築するうえでの説得力が、十全に施されていない憾みが残った。なぜ、娘の友人と元カレが主人公の家に留まらなければならないのか。作品の根幹に関わる部分の詰めが十分ではないし、脅迫者の正体を推理する過程にも、強引さが目立つ。プロットの粗を、無理やり腕力で押さえつけた、という印象だ。が、この豪腕ぶりとリーダビリティは、捨て置くに惜しい。是非とも捲土重来を期していただきたい。
上記2作は最後まで、選考委員の間で議論の対象になった応募作だ。ここからは個人的に思いが残る作品を順に紹介する。まずは『パーフェクト・ワールド』。閉塞感漂う現在の政治・経済・国体を打破する近未来経済施策をモチーフにした点が、殊勲甲だ。重くなりがちなテーマを、軽い文体と軽妙なキャラクターで推進させる作者の目論見は、成功していると思う。ことに、主人公とチームを組む小役人が、会話の途中で随所に挟む「(うふふ)」という笑い――照れ隠しなのか嘲笑なのか自嘲なのか判然としない含み笑いが、抜群にいい。こういう奴いるよなあ、と個人的には大いにツボった。なかなか事件が起こらないため、中盤までサスペンス性に乏しく牽引力となる謎の提示がないのが、最大の欠点だ。つまりは構成に問題がある。同じ欠点は『重力のナイフ』にも言える。アポロ計画と宇宙飛行士への憧憬を交えた導入部は魅力的で、これからどう話が展開するのか、読みはじめは大いに期待させた。過去を消すイレーザー(消しゴム屋)の存在もアクセントになり、リーダビリティはかなり高い。が、謀略ものと思わせておきながらSFに落とすという構成が、決定的に間違っている。真相を明かされて腰が砕けた。これは逆でしょ。SFと思わせて、実際は不可能を可能にする(不可解な謎を合理的に解明する)知的謀略サスペンスにすべきだった。
続いて惜しまれたのは、『瑠璃色の一室』『夏桜』『りらいと』『神様による猫色の日々』の4作。いずれも20代(『神様』は応募時19歳)の若い書き手による応募作だ。どれも将来性を感じさせる作品で、筆力も歳に似合わず、十二分に一次突破の水準に達している。最後まで読ませる力はなかなかのものだ。が、共通して言える欠点がある。細部のリアリティと説得力である。これが十分でないから、ところどころで咽に小骨が引っかかる。また全体像が明かされても、犯人側の行動原理が動機を含めて釈然とせず(ことに『夏桜』は私に言わせればザ・無理筋)、俯瞰して見る全体像に違和感を覚えた。犯人側の視点でのプロットの再構築と検証を、この4名には奨めたい。同様に最後まで読ませる力は持っていたが、『わが母のおしえ給いし歌』も基本的に上記4作と同じ欠点を内包している。
個人的に期待していたのは、一昨年競馬界のトンデモ・ミステリーで一次を通過した著者による『スクープ・ハンターの乱舞』と、昨年2作同時に二次に残った著者の『羊が吠える』だ。前者は再び競馬界のトンデモ陰謀を題材に取り上げたのが、後者は昨年応募作の世界観そのままに続編を書いたのが、完全に裏目に出た。両者とも前作を超えるインパクトがなく、二次の接戦のなかで埋没した感じだ。戦略ミスと言わざるを得ない。以前、別の賞でも読んでいる作者の『神待ち』にも期待したが、書き手の迷いが伝わってくるような作品だった。エンターテインメントとしては冗長で、文芸作品としては深みに欠ける。どっちつかずで中途半端なのだ。いま一度原点に立ち返り、ディーン・R ・クーンツ『ベストセラー小説の書き方』(朝日文庫)あたり熟読することを、お奨めする。
『ライブ・イン・邪宗門』『星屑のパリ』『皇帝の乱』『日本発狂』の4作に関して私は、いい読者ではなかったのかもしれない。良さがまったくと言っていいほど伝わってこないからだ。とは言えこの4作も、一次選考委員が認めた作品である。自信を持っていい。が、いずれの作品も、これまで挙げてきた他の作品の欠点の数々を、少なからず抱えていることは指摘しておく。
最終に残った7作(※編集部注/二重投稿失格のため6作)は、少し手を入れれば出版レベルに達する作品揃いだ。どれが大賞を射止めるか、今回も予断を許さない。最終選考会での激論(?)を、今年も大いに期待していただきたい。
さて、『このミス』大賞がはじまって10年、世に出した新人の数は34名を数えた。この4年間に限って言えば、平均して毎年5名前後が、隠し玉を含めてデビューしている勘定になる。応募数に対する出版比率は、本賞が一番高いのではあるまいか。つまりは、入り口は狭いが、出口は広い門――それが『このミス』大賞である。
諦めないことが肝要である。己を信じ、ひたすら精進すべし、だ。
付記(2012年8月31日)
最終候補に残した応募作のうち一作が、二重投稿により失格となった。選考に携わった委員のひとりとして、遺憾の意を表さざるを得ない。同時期に同じ作品で別々の新人賞に応募することは、応募規定で明確に禁止されたルール違反だ。もし双方で受賞した場合、出版社間で版権問題が持ち上がるからである。たとえどれほど素晴らしい作品であっても、ルールはルールである。主催者側が厳正に対処するのは当然だろう。
二度とこういう事態が出来(しゅったい)しないように、ここで二重投稿に関するガイドラインを述べておきたい。作中の文言等が若干違っていても、同じ世界観、主人公、ストーリーで描かれた作品は、同一作品と見做される。同じ世界観で登場人物が被っていても、まったく別のストーリーで描かれた作品(続編やスピンオフ)――これは二重投稿には当たらない。が、しかし、映像化やコミック化、キャラクター問題などが絡んだとき、出版社間で権利の帰属問題が起こる懼れがある。慎まれるべきだろう。
念のため書き添えておくが、これはむろん、応募時に結果が判明していない場合である。落選が確定していれば、同一作品で他の賞に応募しようと二重投稿に当たらないのは、言うまでもない。
ただ個人的には、改稿した作品であっても原稿の使いまわしは、慎むべきだと考えている。理由は以前に何度も書いているのでここでは繰り返さない(興味のある方は過去の選評を確認していただきたい)。