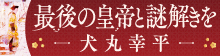第11回『このミス』大賞 2次選考結果 村上貴史氏コメント
一定の水準は達しつつも差を感じた今回
昨年も感じたことだが、一次選考を通過する作品とそうでない作品で、明らかにレベルの差が出てきている。賞そのものが歴史を重ね、質が高まっている一方、応募原稿も増え、小説としての完成度が不十分な作品も増えてきたということなのだろう。結果として、一次を通過した23作品(※編集部注/二重投稿失格のため22作。以下同)は、一定以上の水準を揃えた作品が揃っていた。そして、その23作品のなかでも、やはり明らかに出来映えに差があったのである。
深津十一『石の来歴』と安生正『下弦の刻印』の両作品は、23作品のなかでも1、2を争う上質な作品であった。石に執着する老人に多くの筆を費やした奇妙な青春小説の『石の来歴』と、大活劇小説の『下弦の刻印』。どちらも一気に読ませてくれたし、十分に愉しませてくれたし、新しさも感じさせてくれた。また、柊サナカ『婚活島戦記』は、私が一次で推した作品だが、これまた前述の2作品同様、スムーズに読めたし、“バトル・ロワイヤル”的なデスゲームものとしての新しさも堪能出来た。このあたりが楽々と最終予選まで駒を進めた作品である。
それらとは対照的にあっさりと落選したのが、木月雲行『ライブ・イン・邪宗門』と西島裕彦『星屑のパリ』であった。いずれも日常を部分的に逸脱した世界での物語なのだが、この作品群のなかで闘うには、どうにも薄っぺらさが否めなかった。黒木隆志『羊が吠える』も二次選考を突破するのが難しい1冊だった。昨年の応募作と共通の設定での新作だったのだが、二度目ということで設定の新鮮さは失われているし、作品そのものとしても、前作ほどのミステリ的なツイストもなかった。
それら3作品ほどあっさりではなかったが、やはり落選と判断せざるを得なかった作品もある。彼方宗一郎『神様による猫色の日々』も、小説としての表現ではなく単に説明するだけの文章が散見されたり、意外性を狙ったであろう結末に新鮮味が乏しかったりと残念であった。霧沢史也『皇帝の乱』は、私が担当した一次選考の作品のなかでは上位だったが、今回の二次選考のレベルのなかでは、魅力の絶対量が不足していた。非常に勢いのある作品として楽しい矢吹哲也『スクープ・ハンターの乱舞』も、造りの粗さが他の作品との比較で目についてしまった。学文路譲『日本発狂』は、シリアスとユーモア、あるいは法螺話とリアリティのバランスがなんともいびつで、しかも文章がこなれていないという作品で、正直なところ読みにくかった。結末のとぼけた味は悪くないのだが、それまでをチャラに出来るほどの結末でもない。
上記7作品と同じく二次選考止まりという結果に終わっても、内容的にはずっと優れていた作品ももちろんある。例えば、穂波了『神待ち』。主役が次第に壊れていく様が十分な迫力で描かれていた。あいま裕樹『オレ様先生』の甘々な世界もよい。連続誘拐殺人事件を超能力で解決しようとする枠組みと、この甘さ加減のブレンドが絶妙だった(のだが、他の2委員を説得するには至らず)。木元カナタ『2Days with 死体 in 冷蔵庫』も娘を殺してしまってオタオタしたり慌てたり開き直ったりする父親の物語というサスペンス小説を、別の事件と巧みに重ね合わせて完成させた作品で、抜群に愉しく読めた。小西未来『重力のナイフ』は、中盤において“こうなって欲しくない”という方向に方向転換してしまったのがあまりに残念。それまでの不思議な出来事の魅力が一気に消えてしまうのである。最高に魅力的だっただけに、最高にガッカリした1作だ。
これらの4作品が、いってみれば二次選考版“次回作に期待”の作品群である。それらと競りあって最終選考に滑り込んだのが、堂島巡『梓弓』をはじめとする4作品。堂島巡『梓弓』は、まずは文章力が光っていた。外連がない一方で、いくつか細かな点で不自然も感じられたりもしたが、トータルとしては十分に読ませてくれた。藍沢砂糖『ポイズンガール』は、一定のルールで食べ物に仕掛けをしあう女子高生たちを描いた作品で、スリルをたっぷりと味わうことが出来た。だが、彼女たちがある一線を越える心理の説得力が不十分だったようにも思う。最終選考でそのあたりがどう評価されるか。新藤卓広『或る秘密結社の話』は、導入部が雑(説得力不足)で萎えさせるが、トータルでは盛り返してセーフ。軽妙な文体も心地よい。
それ以外の作品についても触れておこう。
三瀬近江『夏桜』の青春小説としての味わいには好感が持てたが、事件を転がす人物の行動はあまりに不自然だった。その不自然さのうえに立脚した心地よい小説だったのが惜しまれる。葉月瀬人『りらいと』は、記憶の書き換えというネタを活かして愉しく読ませてくれたが、大風呂敷を終盤でたたむ際に、それまでの魅力もあわせてしぼんでしまった。壮大な計画はよいが、詰めの甘さも感じられた。明利英司『瑠璃色の一室』は、ところどころ非常に印象的な場面のある小説だった。例えば前半に登場する安い飲み屋の風景とか。それだけに、そうした素敵な光景をつなぐストーリーの魅力や登場人物たちの行動の説得力の不足が目についた。斎藤操『わが母のおしえ給いし歌』は、海堂尊の産んだ白鳥のような雰囲気の剣崎というキャラクターが魅力だったが、事件の構造がどうにも「作りもの」に止まっていたのが弱点だった。序盤から中盤にかけて、これが今回の本命か、と思いながら読んでいたのが、追丸零時『パーフェクト・ワールド』。ビジネスプランや選挙戦略、あるいはリズミカルなプログラミングといういくつもの要素が輝いていて愉しく読ませてくれた。だが、物語としての構成(動き始めるまでが長過ぎる)に難があり、最終選考進出には至らなかった。
※二重投稿で失格となった作品の選評は、削除させていただきました。(『このミステリーがすごい!』大賞事務局)