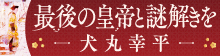第10回『このミス』大賞 2次選考結果 村上貴史氏コメント
着想、設定、構成の練りこみを
23本の一次選考通過作品を読んでまず、読みやすい作品が例年以上に多いと感じた。文章や台詞で引っかかる部分が少なく、ストーリーもこなれていてページをめくらせる。しかも書き手の独り善がりに陥らずに物語を紡いでいる。そうした作品の割合が高かったのだ。
そんな水準であったが故に、在神英資『ユークリッド焼きそばの漆黒』、玉峰新一郎『怒れる樹木のうた』、三木了『微妙都市』、西條好夫『夢幻臨床』の4作品については、それぞれの至らなさが目についてしまった。特徴のあるキャラクターや舞台を設けようとする心意気はいいが、結果をみれば“キャラ立ち”させるための特徴付けに終わっていて、深みや説得力に欠けていた。特異であればあるほど、それをきちんと読者に納得させることに筆を費やすのが基本だろう(あるいは、せめて特異さが薄っぺらなことを補う代替策を講じるべきだ)。もちろん読者を納得させるための記述が小説としての読みやすさを損なってはならないわけで、相当の実力が求められるのである。この4人の方々には、自分の着想をどこまで練り込み、どこまで丁寧に読者に語りかけたか、もう一度振り返ってみて戴ければと思う。
その点、時井佑『刑務特別区』は特殊な設定の説明がきちんと出来ていて好感が持てた。だが、ボリュームは半分でよかったのではないか。視点人物が多すぎて物語が散漫になる。また、バスジャックや脱獄などのアクセントははさんでいるものの、中だるみ感は否めない。とはいえ、特異な世界をきっちりと構築した実力は高く評価したい。次は物語としてどこにフォーカスするかをきっちりと計算して書いてみてはいかがか。
黒木隆志の二作品『世界の終わり』と『僕が誰なのか、あててごらん』も、特異な世界だった。両者を比較すれば『世界の終わり』の方が出来はよい。成長小説、近未来描写、本格ミステリめいた知的遊戯のいずれもが読ませる水準に達している。だが、それらがバラバラであり、同じ袋に放り込んだだけ、という以上の緊密な結びつきが不十分だった点が残念だった。『僕が誰なのか、あててごらん』は、何者かに密室に閉じ込められた面々の心理ドラマであるが、その密室状況に関する説明はいささか心細いレベル。それを会話の内容のスリルで補い、とりあえず先へ先へと読ませていた。これはこれで一つの手段としてアリだろう。惜しむらくはタイトルで示された問いに関する回答の説得力が欠けていた点。結末にも独り善がりな一面があった。なお、二作品が一次予選を通過した点は著者の持てる力量を証明しているともいえるが、いずれも二次予選を通過できなかった点もよく考えてみて戴きたい。一作品を磨き上げるという道もあるということだ。
特異な世界を舞台にしてその世界自体の魅力が鮮烈だったのが、はじめひかる『愛してムーヴィン 恋してダイヴィン』だ。特に序盤の鮮やかさは特筆に値する。中学生の男女4人組が、川から自殺者の死体を次々と淡々と引き上げていく光景のなんと美しいことか。そのまま進んでくれればよかったのだが、後半で登場人物がどんどんと増えていくにつれて序盤のきらめきが次第に失われていったのが非常に残念。後半で描かれた5人組の関連を解明するエピソードも、妙にロジカルすぎて(かつ作りものっぽさが見えすぎて)作品世界の魅力を減じている。まことにもって惜しい作品である。
お面をかぶると変身する――こんな特異な状況に特にたいした説明もつけず、“そういうもの”として一気に突っ走ったのが神護かずみ『猿王~哀しき道化師たちの祝祭』だ。この一作はアクション小説として痛快。実に愉しく読めた。だが、それだけといえばそれだけ。新鮮味が感じられないという批判は甘んじて受けざるを得ない。
慰撫アシマ『風に揺れる四十八の棺』もストレートな娯楽活劇。読者を飽きさせない工夫があちこちに施してあって、一気に読ませてくれた。だが、これも新鮮味に欠ける。しかも『バトロル・ロワイアル』という偉大なる先達が備えていた“クラスメイト同士の”殺しあいという重要な設定がすっぽりと抜け落ち、単に殺しあいを強要された人々のドラマになってしまっていては、勝ち目はない。
田中徹一『プルートーの降伏』は終始作りものの世界に浸りきっていた。冒頭で記した“愉しく読める”作品であることは間違いないのだが、それ以上ではなかった。終盤での“風が吹けば桶屋が儲かる”的な展開は愉しめたが、そこは所詮作りもののなかでの都合のよい展開に過ぎない。伊坂幸太郎の縮小コピーというか、カラー原稿をモノクロコピーしたというか、こぢんまりと纏まってオリジナリティに欠け、しかも読者の現実に響いてこないのでは受賞は難しかろう。読みやすい作品を書く能力をどの方向で活かすか、再度根っこのところで考えてみるべきだ。
そこそこ愉しく読みつつも、読み終えてみると“着想だけはよかったんだな”というのが、納谷英樹『ROUTE』。人間と人工知能の関係をエンターテインメント的に仕上げようとしたのだろうが、人工知能描写に説得力が不足していた。とくに、クライマックスで著者の大仕掛けを読者に納得させる部分の説得力が決定的に足りない。御自身の着想のキモを読者に伝えることに関して、もっと執念を持つべきだろう。
戴天洙吏『トリプル・アクセス』の長所については一次選評を参照して戴きたいが、後述する『鋼鉄の密林』との比較で負けた。あちらと較べて、ホラ話の土台となるリアリティが脆弱だったのが敗因である。
これまたホラ話といってよいのだろうか。龜野仁『ALL ABOARD』では、元警官の日本人がニューヨークの闇社会で生き延び、その後、警察と手を組んで活躍するのだ。リアリティに欠けるが、テンポよい物語はそれなりに読ませる。だが、そのテンポもときおり淀む(特に過去を語る場面で淀む)。これでは勝ちきれない。リアルを目指すか、テンポを取るか。ホラで圧倒するか。もちろん全てという手もある。
長い作品であるうえに、その前半に魅力が欠けているのが篠原昌裕『殺人画家は 私です』だ。“殺人画家”というモチーフをはじめとして個々のパーツは悪くないだけに、全体としての構成(それは冗長な部分を切り落とすことも含む)を冷静な視線で見つめ直すのがよかろう。
愉しく読ませるし好感度も高かったのが、中川つちか『♪のある恋愛風景』だ。だが、選考の場においてミステリとしての争いになると分が悪い。ミステリ要素が不足しているのだ。これは、波名『駄作のすゝめ』も同様。他に魅力的な作品がなければ争いを勝ち抜ける水準の出来映えであったのはたしかだが、同水準の争いとなった場合は、まず負ける。こうしたタイプの作品を投稿する場合には、そのリスクを意識しておくべきだろう。
というわけで、これらの作品を蹴落として勝ち残ったのが、次の6作品だ。
友井羊『僕がお父さんを訴えた理由』は、子供が親を訴えるという、その子供が実によく書けていて、作品にどっしりとした重みを与えている。しかも、その子供の心がミステリの文脈と一体となる形で描かれている点が素晴らしい。主役の恋人の造形などはまだ磨く余地があるだろうが、その一方で、義母の描写には冴えがある。伏線(それなりに張られている)のバランスをもう少し調整すれば、さらに上質なミステリとなるだろう。
愉しく読ませるし好感度も高かったのが、岡崎琢磨『また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を』だ。『♪のある恋愛風景』『駄作のすゝめ』と同様の文章で紹介したが、この作品には、ミステリの魅力もしっかりと備わっていた。日常の謎風の連作としての魅力もあれば、主人公とバリスタの恋愛劇を織り込んだ長篇ミステリとしての味も備えている。好感度だけに止まらないプラスアルファが、しっかりと存在していたのだ。
ハードボイルドも選んだ。保坂晃一『エンジェルズ・シェア』である。ハードボイルドの一つの魅力であるワイズクラックが、これでもかというくらいにてんこ盛りに盛り込まれた一作だ。ワイズクラックだけで全体を完成させたといってもいいほどの量である。ところどころ空振りもあるが、この量は圧倒的。それが、資格停止中の弁護士という主人公の造形と絡み合って大きな魅力となっている。
塚本和浩『鋼鉄の密林』は、東京タワーを占拠した犯人側の行動に特色がある。それに加えて、70代の老人がスーパーヒーローとして活躍する荒唐無稽さが素晴らしい。こんなジイサンいるわけないじゃんと思いつつも、ついついジイサンに声援を送ってしまう自分がいる。これこそがエンターテインメントの筆力であろう。
筆力といえば、矢樹純『Sのための覚え書き かごめ荘事件のこと』もそう。一次選評に書いたことに付け加えることは特にないのだが、妙は妙なりに説得力と魅力を持ってページをめくらせるのである。そしてその説得力と魅力はどうやら他の二人の選考委員にも響いたようだ。
本稿で23番目に言及するのが、田中圭介『空と大地と陽気な死体』だ。いい雰囲気の小説だが、これに関しては、主要登場人物の一人の行動に疑問を覚えた(つまり、説得力が不足していた)。あの人物がそこまで友人を追い詰めるとは思えなかったのである。とはいえ、他の作品との争いにおいて負けないだけの筆力を備えていたのもたしかで、最終選考への推薦には異を唱えなかった。
というわけで、主体的に推したもの推されたものもあり、正直なところ二次予選通過の6作品に凸凹はある。だが、この6作品には、愉しく読ませる工夫が十二分にちりばめられていた。そして、最終選考会でどれが選ばれるか、例年以上に予想がしにくい。第10回にして、最も興味深い最終選考会といえよう。
→ 通過作品一覧に戻る