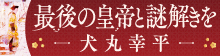第9回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望
“ふつうによくできたミステリ”は必要ない
大賞受賞作は満場一致で瞬時に決まった。こんなに気持ちよく即決したのは、第4回の海堂尊『チーム・バチスタの栄光』以来じゃないですか。それもそのはず、『完全なる首長竜の日』は、ここ数年に読んだ数十編の公募新人賞受賞作の中でも1、2を争う出来。しかも、著者はすでに別の作品で朝日時代小説大賞を受賞しているそうだから、今年の新人王は、文句なしに乾緑郎で決まり。というか、『完全なる首長竜の日』の作者が山田風太郎ばりの忍者活劇も書けるとは……。そっちの受賞作『忍法煙之末』を早く読みたい。
こっちの受賞作『完全なる首長竜の日』は、P・K・ディック(とくに『ユービック』)流の現実崩壊感覚を主旋律にした現代もののサスペンス。「トータル・リコール」とか「マトリックス」とか「ザ・セル」とか、虚構と現実の区別がつかない物語の系譜に属する。今年の映画で言えば、まさに「インセプション」で、虚構世界での自殺がくりかえされるところもよく似ている。もっとも、当然のことながら、本書が書かれたのは「インセプション」公開以前。昨年6月、劇団 SPIRAL MOON が東京・下北沢の「劇」小劇場で初演した自作の戯曲「LUXOR」が下敷きだというから、アイデアを頭にインセプションされたとすればクリストファー・ノーランのほうだろう。
“昏睡状態に陥った患者とコミュニケートするための新しいインターフェイス”というSF設定は(「インセプション」以上に)リアルだし、中堅の少女漫画家であるヒロインの日常をしっかり(たいへん面白く)描くことで、ウソっぽさを感じさせない。思えばディックも、ありふれた日常描写が抜群にうまく、だからこそ、現実の皮がべりべりとめくれる感覚がめちゃくちゃリアルに伝わってくるわけだ。その意味でも、『完全なる首長竜の日』はまさにPKDサスペンスの正嫡。この小説がセンセーションを巻き起こす日が楽しみだ。
なお、題名(およびピストル自殺のモチーフ)はサリンジャーの短編 ‘A Perfect Day for Banana Fish’ (バナナフィッシュにうってつけの日)から。首長竜は「ブレードランナー」におけるユニコーン(「インセプション」におけるコマ)の役割を果たしている。
今回、『首長竜~』に次いで2番目に評価したのは、喜多喜久『有機をもって恋をせよ』。主人公の非モテ男子、桂一郎は有機化学を研究する大学院生。天然由来の化学物質を単純な有機化合物から人為的に合成する“全合成”が専門分野だが、なんと彼は、“物質の構造を見ただけで合成ルートが閃く”という特殊能力の持ち主。その力を使って破竹の勢いで論文を発表してきたのに、研究室の新人秘書にひと目惚れしたとたん、能力を失ってしまう。そのとき、主人公の前に、カロンと名乗る黒衣の女が出現する……。
とまあ、設定はぶっちゃけ、石川雅之『もやしもん』+森見登美彦『太陽の塔』。ただし舞台は東京農大でも京大でもなく、東大農学部。理系大学院生の日常がめちゃくちゃおかしい。絶食系男子がいきなり恋に落ちたら……というベタな設定ですが、全合成にかける主人公の情熱と鮮やかなディテールのおかげで、すばらしく個性的な小説になっている。前代未聞空前絶後の有機化学ラブストーリー。ただし、さすがにこのタイトルはあんまりなので、“オーガニック・ラブ”もしくは“ラブ・ケミストリー”と名づけたい。
反対派の茶木委員からは、こんなのライトノベルじゃん!(大意)との声もありましたが、女の子の萌えキャラが描けてないのでラノベ度は低めです(事実、作者はこのラノ大賞にも応募したが、1次選考にも通らなかったとか)。さいわい、香山二三郎委員の力強いA評価を得て、すんなりと優秀賞受賞が決まった。
この段階で選考会が終了しても不思議はなかったが、揉めたのはここから。茶木則雄委員が「百万人ありとてもわれ行かん」の覚悟で、『羽根と鎖』を推して推して推しまくったのである。たしかに筆力はあるし、構成もよくできている。これが湊かなえの新作なら、たちまち20万部突破も夢じゃない。しかし(第7回優秀賞の塔山郁『毒殺魔の教室』のように)たまたま不運にもスタイルとモチーフがかぶったのならいざ知らず、『告白』が300万部以上売れている今、DVの話を関係者のモノローグ形式で書くというのは、新人賞応募作としては致命的に間違っている。これまで茶木委員に味方することが多かった吉野委員まで「今回はちょっと……」と反対に回り、茶木委員は三面楚歌。さすがに今回ばかりはゴリ押しも通らないかと思われたが、そんなことで引き下がる茶木則雄ではない。
「ちょっと頭を冷やしてくる」と中座して、15分間の作戦タイムから戻ってくると、30分間にわたり『羽根と鎖』がいかにすぐれているかについて熱弁を揮う茶木則雄。
いつものことなのであとの3人はろくすっぽ話を聴かずにケータイをいじったりツイッターを眺めたりしていたが、形勢不利と見た茶木則雄は即座に泣き落とし戦術に変更。がばと頭を下げ、「せめてなんとか……『有機~』と一緒に優秀賞ということでひとつ」
このパフォーマンスには勝てず(というか、まあ、筆力があるのは事実なので)、『羽根と鎖』への優秀賞授賞に賛同した。
惜しくも落選した3作品については簡単に。私が3番めに推したのは高山深雪『ホークウッドの亡霊』。ありがちな幽霊ホテルもので、どんでん返しもありふれているが、“過去の惨劇の真相を推理する”という本格ミステリの定番をゴーストストーリーと結びつけることで、けっこうユニークなホテル怪談になっている。もっとも、他の3人からは総すかんを食い、指摘された欠点も理解できるので強くは推せなかった。茶木さんの豪腕を見習いたい。『森のくまさん―The Bear―』は、劇場型シリアルキラーもの。いかにもB級っぽいネタと文体は「隠し玉」向きかと思ったが、編集部から手は挙がらなかった。『ハナカマキリの変容』は、しっかり書けているものの、当たり前すぎる。こういう、ふつうによくできたミステリが、いまとなってはいちばん売りにくいかもしれない。
香山ニ三郎
活劇大作に期待
残念ながら、今年は積極的に大賞に推したい作品がなかった――というと、候補作が低調だったように思われるかもしれないけど、そういう意味じゃない。それについて説明する前に、まずは読んだ順から感想を述べていくと、堀内公太郎『森のくまさん―The Bear―』は悪漢ばかりを成敗する連続殺人犯“森のくまさん”の事件に2組の若者カップルが関わる犯罪サスペンス。シリアルキラーものに誰でも知ってる童謡を絡めたアイデアは面白いけど、登場人物もストーリーも類型から出ていない。この手の話は内外にいっぱいあるので、そんなのとはひと味もふた味も違うというところを打ち出して欲しかった。
喜多喜久『有機をもって恋をせよ』は東大とおぼしき大学の農学部で有機化学を研究する大学院生の前にある日突然カロンと名乗る妖女が現われ、スランプ中の彼の立て直しを図る。スランプの原因は恋――彼は教授の新しい秘書にひと目惚れしてしまったのだ。かくて主人公はカロンとともに彼女のハートをつかむべく奮闘努力するというライトノベル調のラブコメもの。大場つぐみ&小畑健のマンガ『DEATH NOTE』や伊坂幸太郎のアノ作品など髣髴させられるカロンのキャラはいささか食傷気味だけど、理科系学生たちのウブで不器用な恋愛活劇が何とも楽しい。有機化学をめぐるアカデミックな趣もあるし、ラストにはサプライズもあり。大賞候補には軽めだけど、優秀賞なら狙えるかも。
高山深雪『ホークウッドの亡霊』は19世紀末のイギリスの田舎にある幽霊屋敷の縁起から説き起こされていくが、細部が薄味でちょっとがっくり。もっとも舞台はその屋敷が移築された現代の軽井沢に移るのだが、語りが濃密になるわけではなく、あっと驚く大仕掛けも外国映画に前例があったりして再度がっくり。ゴシック系のホラサスはもっとじっくりこってりと読ませて欲しいと思うのである。
乾緑郎『完全なる首長竜の日』は南西諸島のある島をめぐるヒロインの回顧譚からして著者の並々ならぬ筆力がうかがえる。少女マンガ家である彼女には長年昏睡状態に陥っている弟がおり、ふたりは最新の医療機器を通して交感していたという設定は、岡島二人=井上夢人的なホラサス仕立てを期待させた。しかし枚数が短めで、物語もストレートに収束していく。文章的にはピカイチだし、サリンジャーの著名作品とパラレルになったテーマ設定も充分魅力的なのだが、山あり谷あり、波乱万丈の活劇嗜好者としては、その点少々物足りなくもあるので、喜多作品と同様、取りあえず優秀賞候補としてキープ。
佐藤菁南『羽根と鎖』は長崎を舞台に長年親の虐待を受けていた少女の軌跡が掘り起こされていく。少女について語られる様々な証言を多声的にとらえてみせた技量はなかなかのもの、はたまた掘り起こしていく人物が果たして誰なのかといった興味もあるのだが、『森のくまさん~』と同様、目新しい趣向には乏しく、DVもののサスペンスとしてはありがちな作品に止まっていよう。
最後の美輪宙『ハナカマキリの変容』で一番困ったのは、別の新人賞ですでにいちど読んだ作品だったこと。二重投稿ではないし、前稿に手が加えられているのもわかるのだが、大筋に変わりはなく、さすがに手放しで誉めるわけにはいかない。かつて拉致監禁の被害にあいトラウマを抱えるOLがひょんなことから健気なキャリアウーマンと知り合い意気投合するが……という女性サスペンスもので、斬新さはないけれども、こなれた語り、キャラ造形でぐいぐい読ませる。初めて読む作品だったら、これがイチ押しだったかも。
かくて今回は『ハナカマキリ~』にいちおう○をつけたものの強くは推せないので、『有機をもって~』と『首長竜~』との三つ巴ということで選考会に臨んだ。結果、『有機をもって』を優秀作、『首長竜~』を大賞授賞作とすることで同意した。残念ながら、『ハナカマキリ~』は賛同を得られなかったが、同じく反対意見の多かった『羽根と鎖』が優秀作に決まったのは、ひとえに茶木委員の熱い弁護に因る。すなわち茶木則雄賞であるが、どんな賞であれ、賞は取ったもの勝ち。佐藤さんには今後の作品でカヤマ、オオモリ、ヨシノを見返していただきたい。
ということで、冒頭の言葉に戻ると、今回は枚数的に短めなもの、コンパクトに仕上げられたものが目についた。『首長竜~』の感想でも記したように、根っからの「活劇嗜好者」であるワタクシは枚数を使った大仕掛けな作品が好きなのである。完成度の高い作品が嫌なわけじゃないけど、この賞ではやはり独自のアイデアに貫かれた波乱万丈の物語エンタテインメントに登場して欲しいのだ。第10回となる次回にはワタクシ好みの傑作と出会えることを期待したい。
それともうひとつ、たとえ二重投稿でなくとも、他の新人賞に応募したものを再度出すのは止めたほうがいい。オリジナル性が採点の重要な基準である以上、再応募作品はそれだけで大きく減点される可能性大!
茶木則雄
新人賞応募作に求められる全てが、ここにある
候補作は赤ペンを手に読むようにしている。気になった箇所や問題点、さらには用語や文章をチェックし、感想を書き込むためだ。いわば赤入れの多寡が、その作品への評価のひとつの基準になる。『完全なる首長竜の日』に入れた赤は、ほとんどない。あったとしても、「OK!」「GOOD!!」といった感嘆符付きの賞賛が大半であった。
冒頭からして素晴らしい。「《猫家》は、「みゃんか」と読む」に連なる短い文章だけで、作者の並々ならぬ才能が伝わってきた。主人公の母親の実家である猫家という屋号の由来が奇妙な現実味に溢れ、たかだか原稿用紙十枚足らずの分量であるにもかかわらず、南西諸島の小さな島の情景からそこに暮らす人々の歴史までが、鮮やかに浮かんできた。しかもこの、微睡みのなかの回想は、弟が海で溺れる部分を中心に物語のなかで何度もリフレインされ、主題と有機的に結びついていく。主題は「胡蝶の夢」だ。そこに昏睡状態の人間と対話できるSF的ツールを取り入れることによって、作者はこれまでにない斬新な物語を構築することに成功している。主人公である少女漫画家の日常がヴィヴィッドに活写され、夢と現実の狭間が徐々に崩壊していく過程を、ミステリー的手法を用いて巧みに暗示してみせるのだ。同様のテーマを扱った映画「インセプション」に、勝るとも劣らない面白さである。
奔放な発想力と類い稀な独創性、堅牢なプロットと瑞々しい文章力――新人賞応募作に求められる全てが、ここにある。大賞受賞は文句のないところだろう。
が、個人的にそれ以上の高い点数をつけたのが、『羽根と鎖』である。冒頭から物語に惹き込まれ、赤ペンを使うのを忘れるほど、一読者として夢中で読んだ。暗示的なラストも出色。読み終わった瞬間、思わず快哉を叫んだほどである。3年連続ダブル受賞も致し方なし、と思って臨んだ選考会だったが、他の選考委員の評価は驚くほど低い(私に言わせれば)ものだった。
確かに、モノローグ形式の構成や児童虐待というテーマは、手垢がついたもの、と言える。そういう意味での斬新さ、独創性は、この作品にはない。しかし、語りだけでその人物のキャラクターを的確かつ玄妙に描き分ける筆致は只事ではない。極めて高度な小説技法を具えた書き手だと思う。テーマの深遠性とリーダビリティは湊かなえ『告白』を凌ぎ、意外性とミステリー的興趣は佐藤正午『身の上話』をも上回る(私に言わせれば)。小説的には手垢がついたテーマとは言え、児童虐待は今も最も今日的な問題のひとつであろう。あえて古い皮袋に挑戦し、既存作品を凌駕する新しい酒を生み出した力量は、充分に大賞に値する。優秀賞に留まったのは、偏に私の力不足によるものだ。作品に罪はないと信じる。いずれにせよ、大賞受賞作にも比肩する、過去最高レベルの優秀賞だ、と断言して憚らない傑作である。
優秀賞を同時受賞した『有機をもって恋をせよ』は、何らかの形で出版することには最初から賛同するつもりだった。ラブコメとしては、非常に楽しく読めたからだ。ただ、物語がいささか冗長であるのと、ミステリー的興趣に乏しい点が、私の減点材料である。「隠し玉」でいいのでは、と考えていたが、他の選考委員の強い推薦もあり、優秀賞受賞ということで落ち着いた次第だ。
出だしだけなら、今応募作中一、二を争う出来栄えだったのが、『森のくまさん―The Bear―』だ。冒頭、謎の殺人者が「森のくまさん」を口ずさみながら被害者を惨殺していくシーンの面白さは、半端ではない。残虐な行為ととぼけた口調が何とも言えない味を醸し出している。だが、後半に行くにつれ、中途半端なシリアルキラー物に成り下がり、せっかくの長所を活かしきれていないのが惜しまれる。文章力をもっと磨き、次作では揺るぎないプロットを打ち立てて、ぜひ捲土重来を期して欲しい。
安定した文章力を持ち、所々に上手さが光る『ハナカマキリの変容』だが、如何せんインパクトに欠ける。変容悪女物の既存作品を上回る何かがあれば、出版にこぎつけることも可能だったろう。次回はぜひ、「新しい作品」で挑戦していただきたい。
西洋幽霊譚は嫌いではないが、『ホークウッドの亡霊』は小説的にあまりにも幼すぎる。仮に仕掛けの面白さ(ネタに前例はあるが)を買うにしても、文章力や人物造形がレベルに達していない。小説的なコクがないので、ネタが割れても「ふーん」としか思えないのだ。残念だが、最終はまだ敷居が高い、と言わざるを得ない。
『このミス』大賞は、来年でいよいよ10回目を迎える。赤ペンを使うのを忘れるほどの応募作と、あるいは感嘆符付きの賞賛を書き込むほどの傑作と、またまみえたいものである。
吉野仁
いまの流行ではなく、次の時代を先取りせよ
個人的にはとても楽な選考だった。乾緑郎『完全なる首長竜の日』が質も内容も群を抜いて優れていたからだ。第一線で活躍しているプロ作家と比べても遜色がないほど細部までよく描かれており、選考を忘れ、単なる一読者として楽しませてもらったほどだ。
とくにヒロインである少女漫画家の世界がきわめてリアル。もちろん本業の方が読めばおかしな点がいくつかあるかもしれないが、アシスタントや担当編集者と仕事を進めていく日常がとても自然に描写されている。
さらには、過去の回想、昏睡状態で入院している弟へ面会に訪れる場面など、徐々にヒロインが抱える秘密が明かされていく展開は、それだけで静かなサスペンスを感じさせられた。いわゆる犯人探しのミステリではないものの、背後に隠された謎の暗示力、もしくは、これからどのように真相が暴露されていくのかという興味の牽引力がものすごく強いのだ。文章や会話など、基本的な小説を形作る部分も達者。文句のつけようもない。
すでに作者は今年度の朝日時代小説大賞を『忍法煙之末』で受賞している。このダブル受賞でより多くの読者を獲得することだろう。いまからデビュー後の活躍が楽しみだ。
さて、問題は残りの5作である。
優秀賞を受賞した喜多喜久『有機をもって恋をせよ』は、まったくの学園ラブコメ。なんと主人公は、有機化学が専門の大学院生で、合成ルートの天才的なひらめきをもつ男。モデルが東京大学だったり大学研究室の日常が詳細に描かれていたりするなど、もてない理系大学生のユニークな恋の模様をとても楽しく読むことができた。
だが、これが「日本ラブストーリー大賞」の応募作ならば、なんの不満もないものの、やはりなんらかの魅力的な謎やはらはらどきどきするサスペンスが話の中心にほしいところ。個人的には、今回は優秀賞なし、でいいと思うのだが、他に推薦する作品もなく、『有機をもって恋をせよ』の優秀賞受賞に強く反対はしなかった。
もう1作の佐藤菁南『羽根と鎖』は、児童虐待をテーマに、ある人物が事件の関係者に話を聞いて回るというモノローグ形式で書かれた作品だ。すなわち、章ごとに様々な人物の「ひとり語り」が展開していく。大ヒットした湊かなえ『告白』と同じようなスタイルながら、こちらは次々に人物が変わり、それぞれの語りも大げさで冗長すぎるためか、いささか読むのがしんどかった。物語を外からみる視点がないせいだろう。たしかに筆力はあるので、あえて優秀賞に反対しなかったが、ぜひ、いまの流行のスタイルや書き尽くされたテーマではなく、今後はだれも挑戦していないミステリに取り組んでほしい。
残りの3本のうち、出だしを読んで期待できたのは、堀内公太郎『森のくまさん―The Bear―』だった。「森のくまさん」を名乗る何者かが、死ぬべき悪人と判断した連中を次々に残虐に殺していくという物語。わざと幼稚で安っぽい調子で書いているのではと思わせる文体と挑発的な内容が光っていた。ところが、後半、真犯人が明らかになったとたんにトーンダウンするばかりか、ぐだぐだに混乱したままエンディングをむかえてしまった。極端にいえば作品を支えていたのがワンアイデアのみだったようにも思えてしまう。魅力ある登場人物がいないのも大きい。筆力があるだけに残念だ。
そして、美輪宙『ハナカマキリの変容』。目をつけた誰かに近づいては殺し、その人になりすましていく女の物語。先を読ませるサスペンス工夫が凝らされている一方、文章の粗さや凡庸な内容が目立ってしまった。ひどく悪いわけではないが、それ以上の面白さもない。ひとつには人物が役割でしかないせいか。思わず感情移入してしまうヒロイン、もしくは悪魔的な魅力を放つ女が描かれていれば、もっと評価は高かっただろう。
最後に高山深雪『ホークウッドの亡霊』だが、厳しくいえば予備選考の1次ですら通過するかどうかという低いレベルだと感じた。とくに文章力があまりにも未熟。もっとも英国貴族の邸宅をそのまま日本に移築した、という大胆な設定のもと、本場のゴーストストーリー+現代日本ミステリを作りあげた発想は大いに買う。しかし、それを生かすための、文章力や構成力が足りないのだ。まずは、人を物語世界に引きつけるための、巧みな語りを身につけてほしい。誰の視点で何をどういう順番で分かりやすく語っていくのか。サスペンスを感じさせることができるのか。数々の名作を参考のうえ、新たなミステリをどんどん書き上げていただきたいです。
さて、本賞も来年でいよいよ第10回をむかえる。毎年のように繰り返す言葉だが、こちらが読みたいのは斬新なミステリだ。これまで誰も書いたことのない面白さ。もちろん高い完成度であること。細部までおろそかにせず、ていねいに作られた作品。期待している。