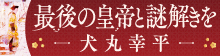第6回『このミス』大賞 最終選考選評
大森望(おおもり・のぞみ)
いよいよ茶木則雄選考委員と正面から激突する時が来たか…
前回の選評でさんざん愚痴を言った効果なのかどうか、今回の候補作は適切な長さの作品が多く、しかも最終に残ったのは5本だけ。去年の苦労がウソのように、おおむね楽しく、すんなり読み終えることができた。
作品の平均レベルも非常に高く、1本を除いては、そのまま商業出版されていてもおかしくない即戦力だ。
中でもエンターテインメント的によくできていたのが、中村啓『彷徨える犬たち』。歌舞伎町を舞台にした、あからさまに馳星周タッチの警察ノワールだが、あんまり破滅的な方向へは進まず、軽ノワール(?)にギリギリ踏みとどまっているのでリーダビリティは非常に高い。数年前なら、ノベルスですぐに出版の声がかかったタイプ。ただし、いま新人賞から出るには新鮮味と個性が足りない。たとえば主人公の一人称を“おれ”から“僕”に変えて、村上春樹っぽい文体で書いてみるとか、なにかミスマッチな要素を導入して独自性を出す工夫が必要だろう。
それ以上に惜しかったのが、森川楓子『林檎と蛇のゲーム』。中学3年生のヒロインは魅力的だし、脇役の水野も抜群にキャラが立っている。現金1億円入りのバッグをかついで逃避行という趣向も面白い。理論社〈ミステリーYA!〉みたいなヤングアダルト系の叢書なら、このままでいますぐ出版できるし、ドラマ化の可能性もあるんじゃないですか。
実際、途中までは、よし、今年の大賞はこれで決まりだ、いよいよ茶木則雄選考員と正面から激突する時が来たか──と思いながら読んでいた。
しかし残念ながら、だんだんテンションが下がってゆく。チャカチャカしたゲーム的なプロットに対して、事件自体はけっこう陰惨だったり、少女売春が出てきたり、リアリティのバランスがどうも一定しない。どっちつかずの中途半端さと線の細さが最後まで解消されず、小さくまとまって終わってしまう。やはり大賞は無理か。ではせめて優秀賞に……と思って選考会に臨んだが、サスペンスに欠けるとか、プロ作家の応募作なんだからこのレベルで優秀賞を出すのはおかしいとかの意見に強く反対できなかった。少女時代の水野さんの話など、抜群に面白いエピソードが随所に出てくるので、なんらかのかたちで出版されることに期待したい。
一方、エンターテインメントとして一定のレベルに達していることは認めるものの、個人的にまったく評価できなかったのが中山七里『魔女は甦る』。外資系製薬会社が陰謀を企む話にはいいかげんうんざりしているので、アイデアによほど説得力がないかぎり高い点はつけられない。出だしは快調で、途中まではけっこう面白く読んだが、ヒートなる架空のドラッグの正体が明かされたあたりで急速に興味を失い、あとは惰性。科学的なディテールに立ち入るなら、せめてもうちょっと説得力を持たせる努力をしてくれないと、ただのトンデモ科学サスペンスになってしまう。ま、そういう部分が気にならない読者もいるでしょうが。
5本の中ではいちばん完成度が低くて、唯一、このままで出版するのは絶対ムリだと思ったのが、桂修司『明治二十四年のオウガア』。冒頭の吸引力はいちばん強く、半分ぐらいまではぐいぐい読まされたが、後半三分の一のひどさは目を覆わんばかり。鈴木光司『リング』の線を狙ったオカルトサスペンスだが、そもそも話の辻褄がまったく合ってないし、好意的に解釈しようとしても、著者がなにをやりたかったのかさえよくわからない。
したがって、「魔女は甦る」と並んで最低点をつけたが、面白い部分だけをとりだして勝負すれば、たしかに今回の候補作で一、二を争う力がある。コントロールはめちゃくちゃだがとにかく肩が強い高校生ピッチャーみたいなもんで、このストーリーテリング力は貴重。コントロールはこれからの練習で獲得できるということで、後半を全面的に書き直すことを条件に、優秀賞授賞に賛同した。
というわけで、大賞が出るならこれしかないと思っていた拓未紀司『禁断のパンダ』が、予想どおり、4人中3人の票を集めてあっさりゴール。
こちらの美点もミステリー部分ではなく、美食パート。冒頭、フレンチ・レストラン〈キュイジーヌ・ド・デュウ〉を借り切った結婚披露宴の食事シーンから、唾が湧くほどリアルでイメージ喚起力豊かな描写が読者を鷲掴みにする。料理を提供する側から描く〈ビストロ・コウタ〉の場面もすばらしい。それに引き替え、警察側の描写は通りいっぺんのルーティンワーク。刑事コンビも類型的で、キャラが立っているとはいいがたい。見え見えのオチも含めて、ミステリーとしては構成に難がある。
しかし、グルメ小説的な魅力は、ミステリー部分の欠点を補ってあまりあるし、どこが悪いかははっきりしているので修正しやすい。フレンチの天才シェフが活躍する神戸グルメ・ミステリーというだけでもウリは強力。ぜひシリーズ化してほしい。読んでいると、値段とカロリーの高い料理を食べたくなるのが欠点です。
香山ニ三郎
荒削りでも先読みを許さない大スケールのものを優先したい
今年も本命なきがゆえの混戦模様だったりしたらどうしようという一抹の不安はあったが、最初に手に取った作品に手応えありで、まずはひと安心。その作品、中山七里『魔女は甦る』は埼玉県所沢市郊外で老若男女の区別さえつかない凄惨なバラバラ死体が発見されるところから幕を開ける警察捜査小説だ。
ほどなく被害者は近所の外資系製薬会社に勤める研究者であることが判明、やがて彼の異様な半生の軌跡が明らかにされていくが、そこに麻薬犯罪を絡める手際も熟れているし、一見地味だが有能な所轄の刑事と警視庁のエリート刑事とのコンビぶりも悪くない。怪物ホラーに転じる後半も迫力充分だ。ただ問題は話作りがストレート過ぎて、真相も読みやすいこと。大賞作品として考えると、ひねり技不足といわざるを得ないが、結論を出すのは他の四作と比較してからでも遅くはないということで、取りあえずペンディング。
続いて読んだのは、森川楓子『林檎と蛇のゲーム』。母親を交通事故で失い父とふたり暮しの女子中学生が、父の海外出張中、彼の幼馴染みという女性と暮らす羽目に。ふたりは初日から冷戦状態で、翌日さらに愛猫が行方不明になったあげく死体で発見される事件まで起きる。娘は犯人とおぼしき近所の猫嫌いの変人の家に抗議にいくが、そこで見たのは血まみれになった住人の姿だった……。
と書くと、いかにもありがちなドメスティックサスペンスふうだが、そこから女ふたりの逃亡劇に父と幼馴染みの少年時代の交際劇が交わり、先の読めない犯罪劇の様相を呈していく。後半事件の真相が意外な人物からさらりと明かされるなど謎解きの妙は薄いけど、何といっても女性主体の活き活きとした活劇演出が楽しい。大賞は無理でも優秀作ならと思ったが、強い反対意見が出たため授賞はかなわなかった。こうなったら賞の枠外での出版を狙うぞっ、というわけで、ガーリッシュな軽活劇が好きな人はぜひご一読を!
三番目の中村啓『彷徨える犬たち』は新宿歌舞伎町を舞台にした悪徳警官もの。新宿署の組織犯罪対策課の狂犬“鬼の弘美ちゃん”こと綾瀬弘美と警視庁から出向中のエリート刑事・廣司悠人のコンビが歌舞伎町のラブホテルで起きたやくざ殺しの捜査に乗り出す。闇の世界と癒着した弘美ちゃんの暴走ぶりも酷いが、エリートの廣司にも実は秘密が、というわけで、お馴染みジェイムズ・エルロイ直系のノワールタッチ。最近の歌舞伎町は都知事の指揮下、すっかり浄化されたとも聞くし、どうせなら都内近郊や湾岸の架空の街とかにしたほうがむしろリアルだったかも。文章も荒く、個人的には高い点は付けられなかったが、ノワール系警察小説にこだわるのなら、黒川博行『悪果』等を参照しつつ、今いちど設定から練り直し再挑戦してほしい。
残るは二作。拓未紀司『禁断のパンダ』は動物小説っぽいタイトルながら、実は美食系ミステリー。神戸でフレンチのビストロを営む青年が妊娠中の妻ともども彼女の友人の結婚式に出席するが、夫の目当ては料理にあった。それを準備したのは会場に隣接したフレンチレストランで、物語はその絶品料理にまつわるドラマと、同時期に起きた運送会社の部長殺しの捜査とが並行して描かれていく。
こちらの特長はずばり、料理描写にあり。とにかく美味そうなんである。魯山人めいた美食家爺のキャラも立っているし、随所で料理小説としての面白さが光る。ミステリーとしてはエキセントリックな二枚目刑事がちょいと浮き気味だし、『魔女は甦る』と同様、先が読みやすいという難点はあるが、表題の動物ネタでサスペンスを盛り上げるなど工夫は凝らされている。今回はこれで決まりかと思って選考会に臨んだら、最初の投票であっさり決定。作者はこのジャンルに新風を巻き起こせる人だと思う。期待してまっせ〜。
最後の桂修司『明治二十四年のオウガア』は、受刑者の変死が続いた岡山県の刑務所に弁護士が調査に赴くが、彼は事件があった保護房で突如目に異常をきたし、さらには自分に襲いかかるサーベルの男を幻視する。つかみという点では五作中随一といっても過言ではなく、しかも弁護士の目に宿ったダルマ型の黒い染みの謎と明治時代のひとりの虜囚の話とが交互に進む展開もスリリング。これはイケるかもと胸膨らませたが、残念ながら、後半失速。オウガアとは、精神病患者に異常を起こしている主体──正体不明のモノや鬼、悪魔オーカス等を意味するが、その研究者を探偵役に出しておきながら、呪いの謎解きにほとんど貢献しないし、これでは困ります。
しかしながら、よくある題材でまとまりのいいものより、荒削りでも先読みを許さない大スケールのものを優先したいという意見にはうなずかざるを得ず、この作品の優秀作授賞には反対しなかった。『魔女は甦る』には申し訳ないが、この作者はいつでもプロデビュー出来る実力をすでに備えている。ひねり技を駆使した先を読ませぬサスペンス演出で捲土重来を期していただきたい。
茶木則雄
これだけ素晴らしいければ、事件なんてどうでもいいしゃないか
今年の最終候補の平均レベルは、「『このミス』大賞」史上ベストと言ってもいい。商業出版されてそのまま本屋の店頭に並んでいても不思議でないものが3作。容易に指摘できる欠点はあるが、確かな将来性と煌めく才能を感じさせる、金剛石の原石が2作。まさしく粒の揃った年だった。
商業出版されていても不思議でない度が最も高かったのは、『林檎と蛇のゲーム』である。どこかのティーンズ文庫の収録作品だと言われても、まったく違和感がない。実際、作者はその分野で数十冊の著作がある人だと聞く。しかし大人のミステリーとして見た場合、余りにも稚拙すぎる。
ヤクザの親分が“林檎と蛇のゲーム”──まっとうな男の子が、大金を持つことでどう堕落していくか、もしくは堕落しないで有意義に活用するか──を愉しむため小学生に1億円(30年前の貨幣価値だからいまなら数億円規模)をくれてやる。その発想を非とするものではない。どんな突飛な発想であろうが設定であろうが、そこに説得力さえあればまったく問題はない。むしろ、そういう作品こそ本賞では求められている。だが、この作品には読者を納得させるような説得力がないのだ。リアリティなんていいじゃない、そういうゲームなんだから、というのでは所詮、子供の読み物であろう。ミステリーとして決定的に駄目なのは、謎の核心が、事実を知る者から主人公に順次、語られていく、というあるまじき構成である。それも最後は犯人側が接触して来てぺらぺら喋るのだから、推理もヘチマない。作者が頭の中で作った物語を、登場人物に都合よく語らせているだけだ。大人の小説をナメてもらっては困る。プロの作者に、このレベルで何らかの賞を出すのは論外と言わざるを得ない。厳しい言い方になったが、アマチュアではないだけに、ご海容いただきたい。もし本気で大人の新人賞を狙うなら、ティーンズ小説の延長戦上にあるものから離れた方がいいと思う。発想や語り口の才には、見るべきものがあるのだから。
次に並んでいても不思議じゃないのが、『彷徨える犬たち』だ。アウトロー文庫やノベルス新書で出版されていても、またかと思いながら結局、最後まで読んでしまうだろう。新鮮味もないが大きな破綻もない作品である。参考資料をかなり読み込んだ跡が窺えるのには好感を抱くが、問題はその参考資料が容易に手に入るようなものばかりであるという点だ。よくぞ調べた、という驚きや感動がない。それっぽく作ってはあるが、アンダーグラウンドの匂い立つような臨場感は、残念ながら作中に醸し出されていないのである。アウトロー小説としては凡庸だが、警察小説として読ませる部分がないわけではない。そのあたりを狙いに、次回はもっと徹底した取材を施したらどうだろう。
受賞した2作以外で惜しまれるのは『魔女は甦る』だ。ラスト一行の凄絶さは抜群である。そこだけ見ても、この作者には明らかに才能がある。しかし惜しむらくは、結末にいたるまでのストーリーの流れが、ありきたりの謗(そし)りを免れない。随所に光る描写はある。ことにクライマックスの“敵”との格闘シーンは出色で、読みながら思わず「うわっ」と声が出たほどだ。ただ死んだ製薬会社社員の恋人のキャラクターが、私にはいまいち馴染めない。沢尻エリカ風の不機嫌さが、どうにも板に付いていないのだ。初対面の刑事に理由なくあんな不貞腐れた態度を取れるのは、本物のエリカ様くらいだろう。キャラクタライゼーションを磨き、斬新な展開を持ち込めば、来年の本命に成りうる逸材と見た。
受賞した2作は、ともにミステリーとしては欠点が多い作品だ。優秀作の『明治二十四年のオウガア』は後半の現代パートがぼろぼろで、張った伏線は中途半端だわ、謎の核心は読者に伝わりにくいわで、結局なにが言いたいのか、作者の真意を測りかねるあやふやな展開に終始する。おそらく、主人公の正から邪へのドラスティックな転換を描きたかったのだろうが、なにせ技量が伴っていない。好意的に解釈してやっとわかる程度だ。しかし、明治期のパートは文句なしに素晴らしい。明らかに小説としての風格がある。明治期の監獄や囚人による北海道開拓工事を描く筆致は、もはや練達の域に達していると言っても過言ではない。何よりも、これまで読んだことのないオリジナリティを感じさせる点が、最大の長所だろう。大幅に改稿すれば、原石の輝きが眩いばかりに表出する可能性、大いにありだ。
大賞に決定した『禁断のパンダ』は、他のミステリー新人賞では最終に残るのも危うい作品だと思う。ミステリーとしては、お世辞にもよく出来たとは言えない作品だからだ。謎の構成は脆弱、サスペンスは希薄、捜査小説としては凡庸。はっきり言って殺人捜査のパートには、ほとんど見るべきものがない。しかし──しかしである。それを補って余りある長所がある。稀に見る出来栄えの美食パートだ。これは本当に、凄い。食材と調理法の豊富な知識もさることながら、味覚そのものをここまで的確かつ典雅に描く筆致は、只事でない。まさしく、本邦初の本格的美食ミステリー(本格的はむろん美食にかかる)だ。
かつてディック・フランシスを評して言った青木雨彦の顰(ひそみ)に倣えば、これだけ(キャラクターがではなく美食パートが)素晴らしければ、事件なんてどうだっていいじゃないか。
こういう作品に大賞を与えられたことを、選考委員として誇りに思う。
吉野仁
第三者に読ませて破綻している部分を直した上で応募を
今回、「文句なしにこれ」というのはなかったものの、総じてレベルが高かった。文章や会話、場面ごとの描き方などが、しっかりしている。その分、気になったのが全体を貫くストーリーの問題だ。話の組み立てに不満を抱く作品が多かった。
まず受賞作『禁断のパンダ』だが、他の選考委員がのきなみ最高点数を与えていたのに対して、わたし一人がもっとも低い評価。確かに「グルメ」の部分や登場人物たちのやりとりは最高に面白い。「このグルメ小説がすごい」大賞ならば文句はない。だが、肝心の殺人事件を中心としたミステリーとしての構成がぎくしゃくしているのだ。主人公が事件を追いかけて(巻き込まれて)いくのか、それとも警察主導で捜査するのか、中盤まではっきりしない。ある場面が全体のストーリーのなかで、どういう役割になっているのか、つかみづらい。とくに冒頭から事件が起こるまでの流れが悪すぎる。過剰な説明をしている地の文も目立った。
すなわち、グルメ場面が、話の中心となるべき軸(殺人の謎をめぐる展開)から浮いているのだ。ゆえに「この先、いったいどうなっていくんだろう」というサスペンスが感じられない。「ムダのないプロット」は、ミステリーに限らず長編の娯楽小説を書くうえで必ずおさえておくべき要素だろう。
しかし、本賞は書き直しを前提にした賞である。他の選考委員も同じく「構成のまずさ」に触れており、修正することを条件として大賞受賞に同意した。単行本として刊行された受賞作は、われわれが選考時に読んだものと大きく違っているはずだ。より完成度の高い作品に仕上がっていることを願う。
同じく他の二人の選考委員の評価が比較的高かったにもかかわらずわたしが最低点をつけた作品が『林檎と蛇のゲーム』だった。前回の受賞作『ブレイクスルー・トライアル』につけた注文とほぼ同じで、「登場人物たちの過去の因縁に合わせるかのような設定、シリアスなのか冗談なのかはっきりしない展開」に難をおぼえた。不自然な部分があまりに多く、それに対してなんら納得できる説明(エクスキューズ)が書かれていない。「およそ現実にはありえない話が作者の都合どおりに語られていく」作品である。
どうも、とんでもない設定をそのまま読み手に受け入れさせるだけの筆力に欠けているのだ。人物のディフォルメを明確にすること。ご都合主義の部分を徹底的に洗い出すこと。この二点を直さないかぎり、いつまでも単なる子供だましのミステリーに終わってしまうだろう。
一方、わたしが今回の最終選考のなかで、もっともストーリーとしてよく出来ていたと思ったのは『魔女は甦る』だった。たしかに他の選考委員が指摘していたとおり、「外資系の製薬会社の陰謀」という手垢のついた安易な設定は大きなマイナスだろうし、とくに斬新なアイデアや優れた人物描写があるわけでもない。そのため、受賞作として強く推すことは出来なかった。それでも、とくに後半の「敵」との攻防は、単なる陰謀ミステリーに終わらず、スリラーとしての醍醐味を楽しませてくれたし、ラストの場面は非常に印象深かった。筆力は十分にある。他にないアイデアや強い個性を盛り込み、ぜひ今後も書き続けて応募してほしい。
次に『彷徨える犬たち』は、全体によく書けてはいるものの、なにか既成の作品をなぞっただけで終わった感じだった。人物がみな型どおりで重み(軽みや空虚さでもいい)を感じさせない。パターンで書かれたある種の暴力/鬼畜小説に何ら関心のないわたしとしては、まとまりのよさを評価するくらいだ。たとえば幻冬舎「アウトロー大賞」に応募されたらいかがだろうか。このまま完成度を高めれば、定型的な暴力/鬼畜小説ファン(?)には受ける作風のようにも思う。
優秀賞に選ばれた『明治二十四年のオウガア』は、現代に起きた不可解な連続死と過去の因縁をめぐるホラー作だが、こちらもまた物語の軸がはっきりせず、どんどん拡散していったまま収拾がつかなくなって終わったという作品だった。主人公が、事件に関連したオカルト分野を研究している専門家にあっさりとたどりつくなど、あちこちご都合主義のところも目立つ。
しかしながら、とくに過去(明治時代)の章に関するエピソードに惹きつけられるような場面が多く、なんともいえない個性を感じさせる小説でもあった。荒削りの魅力だ。こちらも全体の修正を条件として優秀賞として選ぶことに賛同した。
全作品に言えることだが、出来れば書きあげた後に小説好きの知り合いなど第三者に読ませ、明らかに破綻している部分があるかどうか指摘してもらい、それを直したうえで応募すれば、より完成度も高くなるだろう。