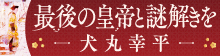第6回『このミス』大賞 1次通過作品
『笑いの神がいるのなら』 田中宏昌
三十歳の太一は、中学三年生の妹モナと組んで漫才コンビ・アニイモンを結成し、新人賞を獲得する。その後もとんとん拍子にスターへの階段を上っていく彼等だったが、ある日、太一のもとにフリーライターの江藤という男がやってくる。太一の父親が過去に起こした事件のことで、彼を脅迫してきたのだ。モナにも教えていない父親の卑劣な犯罪行為。それを隠し通す決意を太一は固める。江藤を殺そうというのだ……。
年の差のある兄妹漫才コンビとして急速に売れていく姿、そして売れてからも驕らずにいる姿の描写が、まず素晴らしい。駆け出し時代の仲間との対比や先輩との交流など、様々な角度から彼等の状況を描く一方で、彼等自身の真面目さ、ひたむきさを的確に読者に伝えているのだ。このあたりの描写力は新人離れした安定感を備えており、とにかく作品世界に引きずり込まれる。さらに、そうした成功によって江藤が登場し、そして太一が殺人に追い込まれていく心の動きにも説得力があり好感が持てる(年の差のある兄妹という設定が活きている)。サスペンス劇を読ませるに十分な筆力といえよう。
さて、この小説の後半は、殺人から五年後の物語として描かれる。逃げ切ったかと思えた殺人にアニイモンが追いつかれるという、この構成もまた見事。事件に再度光を当てられる流れも自然だし、なにより決め手となる物証の出し方(言いかえるならば、その物証をそこまで隠しておく手腕)が素晴らしい。作者がミステリセンスに優れていることの物証でもある。
現実の芸能人を思い起こさせる描写や、表面的なミステリ色の薄さ、まだ刈り込めるであろうエピソードなど、いくつかの減点要素はあるが、全体としての完成度は高い。愉しく素直に読めて、しかも「あの描写がここで効いてくるのか!」という満足も味わえる一篇である。2次進出は当然といえよう。
(村上貴史)